新型コロナウイルスの第7波の混乱を教訓に、第8波では戦い方を変えている病院もある。
一度始めた対策を変えるのは難しいと言われる中、何を削ぎ落とし、緩和策とどうバランスを取るのか?
前編に引き続き、藤田医科大病院の副院長で、救急総合内科教授の岩田充永さんに聞いた。

※インタビューは12月26日に行い、その時点の情報に基づいている。
院内で感染者が出ることには慣れてきている
——(インタビュー中に電話に出た先生の受け答えを聞いて)院内で感染者が出たのですか?
今、一つの病棟で感染者が出たようですが、もう不思議なことではありません。スタッフもみんな入院患者や職員から陽性者が出ることには慣れてきました。
流行初期はそんな知らせがあると3日間は寝られませんでしたが、今は「そういうこともあるよね」という感じです。
——7波では感染者が少なくて今、大変になっている地域ではまた違う状況でしょうね。
沖縄から首都圏、名古屋などは7波でつらい思いをしましたが、どこでもいずれ暴風雨は経験してしまうと思います。
——第7波で苦しんだ首都圏ですが、第8波も大変だという声が上がっています。
先日、別地域の医師たちと話したのですが、「みんなで診よう」という感覚がなかなか生まれにくい地域では、一部の急性期病院に皺寄せが来ているようです。
我々も7波のお盆休みの頃に、救急外来が発熱した患者でパンクして大変なことになったのですが、逆に言うと、普段開業医の先生たちが発熱患者を診てくれていたことを実感しました。
今年の年末年始もおそらく開業医の先生は休診するので、僕ら大学病院は大変になるから備えようと思っています。でもそれは普段、発熱患者を開業医の先生が診てくれている裏返しでもあります。
東京や大阪で今、大変なのは、そうした地域全体の診療体制をさらに改善してゆくことを求められているのかもしれません。
とはいえ、僕たちも決して余裕があるわけではありません。僕らは入院患者や重症者が増えたらどうしようという恐怖感よりも、職員が感染や濃厚接触で出勤できなくなったら回らなくなる、という恐怖感が常にあります。
院内感染、許容できるか?
今、入院する時のPCR検査を多くの医療機関がやっていますが、入院時は陰性で、その後陽性になって「すり抜けだ」などと言っています。
しかしウイルスが院内に入ってくるのは、患者さんが持ち込む、付き添いの人が持ち込む、無症状で感染を自覚しない医療者が持ち込むなどと、さまざまなルートがあります。
無症状の医療者が持ち込むのは誰も悪くないし、無症状で感染の自覚がなかったらわざわざ検査なんかしないで医療を守るために働くのは当たり前です。
「感染を許容する」と言うと問題かもしれませんが、どこにいたって感染しておかしくない。そんな前提で動かなくてはいけないことを医療者以外の方たちにも理解してもらわなければいけません。

——流行当初と比べて、「院内感染が起きた」と言ってその病院を責めることはなくなってきている気がします。
でもかかったら重症化が防ぎきれない患者さんたちが院内にはいます。そういう方が院内で感染してしまうことはやはりショックなことです。
——病院スタッフの皆さんは持ち込まないために感染リスクを避ける生活を続けているのでしょうか?
同じ部署での忘年会などはまずやりません。医療者の倫理観とか崇高なことではなく、純粋に同じ部署で忘年会をやって感染者が複数出ると、次の日から診療が回らなくなるからです。
他部署の人同士が少人数で集まるのは許容できたとしても、同じ部署で集まるのはやめてくれと伝えています。もっと厳しいルールを設けている病院もあると思います。
健康な人はどう行動すべき?
——重症化リスクが少ない健康な人はこの年末年始、どう行動するべきでしょう?
ワクチンをうっている人の大半は、感染してもいわゆる「風邪」で済みます。自分の周りにかかったら重症化する人たちがいないかをまず考える。もしそういう人がいるなら事前に抗原検査キットで検査し、体調が悪かったら会わないようにすることが大事です。
それ以上、過剰に恐れる必要はありません。ただ医療者も感染するので、感染が広がれば、ベッドはあるのに医療者が出勤できなくなって病院の機能が十分に発揮できない恐れはあります。
でもそれを防ぐために何ができるか考えるとなかなか難しい。
国は濃厚接触者でも医療が逼迫すれば出勤してもいいと言っていますが、そこから院内に感染が広がってもみんな受け入れましょうね、というところまで伝えていません。
何かを緩和したらそこで起きる不都合なことまで責任を持って伝えてほしい。感染者の隔離期間も10日から7日に短縮されました。でも研究では、8日目、9日目も感染させるリスクは当然、残ります。
国が「短縮によって感染が広がるリスクがありますが、それを認めていきましょう」とまで言ってくれないと、医療機関としては「国が隔離期間を短縮しかたら、8日目から復帰ね」とは言いにくいです。
——先生の病院では10日間の隔離ですか?
僕のところでは10日にしています。職務復帰は11日目から。復帰した医療者から感染を広げたくないからです。でもそれによって職員の減少は厳しいことになっています。
リスクを考えて自分で判断することが苦手な国民
——そういう意味では市中感染を広げないために一般の人にも協力してほしいのではないですか?
でも9割9分の感染者が喉の痛みやガラガラ声で終わってしまう病気で、感染を減らそうという力は働きにくい。感染者を減らすためにみんなが自粛したら、3年目の今度こそ、飲食業や観光業の人は大変なことになりそうです。
コロナの流行では、最初は「医療者ありがとう!」と持ち上げられ、増えてきたら「大変ですね」という取材が入り、波が終わると「Go Toキャンペーン」が始まる。そして増えてくると「大変ですね」とまた言われる。本当に不思議な3年間を過ごしてきました。
僕は医療は社会生活の一部にすぎないと思っています。「医療者が大変だから飲食業が我慢しましょう」というのは絶対に間違いです。
——私も今、飲食業でアルバイトをしていて、やはりお客さんが少ないと経営が厳しいのを実感するし、お客さんがたくさん入ると嬉しいのですね。コロナの感染拡大は頭にありつつも、立ち位置が違うと捉え方が違ってくるのを感じます。
そこで岡部信彦先生は「いきなり全開はダメだよ」という言い方をされてていますね。でも全開にするか、8割にするかは難しい。僕自身「今日は8割で飲もう」とかはできません(笑)。
もちろん飲み会は人数が少ない方が感染が広がるリスクは少ないし、被害も抑えやすいです。
ただ、僕らが「感染すると人生が終わってしまうかもしれないから外出を控えてください。飲食を控えてください」と言えたのは、ワクチンが行き渡る前の第4波までです。
その後は重症化する人が減る中で、それでも重症化する人が一部いるため、自分はどう行動するかという一段難しい判断を一人ひとりが求められています。
今まで、こうやって勉強したら試験に通る、というようなマニュアル的な教育ばかり受けてきた僕らは、自分のリスクの程度を考えて行動することがすごく苦手です。これは日本の教育の成果かなとイヤミの一つも言いたくなります。
自分の身は自分で守り、高齢者は「もしもの時」の話し合いも
——それにしても、重症化リスクの高い人に自分の身は自分で守れ、と言うのは酷な気がします。
施設の方やそういう人を介護している家族は、世の中が緩和する流れにあっても、ものすごく気を遣っています。高齢者や医療ケア児の御家族のストレスはむしろ増えていると推察します。
このギャップのなかで僕が医療や救急の立場から言えることは何かと考えると、そういう人たちが体調を崩して陽性になったとわかったら早く重症化予防する薬につながってほしいという結論になってしまうのです。
そのためにも、病院の医療従事者が減っていって医療が回らなくなったらどうしようという恐怖感はずっとあります。
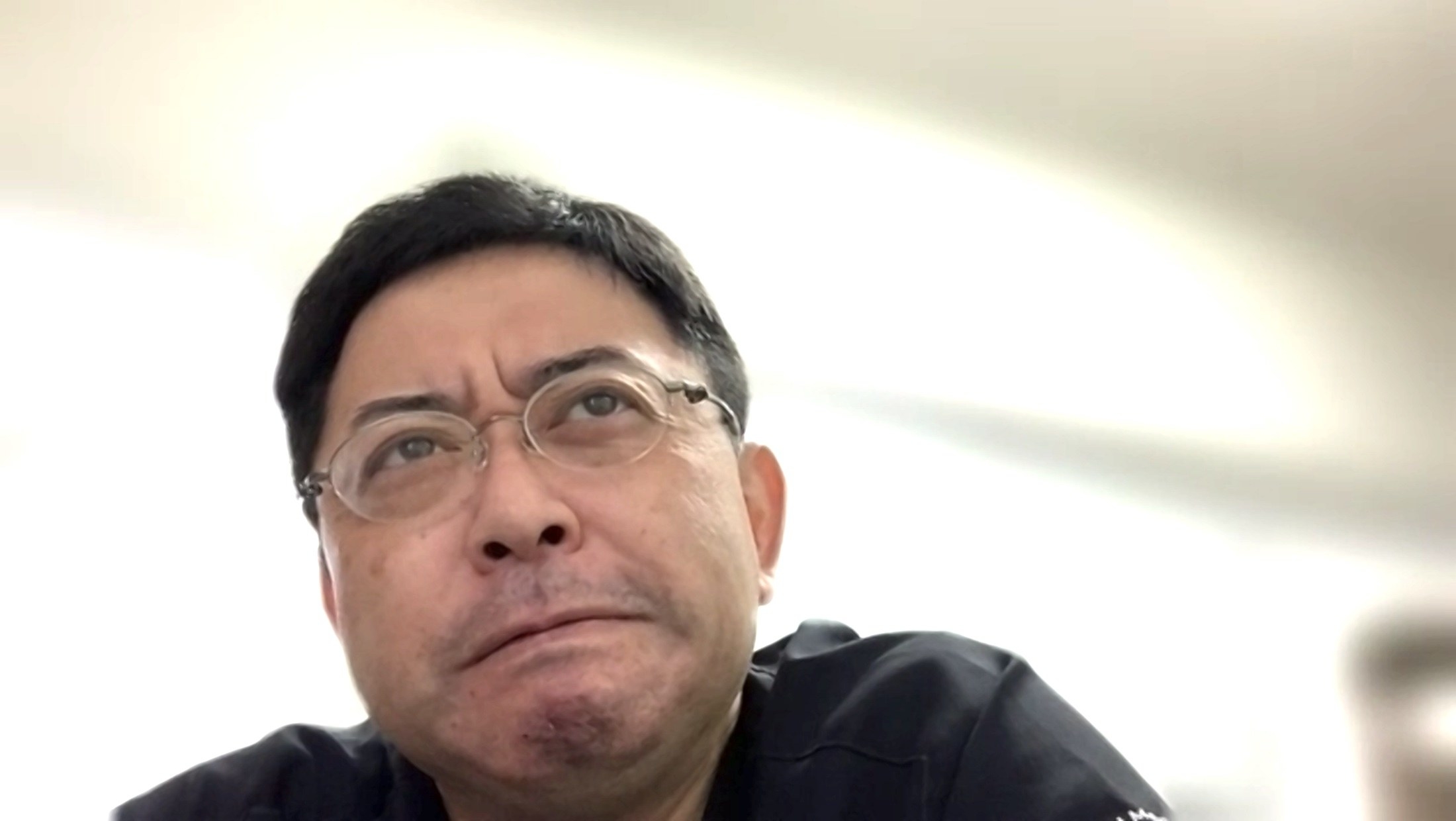
だからといって、飲食業や観光業にこれ以上我慢しろなんてとても言えない。そういうところのバランスを見ながら判断するのが、本当は政治の役割なんでしょうね。
結局、多数派の人が恩恵を被るように舵を切っているのが現状です。この流れで行くと、今後は陽性になっても隔離期間を設けなくなるのかもしれません。
そうなった時に、感染が広がることは織り込み済みでしょう。だから、少数で重症化を防ぐことができない人は、せめて早く検査して重症化を予防して御自身の身を守ってほしいと心から呼びかけたいのです。
高齢者はインフルエンザの流行時もこうしたリスクに晒されてきたことを考えるならば、コロナでそうなった時に、自分の人生はどうあるべきなのかを考えなければならないかもしれません。
もしもの時にどういう医療やケアを受けたいのか、受けたくないのか話し合う「アドバンスケアプランニング」もしっかりしておく必要があるのではないでしょうか?
検査も強制はできない
——健康な人の備えとしては、やはり抗原検査キットや解熱剤を準備して、体調が悪化しない限り、自宅で療養してほしいという感じでしょうか?
おそらく感染して自分の生活がストップすることを恐れて、解熱剤だけ飲んであえて検査していない人もいると思います。そういう人たちを全て見つけ出して検査する段階ではなくなっており、どこまで検査を強制していいのかもわからなくなっています。
街角でマスクをしていない人を責められないのと同じです。そういうことで人間関係がギスギスしている話はよく聞きます。
——しかし医療者としては、症状があったら検査をして、陽性だったら自主隔離してほしいと思いませんか?
これまで、毎年、医療従事者の中では、「インフルエンザの抗原検査キットで検査するのは意味がない」とか、「タミフルを飲んでも症状を1日短くするだけだから意味がない」と言う主張も多くありました。
インフルエンザにかかったと思ったら、解熱後2日までは家にいて、わざわざ病院に診断を求めにくる必要はないと言ってきたのです。コロナもだんだんそれに近づいてきているのを感じます。
むしろ今は、「元気な人は診断を受けるために医療機関に来ないで、自分たちで検査して療養してください」という発信が増えています。その時、そもそも検査をする気のない人に「絶対にしてください」と言うべきなのかは悩みます。
——流行拡大を抑えるために、本当は陽性者に自己隔離してほしいわけですよね。
医療者としては本当はそうしてほしい。でもそれは今、お願いベースでしか呼びかけられません。その状態が「ウィズコロナ」だとするならば、自分がかかったら本当に大変な人が、自分で身を守るしかないだろうと思います。
重症化を防ぐためにワクチンはうった方がいい
——非常にシビアで現実的な提案ですね。健康な人は少なくともワクチンはうっておいてほしいですか?
比較的若い、50代とかでワクチンを一度もうっていない人が、昔のような重症肺炎になり、ECMO(体外式膜型人工肺)を検討する状態になったりしています。
ワクチンは重症化予防のために接種するものです。ワクチンをうっても感染はしますが、重症者が減っているのは明らかにワクチンの恩恵と体感しています。うった方がいいと思います。
入院時のPCR検査も廃止 病院の防御体制も合理化
僕らは予定入院時のPCR検査も11月からやめました(緊急入院での抗原検査は行っています)。
全入院患者PCRを施行しても、全国的に病棟で複数の感染者が発生していることを考えると、結局、患者の持ち込み、付き添いの持ち込み、医療者の持ち込みのどれが高いか考えると、医療者の持ち込みが一番多いと考えるのです。患者ばかり水際対策をしても意味がありません。手続きが大変な割に、効果が薄い段階です。
その代わり、スタッフも患者も少しでも風邪症状があったら早めに検査し、そこから感染対策を徹底することにしています。
——そこまで合理的に割り切っているのですね。
学会などでこれを話すとざわつきます。逆に全入院患者にPCR検査をやっても、入院患者や職員から集団で陽性が出ていました。非常事態の時に始めたことはやめ方がわからないものです。それでも出口戦略はどこかで示さなければいけません。
——面会はどうしていますか?
面会は基本禁止にしていますが、療養上、主治医が必要と認めた場合は許可しています。ただし15分以内です。やはり緩和病棟の方の面会は大切な時間ですし、子どもの患者の付き添いはそれが療養の一環でもあります。
——合理的な判断ですね。
「全入院患者にPCR検査」は、いわばノーアウト満塁で1点もやらないという前進守備体制です。でも1回から9回まで常に前進守備体制でやれるわけがない。
だから「1点は仕方ないけど、大量失点は防ごう」みたいな守備体制が重要と考えるようになりました。
もちろん影響は検証していて、これまでの予定入院患者PCRの毎週の陽性率はほとんど0〜0.3%です。一番高かった7波のピークの時で1.5%です。大規模マラソンで走るランナーの当日のPCR陽性率は0.6〜0.9%とピークの時は言われていました。
そう考えると、よほど無症状で働いている職員の方がリスクが高いのです。だから症状が出たら早めに検査、に方針を切り替えました。もちろんそれでも継続するべきだという診療科は診療科の判断でやってもらっています。
でも、そのような病棟でも感染者が発生するリスクは想定しておかなければならないということです。
一つの作戦に固執しないように
現在のコロナ対策は、災害の時の戦術のようです。『Disaster Rules(災害時のルール)』(ロブ・ラッセルら著)という本があるのですが、そこに「計画一つは無計画」とか「戦いが始まったら一つの作戦に固執してはいけない」と書かれています。
コロナも段階によって、対策を変えていかなければいけません。それを今、強く感じています。
(終わり)
【岩田充永(いわた・みつなが)】藤田医科大学病院副院長、救急総合内科教授
1998年、名古屋市立大医学部卒業。同大学病院、名古屋大学病院、協立総合病院で内科・老年科・麻酔科を研修後に名古屋掖済会病院救命救急センターで勤務、名古屋大学大学院老年科学にて博士号取得。2008年より名古屋掖済会病院救命救急センター副救命救急センター長、12年10月藤田保健衛生大学救急総合内科准教授、14年4月同教授。2016年から2021年まで救命救急センター長併任。2020年8月より、副院長。日本救急医学会救急科専門医、指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本老年医学会老年病専門医。


