今年の冬に確実に来ると言われている新型コロナウイルス第6波に加え、心配なのは季節性インフルエンザの流行だ。
昨年は新型コロナの感染対策が功を奏して、インフルエンザも押さえ込んだが、今年はどうなのか?
コロナとの同時流行はあり得るのか?
BuzzFeed Japan Medicalは、国立感染症研究所の鈴木基・感染症疫学センター長に聞いた。
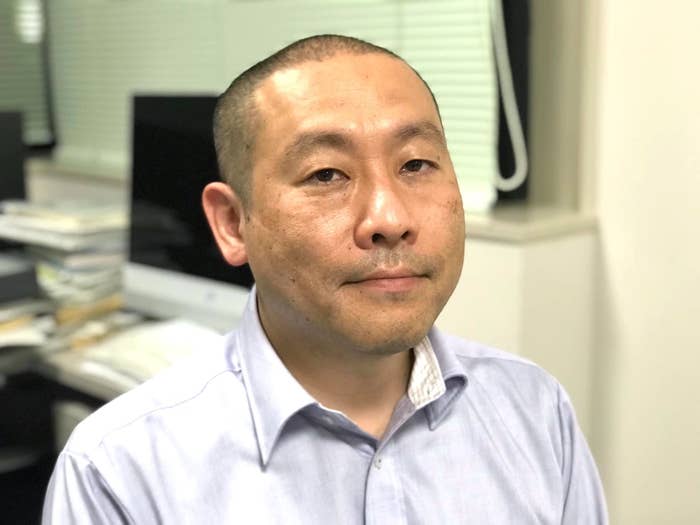
日本の冬の流行を占う南半球、赤道付近の流行
ーー今年はインフルエンザ、流行する可能性はありますか?
新型コロナ流行の前から感染研では国際的なインフルエンザの発生状況をサーベイランス(監視)しています。
インフルエンザは世界中で流行しているので、グローバルな視点に立ってみていくことが大切です。インフルエンザは温帯地域では毎年冬に流行します。また熱帯地域、赤道近辺では、夏冬関係なく通年で流行しています。
私たちが、日本も含めた北半球の温帯地域の流行を予想するときに、まずはその年の夏、南半球での流行がどうだったのか、どういう株が流行していたのかに注目します。熱帯地域でどういう株が流行しているのかも有用な情報です。
- 夏に南半球の流行はどうだったか
- 赤道付近の熱帯地域での流行はどうだったか
それを踏まえて、この夏、南半球でどうだったかをみてみると、オーストラリアやブラジルなどの南米のインフルエンザの流行状況は極めて低調でした。昨年の夏もそうです。ほとんど流行していない。
国によっては、新型コロナの流行の影響でインフルエンザのサーベイランスが例年通りに働いていない可能性もあります。例えばロックダウンの影響で病院を受診する人が減ったとか、新型コロナの検査が優先されてインフルエンザの検査がおろそかになったとか。
ただ、オーストラリアにはしっかりした監視システムがあって、あらかじめ決められた検査機関に集まったサンプルについては、コロナもインフルエンザも全て検査しています。
それにもかかわらず、ほとんど陽性は出ていない。
ということはほぼ間違いなく実際に流行していません。監視システムが探知できていないわけではなく、実際にオーストラリアでは夏から現在に至るまでインフルの流行は低調だった。
オーストラリアと比べると監視システムの精度が劣る国もありますが、南米各国の状況を見ても、やはり新型コロナ以前のような流行は見られません。
例年、南半球で流行していた株が、人の動きに伴い、熱帯地域を経て、北半球に上がってくると考えられます。
昨シーズンは日本でも流行は低調でした。そして南半球で今年、ほとんど流行していない。これらのことだけを考えると、この冬も、日本で大きな流行はないという予想になるかもしれません。
気になるのは、中国での流行
ただし、今、少し気になるのは、中国南部でインフルエンザB型が徐々に流行してきていることです。
ーーB型から流行することはよくあるのですか?
これまではほとんどないです。日本では例年A型が主体で、少し遅れて春近くになってB型が流行するパターンがほとんどです。
今回、B型の中でもビクトリア系統というタイプが中国で増えてきています。これが日本も含めた北半球の温帯地域の流行にどう影響してくるのか注意して見ていく必要があります。
ーーB型のビクトリア系統の症状で何か特徴的なものはあるのですか?
これまでB型はA型に比べて軽症だと言われてきましたが、最近の研究ではあまり違いはないのではないかという結果が出てきています。
いま中国で流行しているB型のビクトリア系統に特別な性質があるのかどうかについて情報はありません。
ーー中国でなぜ増えたのかはわかっているのですか?
それはわからないです。ただ明らかにどんどん増えていますので、一時的な現象ではなく、流行が拡大する理由が何か背景にあるのでしょう。それが何なのか、今は明確にはわかりません。
ーーインドでも一時増えていましたよね。
そうですね。夏場に流行の拡大がみられました。最初はA型が主体でしたが、そのあとはB型が主体になって、今は少し落ち着きつつあるようです。
コロナ流行中にインフルエンザが低調なわけ
ーーコロナが流行しているこの2年間、インフルエンザが低調だったのは、コロナの感染対策をしているからですか?
それが一番大きいでしょう。ほぼ間違いないです。
基本再生産数(※)はインフルエンザよりも新型コロナの方が高いです。インフルエンザは1.5から2ぐらい。新型コロナはデルタ株で5近いと言われています。
※何も対策していない時に一人の人から二次感染する平均人数
その新型コロナを抑えるためにあらゆる感染対策を講じているので、それより感染力が低いインフルエンザは自ずと抑えられていると考えられます。
ーー感染ルートを考えると、感染対策は一緒なわけですね。飛沫感染と接触感染だから、マスクや手洗い、3密回避ということですね。
そうですね。基本的に呼吸器ウイルスであることは一緒なので対策は変わりません。
飛沫感染という言葉については、これまで通りどこかで線引きして「空気感染」と区別するのか、あるいは幅広く「エアロゾル感染」と呼んで「空気感染」とみなすかなど、研究者の間で言葉の定義をめぐって議論があります。
ただ現象としていえば、小さい飛沫の粒子が空気中を漂って感染することがあり得るのは新型コロナもインフルエンザも変わりません。
コロナの第6波はいつ来るの?
ーーみんな気になるのは、コロナウイルスとの兼ね合いです。第6波は確実に来るとどの専門家も口を揃えています。まずコロナの第6波はいつ頃来そうだと予測されていますか?
今、第5波はグッと抑えこめている状態です。その要因は2つあると考えています。
まず何よりワクチンの効果です。
日本では短期間で非常に高い接種率を達成でき、今まで流行の主体だった20〜40代の活動性の高い世代にも高い接種率を実現しました。このおかげで大きく感染を抑えることができています。
もう一つは、人の動きは徐々に増えてきていますが、人のいるところでマスクをしっかりつけて、個々の場面で3密を回避したり換気を徹底したりするなど、私たちは非常に慎重に行動しています。日常の基本的な感染対策を維持している。
この2つの要因で第5波はしっかり抑えられています。
問題はこれから数ヶ月、どこまでそれを維持できるかです。
まず、ワクチンの効果が徐々に弱くなってきます。これはほぼ間違いないです。
ワクチンの有効性に関しては感染症疫学センターと複数の医療機関が協力してモニタリングしていますが、8月時点で87%という高い値です 。日本は急速に接種率が上昇したので、みんなうったばかりの状態です。最大限効果が発揮できているのが今です。
ただイスラエルやイギリスの報告によると、半年ぐらいで発症予防効果が減弱してきます。当初は90%近いのが、50%ぐらいまで減弱すると言われています。
日本でだけ高い効果が続くとは考えにくいでしょう。高齢者は4月頃の接種ですから既に半年ぐらい経ちました。これまで流行の主体を占めてきた活動性の高い20-40代は、7〜8月に一気にうちましたから、年末から年明けにかけて免疫が減弱してくると流行拡大のリスクになります。
ーー医療者が12月から接種を始めますが、活動性の高い年代も年明けぐらいに一気にブースター接種できませんかね。
2回目の接種から8ヶ月空けて全員にうつことになりましたので、お知らせのお手紙が来たら20〜40代の方々もぜひ接種を考えてほしいですね。
同時流行はあり得るの?
ーー今のところインフルはそれほど流行を思わせるデータはないわけですが、コロナの第6波は確実に来そうです。同時に流行る可能性もなきにしもあらずですか?
問題はコロナの第6波にも関連しますが、要因はワクチンの効果の減弱と、基本的な感染対策が緩むことです。
今は流行が落ち着いているので、人の動きが戻っている。マスクや三密回避などの基本的な対策も少しずつ緩んできています。
それでもワクチンで抑えこめているのが、ワクチンの効果も弱くなってくると、コロナの第6波が起こるだけではなく、基本的な感染対策で抑えこめているインフルエンザの流行も同時に発生する可能性は十分あります。
ーー喉が痛いとか咳が出るとか、両者は当初は似たような症状ですし、医療機関は混乱するのではないでしょうか?
インフルエンザの診療は日本の医療機関は何十年と経験していますし、コロナに関しても、感染対策の方法は違うとはいえ、この1年半各医療機関で体制を作ってきています。診療という点で言えば、医療現場が混乱することはそれほどないのではないかと期待しています。
ただ同時に大きな流行がおこると、当然それぞれの重症者数が増えます。
コロナに加えてインフルの負荷が上乗せされた時に、コロナだけで想定していた重症呼吸器感染症の入院医療のキャパシティを超えてしまい、医療の逼迫が起こる可能性はあります。
ーーただワクチンは半年で発症予防効果は減弱するとしても、重症化予防効果は維持されると言われています。それは希望にはなりませんか?
確かにそれは希望なのですが、最近、重症化予防の効果に関してもやはり徐々に減弱してくるという報告も出てきています。「重症化はしっかり守られるのだ」と安心してはいけないと思います。
「増殖力を失ったウイルスが自滅」仮説 「考えにくい」
ーー国立遺伝学研究所と新潟大のチームが、第5波が急速に収束した理由として、デルタ株のゲノムが変異して自ら死滅していったという仮説を提唱しています。どう受け止めましたか?
詳細がよくわかりませんし、学会でそう報告されたという報道で読んだ以上のことがわからないです。何か確証があると言えるデータをお持ちなのかもしれませんのでなんとも言えません。
ただ、報道されている内容を見る限りは、考えにくい仮説だと思いました。
ウイルス自身が増殖できなくなる変異を獲得することはあり得るかもしれませんが、増殖できなくなるにもかかわらず、それが従来のウイルスに置き換わって感染の主体を占めていくことは考えにくいです。矛盾しています。
シンプルにそれは疑問ですし、納得のいく説明が欲しいです。
ーーウイルスは増殖力、感染力の高い方が勝っていきますよね。従来株からアルファ株、アルファ株からデルタ株への置き換わりもそうでした。
生き残れないウイルスはただ単に消えていくだけです。それが普通の解釈だと思います。
研究者というのはいろいろな仮説を立てるもので、それ自体は否定すべきではありません。あとは研究者のコミュニティでしっかりと検証していく必要があります。
ヨーロッパ並みの流行あり得る? 経済対策との兼ね合いは?
ーー現在、ヨーロッパで流行が加速しています。日本の第6波もヨーロッパ並みの流行になる可能性はありますか?
コロナに関しては十分あり得るでしょう。

イギリスやヨーロッパのいくつかの国では一定のワクチン接種率を達成したところで、戦略的に社会経済活動をオープンにしました。その後の状況をみれば、社会活動が活発になると、高い接種率を達成しても再流行が起きること、トータルの患者数が増えれば重症者も増え、病院も埋まってくることは明らかです。
日本は高い接種率を達成して緊急事態宣言は解除されましたが、基本的な対策の推奨を続けています。いまのところ多くの市民はそれを遵守しています。
ただこのまま低い感染者数が続けば、だんだんと活動度があがってくるでしょう。そうすると、コロナもワクチンの効果の減弱と共に増えていきます。そこでどこまで社会活動を抑制できるのかに、かかってくると思います。
ーー経済を立て直そうということで、Go Toトラベルの再開も打ち出されています。人が動くことを促しながら、感染対策を呼びかけるという矛盾したメッセージが送られることになりますが、感染予防効果はどうなると思いますか?
感染対策を維持しながら、社会経済活動も維持するという方針については多くの人が納得していると思います。有効性の高いワクチンの接種がすすんだ後では「ゼロコロナ」はよい戦略とは言えず、世界中でほぼ現実的にあり得ない選択肢になりました。今後は可能な限り、重症者や死亡者の数を抑えながら、社会経済活動も行う。それは私も賛成です。
分科会でも、新規感染者数ではなく、重症者をモニタリングしながら強い対策をうつタイミングを図る方針に変わりました。
では実際に感染対策と社会経済活動の両立をどのようにやっていくかは、試行錯誤していかざるを得ないと思います。
今はワクチンが行き渡っているので、第5波の時のように患者数が増えたからといって、一気に病棟が埋まるという状況にはならないはずです。なかなか簡単ではなさそうですが、病床拡大の努力もされています。中和抗体薬を使った治療も重症化を防ぐはずで、実際の効果については今後わかってくるでしょう。
議論になっている「ワクチン・検査パッケージ」もありますが、積極的に経済を動かすために活用しようという人もいれば、差別の問題を懸念して慎重な人もいます。社会の中で議論していき、試行錯誤で進めていくのがよいでしょう。「絶対に導入すべきだ」とか「これはダメだ」と言うものではないと思っています。
ーーセンター長は「ワクチン・検査パッケージ」をどう考えますか?
ワクチンをうっても効果は100%ではなく、実際に全員がワクチンをうっている高齢者施設でも集団感染は起きています。
検査も、PCR検査であれ抗原検査であれ感度は100%ではありません。たとえワクチン・検査パッケージで徹底的にチェックしたとしても、集団感染は起こり得ます。
もちろん個々の店や施設のレベルで言えば、パッケージを使わないよりは使った方が集団感染のリスクは低くなるでしょう。しかし、人が集まるすべての場面で導入されるわけではありませんし、地域全体の流行抑制にはそれほど大きな効果は期待できないと考えています。
それでも、私が必ずしも反対ではないのは、それを巡って社会の中で議論されることで、感染対策と社会経済活動の両立が前に進むのではないかと思うからです。
法的強制力、持つべきか?
ーー議論があったロックダウンの法制化についてどう考えますか?衆院選で公約として提示していた党もありました。
地域をまたぐ移動を制限するロックダウン、あるいは都市封鎖と、個人が家の外に出ることを制限するステイホームとは分けて考える必要があると思います。
新型コロナの流行が始まって2年近くがたち、基本的な対策を徹底すれば一定のコントロールができることもわかってきました。また、ワクチンが行き渡ったことの効果は絶大で、それを維持するためのブースター接種も目の前に迫っている状況です。
今後、新規感染者数が増えて、病床の逼迫に近い状態になったときには、また宣言が発出されて、基本的な感染対策の再強化や一時的な外出自粛に協力が求められることはあるかもしれません。しかし、法令に基づく都市封鎖や徹底的なステイホームの戦略が必要になることはおそらくもうないだろうと思います。
新型コロナ対策として、これらを法制化しなければいけないとは、私は思っていません。
ーーみんなが身につけてきたやり方をもう一度呼びかけることで、また乗り切れるだろうという考えですね。
もちろんこれまでとは同じようにいかないかもしれませんし、守ってくれる人も少なくなるかもしれません。しかし今後の新型コロナ対策は「ウィズコロナ」で行く、つまりこれまでのやり方でできる範囲内で進めていくことになるのではないかと思います。
ただ、これから5年先、10年先に、新たな感染症の脅威が訪れたときに、いまの要請ベースの緊急事態宣言だけで、昨年の4月のような状態を再現できるでしょうか。私は、日本の新型コロナ対策は共同体の力があったからこそ、ここまでこれたのではないかと考えています。
しかし、共同体というのは、なんともつかみどころのないものです。国際的な人の動きが戻ってきて、また世代も変わったあとで、同じように共同体の力に頼ることができるかどうか。今後を見据えた議論は必要だと思います。
ワクチンは速やかにうって 基本的な対策を
ーー最後にこの冬の6波を前に「こう過ごしてほしい」と呼びかけておきたいことをお願いします。
幸せなことに今は流行がとても落ち着いています。できる限り、この状態を維持できるといいですね。個人的にも強くそう思います!
ーーそのためには。
今はワクチンの効果が最大限に発揮されていて、我々が慎重に日常生活を送り続けているから、落ち着いた状態を維持できています。
ただ考えておかなくてはならないことは、年末にかけて、高齢者を中心にワクチンの効果が弱くなってくるだろうことです。また新規感染者が少ないと自然と行動が活発化してきて、基本的な対策もおろそかになってくる。そこで第6波の流行が起き、インフルエンザの流行も重なる可能性があります。
それを考えると、社会経済活動を一気に戻すのではなく、ゆっくりと戻していきたい。ワクチンのブースター接種についても議論がありますが、タイミングがきたらうつことを前向きに考えていただきたいです。
ーー年末年始の帰省や忘年会・新年会はどうでしょうか?
基本的な感染対策を守りながら、そろりそろりと行きましょう。ワクチン・検査パッケージの活用を考えるよい機会かもしれません。
ーー今後、ワクチンは半年ごとにうつことになりそうですか?
それはまだわかりません。今後の検討課題です。ただ低中所得国の中には、供給不足や価格の問題から1回目の接種すらままならない国が多くあります。高所得国は自国のブースター接種をすすめるだけでなく、広く世界中にワクチンが行き渡るように考えなければいけません。
日本はスタートこそ出遅れましたが、今や世界トップクラスの接種率を達成しました。これから社会経済活動を戻していくということは、国をまたぐ交流が増えることでもあります。低中所得国のためだけでなく、我々のためにも、グローバルなワクチン共有体制の整備に貢献していきたいものです。
【鈴木基(すずき・もとい)】国立感染症研究所感染症疫学センター長
1996年、東北大学医学部卒業。国境なき医師団、長崎大学ベトナム拠点プロジェクト、長崎大学熱帯医学研究所准教授などを経て、2019年4月から現職。専門は感染症疫学、国際保健学。


