新型コロナウイルスの流行下で開催された芸術祭「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」(主催・東北芸術工科大学)で、生きることや芸術について語った詩人の岩崎航さん。

5回連載の2回目は、2011年に仙台で東日本大震災も経験した岩崎さんが、災害で固まった人の心をほぐすものについて語ります。
※トークは読みやすく編集を加えた上で、岩崎航さんにも確認してもらっています。
【コロナ禍・災害】
人に近づいてもらわなければ生きられないのに、接触がリスクに
――病が生活に影響を与えることを考えると、新型コロナは全ての人に大きな影響を与えていると思います。岩崎さんはコロナの影響はどうですか。
どの人にもコロナは影響を与えているわけですが、私のような24時間、人の介助が必要な人間では、多くの人の手助けを借りて生きているわけです。
ヘルパーさんに何人も訪問していただいているわけですが、このコロナは感染症なので、人と人との距離を取ること、これまでと違った人との距離をとる必要性が言われています。
感染防止のためですが、私は人に近づいてもらって身体の介助をしてもらわなければならない人間ですから、人が物理的に離れてしまうとその時点で生きることができなくなってしまいます。
だけど介助は受けなければいけません。介助というものが感染症の視点ではリスクとして考えなければならないのはとても苦しいことです。
今でも私のところには多くの支援者に来ていただいていて、そのおかげで今も無事に暮らしているわけです。そういう人たちや私の家族が感染対策の注意をしながらなんとかこうやって暮らしています。
でも新たにコロナで、こういう注意を払わなければいけないことが加わり、今までできていたことの制限をせざるを得なくなっています。
これまでなら介助者の手を借りて外出も少しできていました。元から、月2回しか外出はできていなかったわけですが、その数少ない機会もここのところずっと中止しています。
状況が状況なのでやむを得ないと承知はしているのですが、ずっと続いているのです。どなたも似たような状況で、私だけ特段大変というわけではないでしょうけれども、以前よりさらに不自由の度が増しています。
外の日の光に当たること、風に吹かれることができない状況です。辛い状況ではあります。
そのような辛さも加わりながら、今後いつ収束して、以前のような形が作れるのか、戻れるのかということもまだ見通しが見えてきません。
今後の暮らしについても、介助体制など、コロナがなかった時代から変更を余儀なくされています。新たに考えながら暮らしていく。私のような介助を受けなければ生きられない人にとっては、ますます厳しい状況が生まれています。
人とのつながりや趣味や娯楽 不要不急か?
――感染症を広げないために、一般の人も、人とのつながりや趣味・娯楽が不要不急のものとして生活から排除されています。それが当たり前のように社会の中で言われていることについてはどう思われますか?
不要不急という言葉が出てきていますが、なんでもない人との会話や雑談のようなもの、明確な用件があるわけではない会話は人が生きる中では結構大事なことではないかと思うんですね。そこで人は安らいだりもする。
趣味や娯楽も不要不急のものとして保留するようになっていますが、人と人とが会って話す、同じ場所を共有したいと思うのが人間の自然じゃないかと思います。
東日本大震災で固まった心をほぐしたのは?
――岩崎さんは2011年3月に東日本大震災も経験されましたね。避難もされて。
私は東日本大震災も経験して、あまりにも甚大な被害があってショックで詩を書くことができなくなってしまうことがあったんです。

私は家から病院に避難して、呼吸器を使う電気も確保してなんとか無事でした。家族も無事でした。
だけど、想像を絶するような災害で、本当に苦しんでいる人を前にして、無事にいた自分は何かものをいうことはできないなと思いました。創作や詩を書くことができなくなってしまいました。心が動かなくなり、固まってしまった。
――その固まった心がほぐれたのは何がきっかけだったのですか?
創作を再開したきっかけがありました。
2011年4月に2回目の大きい余震がありまして、また避難をしたのです。
その時に東京から友人が見舞いに来てくれました。その人も書く仕事をしていて、取材ということで仙台に来られていて、前から私と会う約束もしていた。
大きな余震が起きたのですが、予定通り避難先に来てくれたんです。
そこで友人は、「今書かなくていつ書くんですか?」ということを言ってくれた。会って帰られて、メールでいただいた言葉ですが、「今書かずしていつ書くのか」と。
なかなかこういう境遇に追い込まれて、こちらが大変だということも十分承知して、それでもあえてそういう言葉をかけてくれるのはなかなかないことだと思うんですね。
だけど、私をものを書く人としてみてくれて、それで詩人としてできることがあるのではないですかという問いかけをしてくれた。
その時に固まっていた心に血が通い出した。辛い状況をわかっていた上で、あえてそういう言葉をかけてくれた人がいるのは、とても幸せなことだと思うのです。私にとっては。
それをきっかけに、自分がその時に感じていることを自分に引きつけて考えて、そのままを書けばいい。誰かの代弁をすることはできない。自分でここで震災に遭って感じていること、思っていることをそのまま書けばいいと思えるようになりました。
そして創作をまた始めることになったのです。震災の1ヶ月後ぐらいでしたけれど、それで再開したということです。
新型コロナ禍 心の奥に残る底力
――きっと今も日本の心でコロナ禍で心が固まっている人は多いと思います。その人たちが心をほぐすきっかけは何からつかめばいいでしょう。
色々きっかけはあると思うのです。千差万別で、人それぞれだと思います。
あまりに苦しい状況、大きな動かしようがない災難に遭ってしまうと、人は心が固まってしまう。
心を動かすきっかけは色々あると思いますが、やはり一人では得ることは難しいのではないかと思います。人と関わって、重なっていくことの中から生まれることもあるのではないかと思うのです。
コロナに限らず、日本では台風の被害など災害が多く起きるようになっていますし、世界中でそのようなことがあります。
私の場合は詩を書くことでした。
そこでまず、自分の身の安全を確保できて、水や食料、暖かい場所、気持ちが落ち着くまでの時間を得られることは大前提です。
ただ、それだけでは固まってしまった心を動かしていくのは難しいのではないかと思うのです。何かそこに一つ、人との関わりの中で生まれるようなきっかけのようなものが必要なのではないかと思うのですね。
大きな災害やコロナも積み上げてきたものが一気に失われてしまう。自然に起こることなので如何ともし難い。
そのような個人の力ではどうしようもできない厳しい状況に遭った時にも、人間の中に残っている底力のようなもの、ギリギリのところで踏みとどまるためのもの、そういうものがあると思うのです。
芸術も、その一つの表れであって、その中で湧き出す底力のようなものがある。それが生きるよすがになっていくこともあると思うのです。
それは、芸術に限りません。私も友人の言葉によって心が動きましたし、ちょっとした人の言葉が心が動くきっかけになることがあると思います。
そういうギリギリのところに追い詰められた時に、人間として本当の、心の底からの言葉が出てくることがある。
そういう芯からの言葉に触れると人は共振して、共鳴する。自分の心も揺り動かすように出てきた言葉が他の人、それを受け取った人の心も揺り動かすことがあると思います。
色んなところで防御するように固まっていたものが、自分の中から動き出す。そのトリガー(引き金)になっていく。人それぞれトリガーは違うと思います。心の底から生まれるものが何かを動かしていくのではないかなと思います。
いのちの奥底の燠火は吹き消せない

誰もがある
いのちの奥底の
燠火(おきび)は吹き消せない
消えたと思うのは
こころの 錯覚
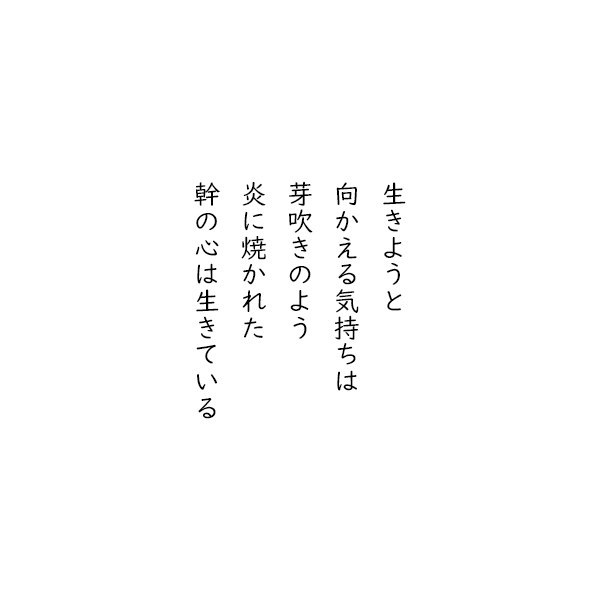
生きようと
向かえる気持ちは
芽吹きのよう
炎に焼かれた
幹の心は生きている
動画作品「漆黒とは、光を映す色〜詩人・岩崎航が、生きることと芸術を語る」(9月25日配信)のアーカイブは以下で見ることができる。
【岩崎 航(いわさき・わたる)】詩人
筋ジストロフィーのため経管栄養と呼吸器を使い、24時間の介助を得ながら自宅で暮らす。25歳から詩作。2004年から五行歌を書く。ナナロク社から詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、兄で画家の岩崎健一と画詩集『いのちの花、希望のうた』刊行。エッセイ『岩崎航の航海日誌』(2016年〜17年 yomiDr.)のWEB連載後、病と生きる障害当事者として社会への発信も行っている。2020年に詩集『震えたのは』(ナナロク社)刊行予定。



