「熊本地震の被災地で、障害者は見えない存在になってしまった」
自らも被災した専門家や当事者たちは、そう語る。日常生活でさえ一般の人たちより困難な障害のある人たちは、災害時にどんな避難生活を送っていたのか。その実態を知ると、さまざまな課題が浮かび上がってくる。
「聞こえない」避難生活の苦労

ある一家の話がある。
画家の乘富秀人さん(46)。妻と13歳の息子がおり、家族全員がろう者である「デフファミリー」だ。
熊本市内に暮らす乘富さんは、4月16日の「本震」後、近くの高校のグラウンドに避難し、3日間ほど過ごした。筆談でBuzzFeed Newsの取材に応じた乘富さんは言う。
「避難所ではろう者へ情報を伝える仕組みが整っていなかったため、まったく何もわからなかった」
避難所での案内は、すべて放送だった。耳の聞こえない乘富さん一家にとって、それは情報が何も伝わらないことを意味する。
周りの人が動き始めたとき、何かの放送があったのだろうと、内容もわからないままついて行ってみることしかできなかったという。
「朝食、夜食を配布するときもそれがわからなくて、みんなが並び始めたのに気がついて遅れてしまったがために、パン一個と水も、もらえないことがありました」
「自衛隊がいつ来て、食料や支援物資を持ってきてくれるという情報も放送でした。自分たちは受け取ることができず、開いているコンビニやスーパーを探し回るしかありませんでした」
人波について行ってみれば、すでに知っている「トイレの場所」だったという無駄足も、何度もあった。看板や貼り紙、字幕など「見える言葉」がなかったのが、とにかく不便だったという。
乘富さん一家は偶然、手話ができる知人と出会えたため、通訳してもらうことができた。しかし、全員がそういうわけではない。

知人のろう者の中には、そういった人と出会えず、避難所で「オロオロするばかりだった」という人や、やむなく家に帰った人たちも多かったという。
また、乘富さんは筆談でコミュニケーションを取ることに慣れているが、筆談ができない高齢のろう者たちは、身振り手振りでコミュニケーションするしかなかった。
「苦労されたと聞きました。知り合いの80代の夫婦の場合、何もわからずただただ、避難所で座っているだけだったそうです」
この夫婦は、避難所では情報をまったく得ることができず、食べ物も手に入れられなかった。結局、家具が倒れ、物が散乱した家に戻り、なんとか食べ物を探して過ごしていたところを、後日、ろう者福祉協会の役員が助け出したという。
「避難所でろう者が見落とされていた、という感覚を少なからず覚えました。でも、私たちはなんとか自分でやれることはできる。身体が不自由な人はもっと怖く、悔しい思いもされたのではないでしょうか」
避難を拒否されたケースもあった
「災害が起きたとき、障害者にまったく配慮ができていなかった。『特別扱いはできない』として、避難所は一般の人しか使えず、事実上、障害者が排除されることになったのです」
BuzzFeed Newsの取材にそう語るのは、自身も車椅子生活をしている熊本学園大教授で弁護士の東俊裕さん(63)だ。内閣府障害者制度改革担当室長を務めた経験をもつ。
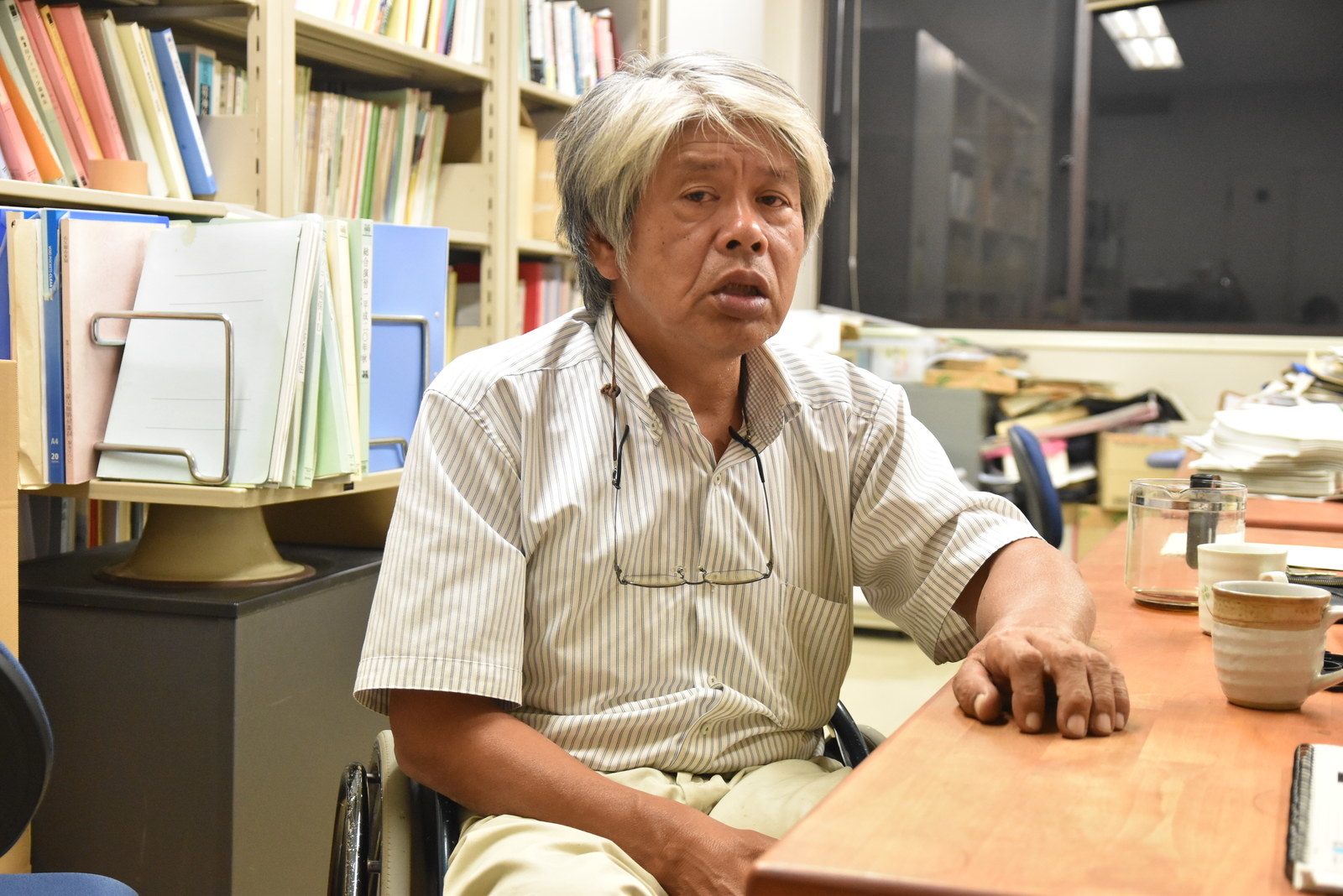
震災直後から障害者支援に乗り出した東さん。4月下旬に「被災地障害者センターくまもと」を立ち上げ、事務局長をしている。センターではこれまで、震災直後の生活援助やがれき撤去、家探しなど、400人を超える人たちを支援してきた。
そうして東さんが支援した人たちの話からは、その現実が見えてくる。
そもそも、障害者にとって「バリアフリー」である避難所は、ほとんどなかったという。
車椅子で使える仮設トイレがない、人がいっぱいで通ることもできない。目が見えない人が移動するための導線がない、耳が聞こえない人たちがいるのに、声による炊き出しの案内しかしない……。
自閉症の子どもが「パニックを起こすから」と、避難を拒否されたケースもあった。避難所での生活が困難ゆえに、避難をあきらめ、損壊した家に戻る人、車中泊を続ける人なども多かったそうだ。
熊本市には、障害者や高齢者などの「災害弱者」が避難するための「福祉避難所」が176カ所ある。約1700人分だ。
東さんによると、熊本市内にいる障害者は約4万2千人。そのうち福祉サービスを受けていない重度の障害者だけでも9千人いたというから、足りていない。
問題は数だけではない

勤め先である熊本学園大学で、避難する障害者が使えるスペースを設けた東さんは言う。
「福祉避難所はある意味、一次避難所にはなり得ないんです。災害が起きれば、障害者は一般の人たちと同じように、身近なところに避難するしかない。福祉避難所の場所すらわからないし、遠くに行くことができるわけでもない」
「避難所で発熱した人が病院に行くように、ある程度災害が落ち着いてからの二次避難所として機能することはあるかもしれません。しかし、『福祉避難所があるなら』と、普通の避難所で障害者を受け入れない理由を与えてしまうことにもなる」
実際、熊本市では、発災から10日間の福祉避難所の利用者は104人にとどまっている。開設できていたのも34カ所だけで、まったく機能していなかった。
これは、多くの障害者たちが、一般の避難所で困難な避難生活を送ったか、避難できていなかった可能性がある、ということを意味している。
東日本大震災直後、東北各地の避難所などを視察してきた東さんはこう感じている。「そこで見た現実が、熊本でもまた、繰り返された」と。
支援の枠組みからこぼれ落ちるということ
そもそも日本が批准している「障害者権利条約」の11条では、こう定められている。
締約国は、国際法(国際人道法及び国際人権法を含む。)に基づく自国の義務に従い、危険な状況(武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の発生を含む。)において障害者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる
さらに4月に施行された「障害者差別解消法」でも、自治体に対し、「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」をするよう義務付けている。
「本来であれば、福祉避難所だけではなくすべての避難所で、障害のある人たちが他の人と同じように避難できるようになるべきなのです。それなのに、行政は各避難所に指導もしていなかった」
震災後の支援に至っても、それは同様だ。
「避難所に被災者が来ることで、社会から見える存在になり、そこに支援者と、救援物資と情報が集まります。それが復興支援につながっていく。しかし、そもそも障害者が避難所に行けないとすれば、公的支援の網の目からこぼれ落ちることになってしまう」
被災した障害者の支援を始めた東さんも、これが原因で「支援を求めている障害者をどう探すか」という問題に直面したという。
「SOSビラ」を作成し、市役所や社会福祉協議会などに配ると、5月だけで100件の問い合わせがあった。その後の7月には、市内のすべての障害者にビラを郵送するよう市に依頼。今度は、多いときで1日70件の問い合わせがくるようになったという。
バリアフリー仮設住宅は、たった6戸
震災から半年、応急的な支援はひとまず落ち着いた。そこで立ちふさがるのは、仮設住宅の問題だ。

熊本県が用意した仮設住宅は、避難所と同じようにバリアフリーではなかった。トイレや風呂の入り口が狭かったり、段差があったりする。そもそも車椅子が部屋に入れないことさえあるという。
「トイレにも行けず、風呂も入れず、どうやって暮らせというのでしょうか」
東さんたちは県に要請したが、いまのところ着工されたバリアフリー住宅は6戸のみ。そこに入れない人たちは、「みなし仮設住宅」として一般のアパートなどを探すか、どうにか我慢して暮らすしかない。
「この問題は復興住宅まで尾を引いていくはず。言わないと何も変わらないので、継続的に県と交渉していきます」
求められるガイドライン
普段から弱者である障害者は、災害時、よりいっそう困難な暮らしを強いられる。これまでの地震で得られた教訓を今後にどういかしていくべきなのか。
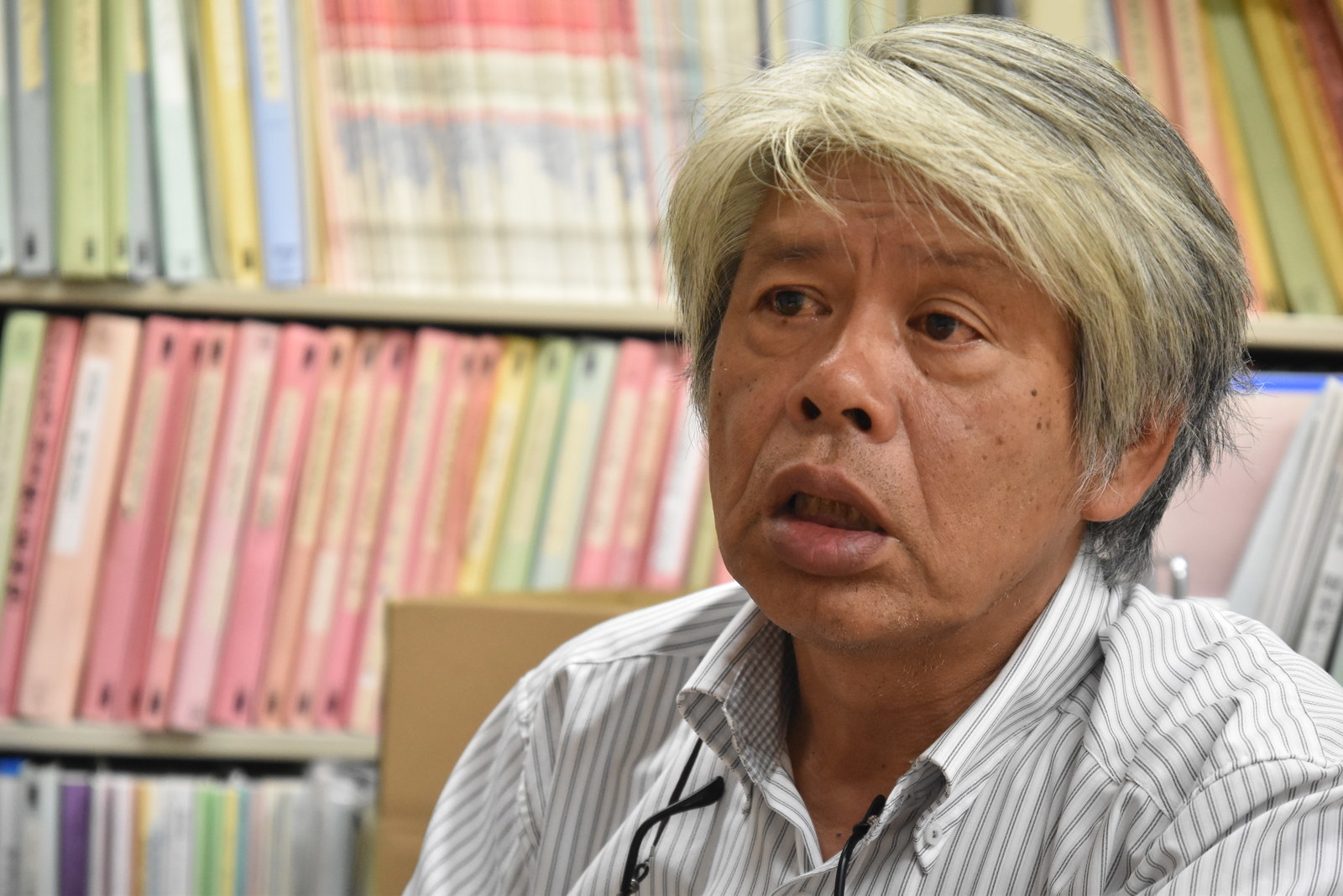
「この地震の教訓を広げるためにも、熊本市や県はまず、ガイドラインを作るべきだと思います。公的支援が一般の人と障害者も同じようになされることが目的です。さらにもう一つ、私たちがセンターでやっていたものと同じような災害後の支援の枠組みづくりも必要でしょう」
「障害者は、一般の人であればなんでもないことが大変になることが、たくさんあります。しかし誰でも困っている災害時に心に余裕がなくなると、『配慮』なんて頭からなくなってしまう。だからこそ、普段から仕組みを整えていくことが大切なんです」
災害大国、日本。誰しもが「もしもの時」の支援からこぼれ落ちないための備えが、いま求められている。
