
政府は4月1日午前11時40分過ぎ、新元号「令和」を発表した。天皇の退位に伴う改元は憲政史上初めてとなる。新元号は5月1日より施行される。
出典は『万葉集』
「令和」の出典は、現存する日本最古の歌集『万葉集』の「梅花(うめのはな)の歌」三十二首の序文が出典とされた。
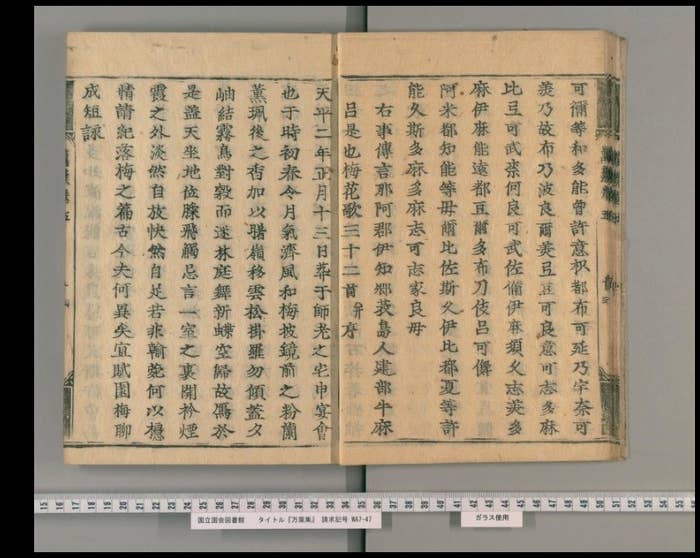
天平二年正月十三日 師の老の宅に萃まりて宴会を申く。時に初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。
『万葉集』は20巻からなる歌集で、770年ごろに成立。編者は大伴家持らとされている。
「令和」の由来となった文は、大伴家持の父・大伴旅人が、天平2(730)年の正月に開いた宴会の情景を記したもの。この宴会で、参会者たちは梅の花にまつわる32首の和歌を詠んだ。
これまでの元号は247
日本の元号は645年に「大化」が定められたのが最初。7世紀頃には元号の空白期間があったり、南北朝時代には異なる元号が並立したが、今日に至るまで1374年の間に247の元号が使われてきた。
かつては新天皇の即位時のほか、天変地異の発生、飢饉、疫病が蔓延した際にも改元がなされた。そのため、一人の天皇在位時に複数の元号が使用されることもあった。
明治以降は、天皇一代に限り元号を一つとする「一世一元の制」をとった。
これまでの出典は、全て中国の書物(漢籍)だった
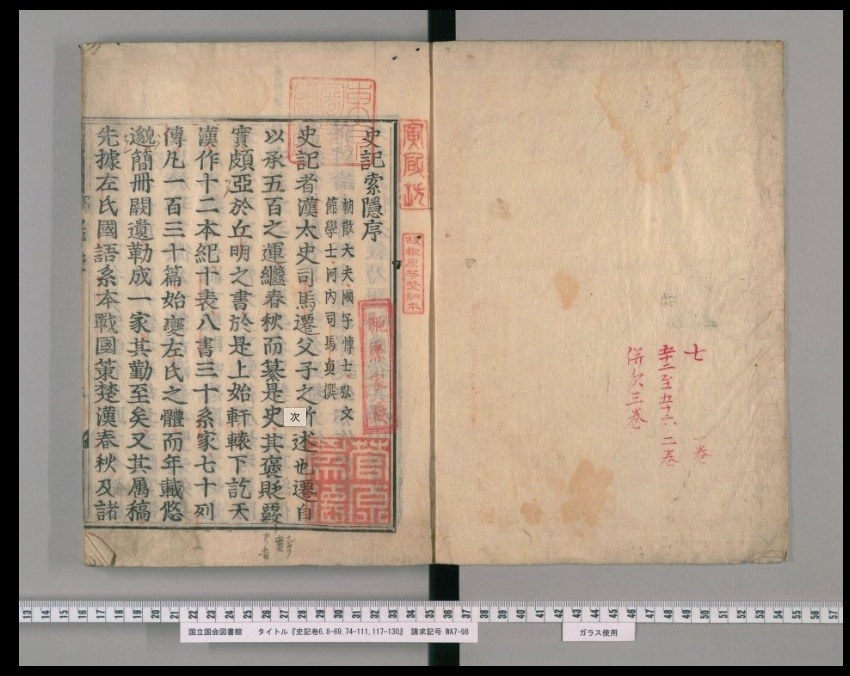
歴史上、元号のはじまりは中国・前漢の武帝が「建元」という元号を定めたのが最初とされている。以来、中国の影響を受けた国々で独自の元号が使用された。
日本の元号も、出典が明らかなものに限り全て漢籍(中国の書物)を典拠としている。儒学の経典「四書五経」や歴史書など、中国の古典から引用されている。
『元号全247総覧』(山本博文編著、悟空出版)によると、これまでに引用回数が多い典籍と使用回数が多い漢字のベスト10は以下の通り。
【引用回数の多い典籍ベスト10】
- 『書経』(尚書)35回
- 『易経』(周易)27回
- 『文選』25回
- 『後漢書』24回
- 『漢書』21回
- 『晋書』16回
- 『旧唐書』16回
- 『詩経』15回
- 『史記』12回
- 『藝文類聚』9回
【使用回数の多い漢字ベスト10】
- 永 29回
- 元・天 27回
- 治 21回
- 応 20回
- 正・長・文・和 19回
- 安 17回
- 延・暦 16回
- 寛・徳・保 15回
- 承 14回
- 仁 13回
ちなみに「平成」は、「四書五経」の一つ『書経』より「地平らかに天成る」、司馬遷の歴史書『史記』より「外平らかに内成る」に由来する。
今回の改元では、政府は国書(日本の書物)の専門家にも考案を依頼していた。
朝日新聞は、菅義偉・官房長官が元号の原案として数案を選ぶ前の段階の20案程度の中にも、国書に由来する案が含まれていると報じていた。また、「安倍政権の支持基盤である保守派には、日本で記された国書に由来する元号を期待する声がある」とも伝えていた。
新元号、条件は「書きやすく読みやすい」「漢字2字」
政府発表によると、安倍晋三首相は3月14日、次の元号にふさわしい候補名の考案を専門家に委嘱した。
考案された候補名は、菅官房長官が検討・整理した上で安倍首相に報告。選定基準については、以下のとおり。
- 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること
- 漢字2字であること
- 書きやすいこと
- 読みやすいこと
- これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと
- 俗用されているものでないこと
元号一覧
大化 645年~650年
白雉 650年~654年
(空白期間1)654年~686年
朱鳥 686年
(空白期間2)686年~701年
大宝 701年~704年
慶雲 704年~708年
和銅 708年~715年
霊亀 715年~717年
養老 717年~724年
神亀 724年~729年
天平 729年~749年
天平感宝 749年
天平勝宝 749年~757年
天平宝字 757年~765年
天平神護 765年~767年
神護景雲 767年~770年
宝亀 770年~781年
天応 781年~782年
延暦 782年~806年
大同 806年~810年
弘仁 810年~824年
天長 824年~834年
承和 834年~848年
嘉祥 848年~851年
仁寿 851年~854年
斉衡 854年~857年
天安 857年~859年
貞観 859年~877年
元慶 877年~885年
仁和 885年~889年
寛平 889年~898年
昌泰 898年~901年
延喜 901年~923年
延長 923年~931年
承平 931年~938年
天慶 938年~947年
天暦 947年~957年
天徳 957年~961年
応和 961年~964年
康保 964年~968年
安和 968年~970年
天禄 970年~974年
天延 974年~976年
貞元 976年~978年
天元 978年~983年
永観 983年~985年
寛和 985年~987年
永延 987年~989年
永祚 989年~990年
正暦 990年~995年
長徳 995年~999年
長保 999年~1004年
寛弘 1004年~1013年
長和 1013年~1017年
寛仁 1017年~1021年
治安 1021年~1024年
万寿 1024年~1028年
長元 1028年~1037年
長暦 1037年~1040年
長久 1040年~1044年
寛徳 1044年~1046年
永承 1046年~1053年
天喜 1053年~1058年
康平 1058年~1065年
治暦 1065年~1069年
延久 1069年~1074年
承保 1074年~1077年
承暦 1077年~1081年
永保 1081年~1084年
応徳 1084年~1087年
寛治 1087年~1095年
嘉保 1095年~1097年
永長 1097年
承徳 1097年~1099年
康和 1099年~1104年
長治 1104年~1106年
嘉承 1106年~1108年
天仁 1108年~1110年
天永 1110年~1113年
永久 1113年~1118年
元永 1118年~1120年
保安 1120年~1124年
天治 1124年~1126年
大治 1126年~1131年
天承 1131年~1132年
長承 1132年~1135年
保延 1135年~1141年
永治 1141年~1142年
康治 1142年~1144年
天養 1144年~1145年
久安 1145年~1151年
仁平 1151年~1154年
久寿 1154年~1156年
保元 1156年~1159年
平治 1159年~1160年
永暦 1160年~1161年
応保 1161年~1163年
長寛 1163年~1165年
永万 1165年~1166年
仁安 1166年~1169年
嘉応 1169年~1171年
承安 1171年~1175年
安元 1175年~1177年
治承 1177年~1181年
養和 1181年~1182年
寿永 1182年~1184年
元暦 1184年~1185年
文治 1185年~1190年
建久 1190年~1199年
正治 1199年~1201年
建仁 1201年~1204年
元久 1204年~1206年
建永 1206年~1207年
承元 1207年~1211年
建暦 1211年~1213年
建保 1213年~1219年
承久 1219年~1222年
貞応 1222年~1224年
元仁 1224年~1225年
嘉禄 1225年~1227年
安貞 1227年~1229年
寛喜 1229年~1232年
貞永 1232年~1233年
天福 1233年~1234年
文暦 1234年~1235年
嘉禎 1235年~1238年
暦仁 1238年~1239年
延応 1239年~1240年
仁治 1240年~1243年
寛元 1243年~1247年
宝治 1247年~1249年
建長 1249年~1256年
康元 1256年~1257年
正嘉 1257年~1259年
正元 1259年~1260年
文応 1260年~1261年
弘長 1261年~1264年
文永 1264年~1275年
建治 1275年~1278年
弘安 1278年~1288年
正応 1288年~1293年
永仁 1293年~1299年
正安 1299年~1302年
乾元 1302年~1303年
嘉元 1303年~1306年
徳治 1306年~1308年
延慶 1308年~1311年
応長 1311年~1312年
正和 1312年~1317年
文保 1317年~1319年
元応 1319年~1321年
元亨 1321年~1324年
正中 1324年~1326年
嘉暦 1326年~1329年
【南朝】
元徳 1329年~1331年
元弘 1331年~1334年
建武 1334年~1336年
延元 1336年~1340年
興国 1340年~1347年
建徳 1370年~1372年
文中 1372年~1375年
天授 1375年~1381年
弘和 1381年~1384年
元中 1384年~1392年
【北朝】
元徳 1329年~1332年
正慶 1332年~1334年
建武 1334年~1338年
暦応 1338年~1342年
康永 1342年~1345年
貞和 1345年~1350年
観応 1350年~1352年
文和 1352年~1356年
延文 1356年~1361年
康安 1361年~1362年
貞治 1362年~1368年
応安 1368年~1375年
永和 1375年~1379年
康暦 1379年~1381年
永徳 1381年~1384年
至徳 1384年~1387年
嘉慶 1387年~1389年
康応 1389年~1390年
明徳 1390年~1394年
【南北朝合一】
応永 1394年~1428年
正長 1428年~1429年
永享 1429年~1441年
嘉吉 1441年~1444年
文安 1444年~1449年
宝徳 1449年~1452年
享徳 1452年~1455年
康正 1455年~1457年
長禄 1457年~1460年
寛正 1460年~1466年
文正 1466年~1467年
応仁 1467年~1469年
文明 1469年~1487年
長享 1487年~1489年
延徳 1489年~1492年
明応 1492年~1501年
文亀 1501年~1504年
永正 1504年~1521年
大永 1521年~1528年
享禄 1528年~1532年
天文 1532年~1555年
弘治 1555年~1558年
永禄 1558年~1570年
元亀 1570年~1573年
天正 1573年~1592年
文禄 1592年~1596年
慶長 1596年~1615年
元和 1615年~1624年
寛永 1624年~1644年
正保 1644年~1648年
慶安 1648年~1652年
承応 1652年~1655年
明暦 1655年~1658年
万治 1658年~1661年
寛文 1661年~1673年
延宝 1673年~1681年
天和 1681年~1684年
貞享 1684年~1688年
元禄 1688年~1704年
宝永 1704年~1711年
正徳 1711年~1716年
享保 1716年~1736年
元文 1736年~1741年
寛保 1741年~1744年
延享 1744年~1748年
寛延 1748年~1751年
宝暦 1751年~1764年
明和 1764年~1772年
安永 1772年~1781年
天明 1781年~1789年
寛政 1789年~1801年
享和 1801年~1804年
文化 1804年~1818年
文政 1818年~1830年
天保 1830年~1844年
弘化 1844年~1848年
嘉永 1848年~1854年
安政 1854年~1860年
万延 1860年~1861年
文久 1861年~1864年
元治 1864年~1865年
慶応 1865年~1868年
明治 1868年~1912年
大正 1912年~1926年
昭和 1926年~1989年
平成 1989年~2019年(4月30日まで予定)
令和 2019年〜(予定)
