昨年、緊急避妊薬の市販薬化が厚生労働省で議論され、否決されました。
市販薬化の見送りについて、メディアの記事やSNS上では今も大きな批判が続いています。
薬局薬剤師の視点から、この問題について考えてみようと思います。
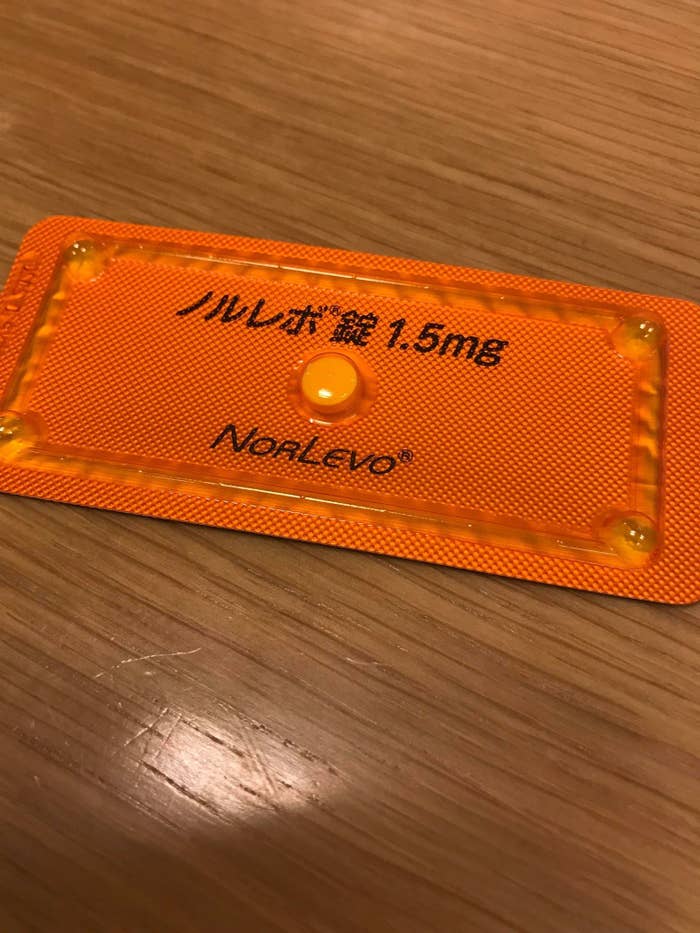
緊急避妊薬とはどんな薬なのか
コンドームの破損や脱落、あるいは強姦被害といった無防備な性交の後でも、緊急避妊薬(商品名:ノルレボ)を服用することで妊娠の可能性を大きく下げることができます。ノルレボは、性交から72時間(できれば12時間)以内に服用します。
現在、緊急避妊薬は市販されておらず、医師から処方してもらう必要があります。価格は病院によって異なり、15000円~20000円の場合が多いようです。
価格に抵抗がある場合、従来の避妊薬(ヤッペ法)など他の選択肢もあります。
今年の2月には、ノルレボの後発医薬品(ジェネリック)の承認申請が行われています。購入者の経済的な負担が軽くなることが期待されます。
ノルレボの副作用の可能性は高くなく、過度に心配する必要はありません。ただし、妊娠初期・中期に服用することで女性胎児外性器の男性化、男性胎児の女性化が起こる可能性があり、安易な服用は勧められません。
臨床試験で確認されたノルレボの妊娠阻止率は81%です。使用は緊急時に限られ、通常の避妊方法として服用してはいけません。短期間に何度も服用すると、避妊効果は低下します。
効果的な普段の避妊方法に関しては、産婦人科医などの医療従事者に相談してください。現在の避妊方法が適切であるかどうかについても、相談することができます。
もし緊急避妊薬を必要とする理由が、強制的あるいは自らの意思に反する性交によるものであった場合、相談・支援のための機関を利用してください。プライバシーに十分に配慮した上で、適切な支援を受けることができます。
行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(一覧)
どこで手に入るのか?
緊急避妊薬は通常、産婦人科医から処方されますが、内科など他科の医師が処方することも可能です。休日診療所や休日当番医で処方している場合もあります。在庫がない場合でも、発注し入荷することは可能です。
もしあなたが緊急避妊薬を必要とするとき、当然のことですが、あなたには緊急避妊薬を求める権利があり、医師にはその求めに誠実に対応する責任があります。
どうしても、72時間以内に医療機関にアクセスすることが困難である場合、オンラインで診療し緊急避妊薬を郵送しているクリニックがあります。スマートフォンでやり取りした上で、宅配便で薬を届ける方法です。
しかし、厚労省は、「原則として初診は対面診療」などとして、緊急避妊薬に関するオンライン診療は認めない方針であるようです。
また、このクリニックが採用する緊急避妊薬は個人輸入された医薬品であるため、万が一健康被害が出たとしても、副作用被害救済制度の対象外であるなど、国内で流通する医薬品と異なる点があることに注意して下さい。
このほか、インターネット上には緊急避妊薬を販売するといったサイトが多く見られますが、この購入方法はお勧めしません。性に関する薬は、医療従事者に相談せず購入したいとのニーズがあり、偽造医薬品などのターゲットとなります。
バイアグラ(勃起改善薬)の個人輸入に関して実施された調査では、半数以上が偽造品でした。
緊急避妊薬に偽造医薬品や粗悪品が紛れ込んでいても何ら不思議ではありません。
厚労省会議でどんな議論がなされたのか
緊急避妊薬の市販薬化が議論された際の資料と議事録は公開されています。関心のある方は下記のリンクから、ぜひご覧ください。
第2回 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議、議事録
第3回医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議議事録
会議では、以下のような意見がありました。
妊娠阻止率は100%ではなく80%程度であり、正に排卵しているときに来られた方は、実は妊娠を阻止できないのです。産婦人科では同意書をとって処方しているような薬です。
市販薬になれば、一般の方が誤解するのではと危惧します。しかし、そのことを周知することは非常に難しいと思います。
欧米では20代の90%以上が経口避妊薬を使用している状況にあり、避妊薬に慣れているのです。ある程度避妊に失敗することもあるだろうということも体感しています。
(国立国際医療研究センター病院副院長)
薬剤師が厳格に管理すべきとの意見もありますが、市販薬のネット販売を認める日本の現状では不十分だと思います。緊急の避妊であり、常用を防ぐための仕組みがありません。
医療機関であれば薬の交付時に適切な性教育を行うこともできますが、市販薬になってしまいますと、その機会を奪うことになります。
(日本医師会)
医療用から要指導・一般用へという転用のスキームが、要指導3年、第1類1年しっかりと薬剤師がコントロールしても、第2類医薬品へと移行する(一般用医薬品への転用後、安全性が確認されれば順次、要指導→第1類→第2類へと移行する。要指導医薬品は薬剤師による対面販売を要し、ネット販売不可。第1類以下はネット販売可)。
何とか新たな仕組みを検討していただきたいと思っております。
それができないのであれば、現状としては難しいのではないかと思っております。
(日本薬剤師会)
薬剤師の意見はどうか
市販薬化の見送りに対し、多くの薬剤師は反発しました。専門メディアやSNS、ブログには「薬剤師の職責・能力の否定であり容認できない」といった意見が多数見られます。
皆さんもご存じのように、日本は薬剤師の存在意義を重視しない国です。
日本は先進国の中で「医薬分業(病院と薬局とを分離し独立性を担保する)」が徹底されない唯一の国であり、市販薬の99%以上は薬剤師の関与を必要とせずに販売されています。
こうした日本の医療文化を支えてきたロジックは、
「医療用医薬品は医師が安全を担保しており、薬剤師の存在は必須ではない」
「市販薬は病院を受診せずに買えるのだから安全であり、情報は説明書で十分」
といったものです。
この理解には多くの薬剤師が呆れ、批判していますが、厚労省での議論の前提として、また「有識者」と呼ばれる人たちの理解、世間の常識としても広く共有されています。日本薬剤師会も現状に強く抗議することはないようです。
こういった状況から、多くの薬剤師は「存在意義を認められ、役割を果たす」ことを強く望んでいます。もし「緊急避妊薬を販売するためには、10時間のweb講座の受講が必要」との決定があれば多くの薬剤師が受講するでしょう。
会議で指摘された「薬剤師の能力不足・教育」は問題にはならないと思われます。
医師の権威・パターナリズムへの反発と市販薬化
緊急避妊薬を市販薬化する目的として、「医師の権威・パターナリズムからの解放」といった面もあるかもしれません。

緊急避妊薬の市販薬化を求める声の中には、「医師から心ないことを言われた」「説教をされる」とする意見が少なくありません。
確かに、医師の言葉づかいや態度は様々です。コミュニケーション技術を改善すべきとの意見もありますが、解決しづらい問題でもあります。人格やキャラクターは様々であり、伝えたいメッセージも持っています。
性に関する話題はデリケートで、コミュニケーションに伴う抵抗感は生じやすいものです。購入者(患者)が医師に権威やパターナリズムを感じ、権利が尊重されていない、失礼だと考えた際、それに反論することは多くの人にとって簡単ではないかもしれません。
しかし、パターナリズムを嫌う一方で、(未成年者や学生、若年者ばかりでなく)皆が医師とのコミュニケーションや摩擦を避けてしまえば、それに代わる新たな関係性を模索することも叶わず、産婦人科を受診しづらい文化も変わりようがありません。
コミュニケーションは面倒ですが、望ましい医療あるいは医師は、ネットやメディアの中に存在するのではありません。生活圏の中で関係性を構築し、皆で文化を醸成する手間を避けて通ることはできません。
パターナリズムからの解放は重要な課題です。ただそれは、余計なコミュニケーションや摩擦なしに緊急避妊薬を入手することで実現するものではなく、市場が解決してくれる問題ではないと私は思います。
海外の緊急避妊薬と薬局
「緊急避妊薬を販売するためには、薬剤師が十分な知識を持つ必要がある」という会議の意見と、「病院にかかることなく自由に購入できる薬であり、安全なはずだ」といった現状の国民的な認識は、残念ながら全く正反対です。
はたして日本人は、これまでの認識を捨て、「使い方によっては安全ではなく、説明書に記載しきれない情報を薬剤師とやり取りすべき市販薬」が登場することを求めているのでしょうか?
また厚労省や医師会・薬剤師会はそうした国民的理解を促す制度設計や呼びかけについて、一貫した姿勢で臨めるのでしょうか。
私は懐疑的です。
この状況を放置したまま市販薬化を実現したところで、説明書に記載された内容の一部を購入者に伝えることしかできない事例が頻発するでしょう。それは、過去に市販薬化した医薬品について実際に今、問題視されていることです(オメプラゾール等のプロトンポンプ阻害薬に関する議論を参照してください)。
緊急避妊薬の問題に熱心に取り組まれている産婦人科医の北村邦夫氏が、イギリスの薬局で緊急避妊薬を購入しようとした際のエピソードについて語っています。

薬剤師からは「男性には売れない」と断られ、名刺を見せたうえで「日本に緊急避妊薬を導入するため調査研究をしている」と伝えてもダメだったとのことでした。同行していた女性と共に再度訪れたことで、やっと購入できたものの、その際には15分ほどの説明(カウンセリング)があったそうです。
このエピソードは「薬剤師は役割を担うことができる(市販薬化は可能)」との観点から語られたものですが、こうした薬剤師の姿勢は、日本の消費者が薬剤師としてイメージする姿、(そして特に)緊急避妊薬の市販薬化で期待する対応とは異なるのではと感じます。
日本の薬事政策は、(諸外国の事例を参照し、また多くの有識者が議論に参加してきたにも関わらず)「薬剤師は役割を担わない(担う必要がない)」との従来の認識を追認してきました。
強い口調で主張し、政治力も併せ持つ医師会への忖度から、誰もが逃れることはできませんでしたし、「国民のニーズ」「消費者のニーズ」といった言葉を持ち出すことで、自らが批判されることを避けてきた面もあるのだろうと思います。
多くの女性が経口避妊薬(ピル)の利用に抵抗がなく、また圧力を感じることなく医師を受診する、薬局薬剤師も患者(購入者)に忌憚なく助言・介入する海外の状況は、日本とはずいぶんかけ離れています。
【後編】緊急避妊薬(アフターピル)市販薬化の是非 市民的な議論は熟しているか?
【高橋 秀和(たかはし ひでかず)】薬剤師
1997年、神戸学院大学卒。病院、薬局、厚生労働省勤務を経て2006年より現職。医療・薬事・医薬品利用についてメディア等で記事の監修や執筆をしている。ツイッターはこちら(@chihayaflu)

