過疎化で廃校となった香川県のある中学校で、高級食材のキャビアが生産されています。ここでチョウザメの養殖にゼロから挑んだのは、卒業生の板坂直樹さん。
板坂さんが生んだ「瀬戸内キャビア」は、東京の高級ホテルなどで提供され、2020年にはフランスのレストランガイドが主催する賞も受賞しました。
「失敗しても失敗しても、成功するまで続ければ、それは失敗じゃない」
「CAVIC」の板坂直樹社長にとって、キャビアづくりとはーー?
歩いていたら頭にチョウザメが浮かんできた

ーーなぜ中学校でチョウザメの養殖を始めようと?
もともとは僕は内装業なんですが、地元の町おこしの一環でドッグランなどを計画しているうちに「おもしろいことをやるようだ」という話が広まっていたようです。
それで、母校の引田中学校が廃校になるというときに「活用法を考えてもらえないか」と東かがわ市から話をいただいたんです。
しかし学校という建物は使い勝手がよくない。市には記念館や倉庫にする案もあったようですが、生産性がないものをつくっても意味ないのでは、と悩んでいたときに、歩いていたら突然チョウザメが頭に浮かんだんです。

ーーいきなりチョウザメが...ですか? おぼろげに浮かんできた?
本当に、ひらめいちゃったんですよね...
あえてかっこよく言うと、引田町はハマチの養殖発祥の地とされており、幼い頃から養殖業は身近な存在でした。さらに僕は中学時代に水泳部だったので、50mプールの印象が強烈にありました。プール=養殖、養殖=チョウザメだと。
ーーあの、失礼ですが、それまでにキャビアを召し上がったことは?
結婚式で食べたことがある程度でしたね。
ーーキャビアがチョウザメの卵だと知っている人もそう多くはないですよね。
幼い頃にテレビで見た記憶があったのかもしれませんが、今となってはなぜチョウザメが頭に浮かんだのか、永遠の謎ですね。
ーー養殖の経験も、もちろん初めてでいらっしゃった?
養殖の技術については、この町には漁師の先輩がたくさんいるので、なんとかなるという確信はありました。
チョウザメは淡水魚ですが、海水魚の養殖と共通する点もあります。技術の面では心配していませんでした。問題は、良質な水をどう調達するかでした。
香川は、渇水で有名です。それでも僕の家の前の小さな川が涸(か)れたことがなかった。きっと、地下に豊富な水源があるに違いない。それで井戸を掘ったんです。
2013年、チョウザメ2000匹の飼育をスタート

ーーキャビアを採るまでに、まずはチョウザメを育てないといけないんですよね。
そうなんです。わずか10〜15cmの稚魚2000匹を育て始めましたが、7〜15kgになって採卵ができるようになるのは7年以上飼育した後で、しかも一度きりなんです。
さすがに7年間も売上ゼロというわけにはいかないので、ある程度まで育った魚や、すでに抱卵している魚も買い付けて、初年度から少量ずつキャビアの加工と販売は始めていました。
ーー当初は、中学校のプールで飼育されていたとか。
はい、中学時代に毎日のように泳いでいた、思い出の50mプールです。
ところが、屋外のプールだと鳥に狙われてしまうんですね。盗難に遭っても困りますし。なので、稚魚と採卵前のタイミングでは、体育館の中に設置した水槽で飼育するようにしました。
その間の中間魚は基本的に、鳴門にある屋外の養殖場に移しています。もともとウナギの養殖場だったところです。
採卵まで7年かかりますから、初代をようやく採卵できたのは一昨年ごろですね。
個体ごとの味の違い

ーー実はキャビアをほとんど食べたことがなくて、食べる機会があったとしてもせいぜい数粒だけなんですが、味の違いってわかるものなんでしょうか。
わかりますよ!まったく違います。
チョウザメの魚種、環境やエサによっても違いますし、同じ魚種を、同じ環境、同じエサで育てたとしても、個体によってキャビアの味や色は異なってきます。
個体の違いを楽しんでもらいたいので、香り、味、油分、水分など9つの項目でランク付けし、ランクごとに分けて商品化しています。
飼育と加工の過程で、こだわりが多ければ多いほど商品の魅力が高まると、僕は信じています。
飼育中はできるだけチョウザメにストレスを与えないように、新鮮な天然水やエサ、環境に気を配っています。
また、加工の方法を変えると、まるで違うキャビアになります。
※キャビアづくりのこだわりは、こちらの記事から

ーー採卵や加工は、家庭科室でされているんですね。
理にかなっているでしょう? 学校の施設をなるべくそのままの形で利用することにこだわり、同じ学校内の家庭科室を加工場にしたことで、輸送の工程も省けています。
1匹のチョウザメから採卵できるのは一度だけなので、ベストのタイミングで採卵することが重要なポイントになってきます。
加工は、時間との戦いです。卵を洗う、水気を切る、塩を混ぜる、こうした工程すべて、職人が経験則から割り出した時間を秒単位で計りながら進め、品質の統一をはかっています。
しょっぱくてプチプチ、ではない

ーー「理想のキャビア」とはどういうものなんでしょうか?
キャビアって、しょっぱいイメージがありませんか? 私も記憶の中のキャビアは、結婚式で食べたしょっぱいキャビアなんです。
また「プチプチしていておいしい」とおっしゃる方もいますが、本当においしいキャビアは、その逆なんですね。
ロシアの方に「私たちはとろけるようなキャビアを食べている。プチプチなんて大間違いだ」って叱られたことがあるんです。口の中に皮が残るのも低級品だと。
塩鮭と同じ原理で、保存するために塩分を高めにする必要があったわけですが、塩分濃度が高いと浸透圧で水分が抜けていきますので、皮が硬くなったり、ドリップ(液体)のほうに旨味が出てしまいます。
冷凍や配送の技術が発達した現代では、塩に頼らなくてもよくなりました。そこで、瞬間凍結の技術を駆使し、目指したのは、「しょっぱい」「プチプチ」とは逆の、とろけるようにまろやかなキャビアです。
軟らかいキャビアが正解だということがわかってからは、どのタイミングなら最も軟らかい状態で採卵できるのかも研究しました。
検卵を一度した後、およそ40通りの計算をして、そのチョウザメにとってベストな採卵日のたった1日を割り出すんです。プラスマイナス12時間の誤差しか許していません。「今だ!」となってからは、わずか2〜3分で採卵するので、加工場は緊迫感に包まれますね。

ーー日本のキャビア生産量1位は宮崎県。各地でしのぎを削っていますね。
チョウザメはワシントン条約の保護対象で、天然キャビアの国際取引が禁止される一方、日本でも養殖業が発展して、2015年からは養殖キャビアの輸出ができるようになりました。
地域に複数の企業があると組合を作れたり、補助金を受け取れたりして生産量のを増やせますが、僕はやはり品質で勝負したいと思っています。
日本のキャビアを世界に

そして、やはり世界に認められたいです。
一つの例が牛肉です。いまは日本人になじみのある牛肉も、食文化として定着したのは江戸時代より後だとされています。
牛肉が供給され、牛肉を食べる文化が根付き、黒毛和牛など大切に育てられたブランド和牛が海外に知られるようになりました。現地の牛肉の数倍の値段で和牛が売られていることもあります。
キャビアも、まだ食文化として日本に根付いてはいませんが、日本人の味覚によってキャビアを育て、世界中にメイドインジャパンのキャビアを広げたい。ヨーロッパのまねをしているだけでは絶対にかないません。日本人が育て上げなければならないと思っています。
僕たちの「瀬戸内キャビア」は2020年、フランス発祥のレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」の日本版でテロワールを受賞しました。でも、これで満足はしていなくて、まだまだこれからです。もっと改良を重ねて進化させていきます。
成功するまでやれば失敗じゃない

ーーこの取材は、銀座のキャビアバーからオンラインで受けてくださっていますね。
キャビアのアンテナショップとして、2016年に東京・銀座にキャビアバーをオープンしました。
ショーケースにキャビアを置くだけでなく、食べ方も一緒に提供できたらと、キャビアを使ったお料理や、キャビアに合うお酒を提供しています。
チョウザメは、2〜3年目に雌雄が判別できるので、雄のチョウザメは「キャビアフィッシュ」として、ここで魚肉を食べることができます。
ーーおいしいキャビアを目指してあちこち飛び回る中、内装業のほうも今も続けていらっしゃるんですか。
やってますよ。働く時間についてあまり深く考えず、塾やエステの経営など、日曜日に最も忙しくなる仕事もやっちゃってました。コロナで移動が制限されたことで、ようやく休む時間ができたくらいです。
採卵のタイミングを計算したり、数百種類の岩塩を比べたりするときには、感覚や勘だけでは納得できなくて、細かいデータを分析する建築業のノウハウが生きてきます。失敗してお蔵入りになったデータもたくさんあります。
僕が試行錯誤しながら事業を進めるのは、こんな信条からです。
失敗しても、失敗しても、失敗しても、成功するまで続ければ、それは失敗じゃない。
負けても負けても、勝つまでやれば勝ちなんです。成功するまでやれば、それは成功なんです。失敗したら、それを成功につなげてやるという気持ちが生まれます。
僕は成功するまでやり続けます。失敗した回数は、9億9999万9999回くらいのレベルですが(笑)
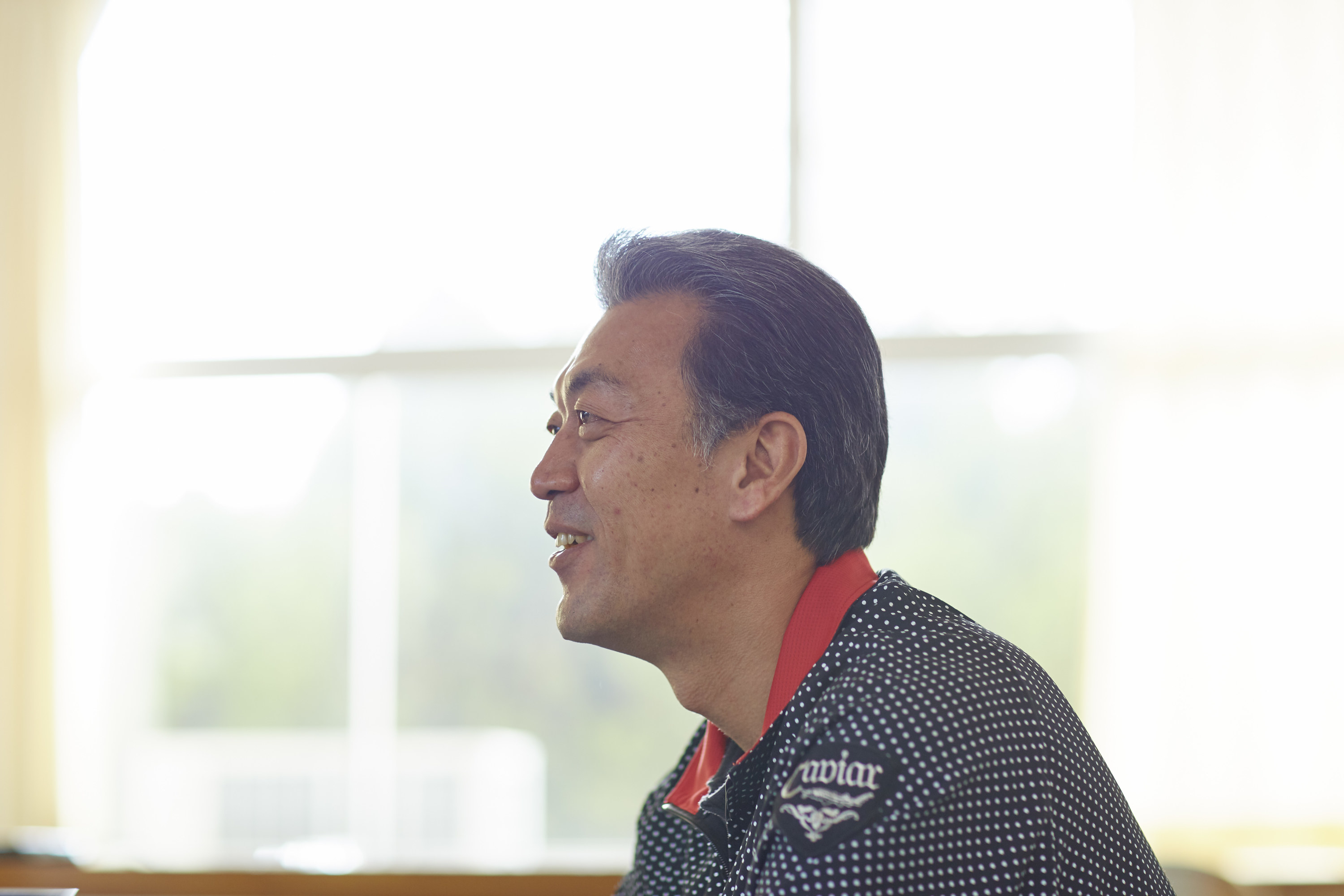
💡人生に影響を与えたコンテンツは?
絵画「洞窟の頼朝」(前田青邨)です。
敗戦を続けていた源頼朝がある日、味方が自分を含めたった7人になり、洞窟に隠れ潜んだ物語を絵にしたもの。今にも殺されそうな場面なのに、頼朝の目つきは未来を見ているように感じます。
後に日本のトップ(征夷大将軍)に立った源頼朝も、若い頃は戦に負け続けていました。これは、勝つまであきらめなかったからです。
商売も同じく、失敗しても失敗しても何度失敗しても決してあきらめることなく、成功するまでやり続ければいいだけ!それをこの絵が教えてくれました。
以前、会社の危機のときにこの絵が何度も頭に出てきて、踏ん張ることができたから、今があります。
💰これまでで一番大きな買い物は?
正直にお答えしますと家、車、と月並みになりますが、「キャビア養殖施設」でしょうか!?
🏖最近の癒し時間の過ごし方は?
家でゆっくりする。ドライブをする。ドッグランに行って、ワンちゃんの走り回る姿を見る。
🎤🎤🎤🎤
BuzzFeed Japanは「ほしい明日がみつかるメディア」として、新しい商品づくりやユニークな挑戦で、社会にポジティブなインパクトを与えている企業トップのストーリーを不定期で紹介します。情報提供は下記にお願いします。
akiko.kobayashi@buzzfeed.com
