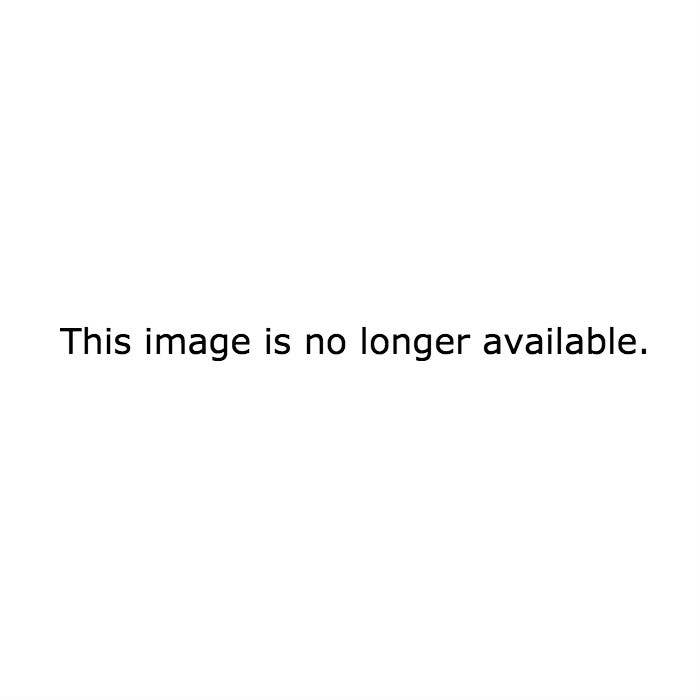
私はいつも心のどこかで、自分の生理は何かおかしいと分かっていた。不規則で1日目から痛みがひどく、放散痛が太ももにまで出て、ズボンが履けないほど足がむくんだ。鮮明に覚えているのは、子どもの頃、暑い夏の日にラウンダーズ(野球に似たイギリスのスポーツ)のピッチにいたときのことだ。紺色のズボンにまで経血が染み込んでいることに気づいた私は、どうやってその場を切り抜けようかと必死に考えた。
主治医は私にピルを処方した。それに続く5年間は、我慢できる程度に症状を抑えてくれる薬はないかと、いろいろなメーカーのものを次々試した。混合ピル、ミニピル、高用量ピル。どれも効いているとは思えなかった。最悪だったのは、黄体ホルモンだけの高用量ピルで、3カ月分の生理が来たかというほど出血し、ずっと終わらないのではないかと本気で心配した。19歳の時には、もうたくさんだと思った。体重は13kg近く増え、惨めだった。そこでピルをやめることにした。自分の自然のサイクルを何らかの形で管理すれば、うまくいくのではないかと考えたのだ。
しかし、続く5年間は、もはやピルが現実を隠してはくれず、症状は悪化した。生理はいつも一緒だった。大学生活、就職、パリへの移住、恋愛といった人生の冒険に、いつもついてきた。2014年の終わりには、生理痛はかなりひどくなっていて、私のパートナーは、体を丸めて吐き気と激しい震えに苦しむ私を見慣れてしまっていた。一度は、救急外来に連れて行ってくれたこともあった。
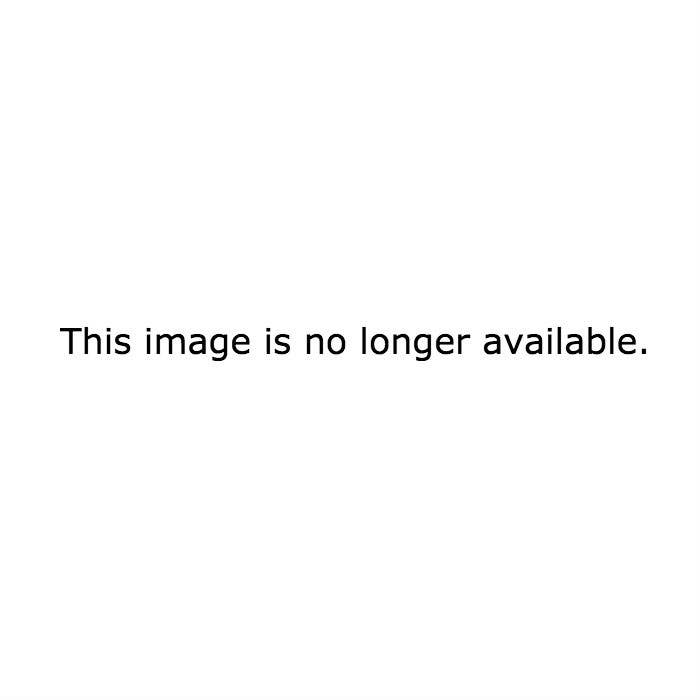
ずっと医者に通い続けていた私は、24歳のとき、初めて腹腔鏡検査を受けた。答えを模索し始めてから10年後、ついに病名が分かった。子宮内膜症だった。
この病気は第1段階(軽度)から第4段階(重度)にまで分類される。医者は私が最も深刻な段階にあると診断した。子宮内膜が子宮の外で成長し、ほかの器官にくっついて、嚢胞や癒着を起こしているということだった。大きな嚢胞が右の卵巣内で大きくなっていて、高度な瘢痕や損傷を残していた。手術をしなかったらおそらく破裂していただろう。あちこちにあった病変は、手術で慎重に切除された。
腹腔鏡検査の翌月は辛かった。体は治ったけれど、精神状態は悪化していたのだ。私は頭の中の叫びを無視することができなかった。「赤ちゃんを産めなかったらどうしよう」。子どもを産めないかもしれないという考えは、ときに重くのしかかり、胸が苦しくなるほどだった。
初めは、何か良い治療法がないかと、クリーン・イーティング(自然で体に良い食材を食べること)に目を向け、ポジティブな気持ちを心がけるようにした。ホットヨガを始め、精製糖と炭水化物をやめ、しまいには完全な菜食主義者になった。しかし、すぐにまた痛みを感じるようになった。なんとかコントロールすれば自分の体も「普通の」状態になるのではないかという妄想は、煙のように消えてしまった。
ほぼ1年後、私は急いで2回目の手術をせざるを得なくなった。主治医は、卵巣の嚢胞があまりにも早く再発したことを心配した。主治医と私は、生殖能力を温存するためには、もっと思い切った治療介入が必要だと合意した。だから、更年期を誘発する治療法を提案されたとき、私はうろたえずに、それを最良の選択肢として受け入れた。
私は6カ月にわたって注射を受けることに同意した。エストロゲン・レベルを一時的に抑え、自然な更年期のような状態にして、生理と生殖能力を停止させる薬だった。
子宮内膜症は、女性の月経周期に刺激されて拡大する。ホルモン・レベルの増減により、子宮内膜が毎月増殖するのだ。更年期を誘発するということは、エストロゲンが出ないということで、生理も来ないし、子宮内膜症の症状もなくなるということになる。お菓子づくりに例えるなら、卵や小麦粉、砂糖、バターなどは準備しておくけれど、ベーキング・パウダーがないからケーキは膨らまない、というわけだ。
私は単純にも、辛い生理がしばらくの間、鍵をかけて管理されるということにほっとし、ホルモンを注射することの影響は深く考えないでいた。ところが1回目の注射をして1週間もしないうちに、その影響を自分が軽く見積もっていたと気づいた。
自然な更年期を経験する女性の多くは、何年もかけて徐々に変化していく。時間をかけて体が新しいリズムに慣れ、心が順応していくのだ。でも私の場合は、治療の全重力が一晩で押し寄せた。
ただちに、5秒間でゼロから100まで到達するようなホットフラッシュ(のぼせや火照り)に襲われた。上唇に汗がたまり、Tシャツは背中に貼りつき、全身を焼かれているような感じがした。
さらに悪いことに、周りの人たちもおかしいとはっきり気づくほどの、明らかな被害妄想に陥った。体の状態のせいで自尊心が大打撃を受けたため、私の心はどんどん孤立していったのだ。
金曜の夜に友だちと飲んでいるとき、仕事仲間とランチしているとき、義理の両親の家を訪ねているとき、どんなときでも、ホットフラッシュが私の思考回路を乗っ取ることがあった。私は、話している相手が誰であれ、その人をじろじろ見つめて、私の顔から汗が噴き出していることに感づいたのではないかと気にしながら、できるだけ控え目で目立たない動作で、こっそり上唇に息を吹きかけた。ひとりだけサウナの中にいるような状態になったり、気分にムラが出たり、自分の中に引きこもったりという毎日の状態を隠すために取った変な行動が、体の症状と同じくらい目立つのではないかと心配にもなった。
私の体形も急速に変化した。お尻と二の腕にぜい肉がついたのだ。体形が変わった自分の姿は、母や祖母を思わせるものがあった。髪は薄くなり、パサついた。自分が自分に対して持っていたイメージが崩れてしまったと感じた。本当なら、色々なことができる将来への希望に満ちた、健康な25歳であるはずなのに。
更年期の症状を緩和するため、少量の合成エストロゲンを補う薬を使ってホルモン補充療法を受け始めた後でさえ、同じような心身の異常を感じていた。
第1回目の注射の後に始まった不眠は、だんだん耐え難いものになっていった。毎晩、ホットフラッシュが来たり引いたりして、パジャマを汗で濡らしながら、掛布団の下でのたうち回った。昼間の私はゾンビが歩いているようだった。
治療は転職の時期と重なっていた。そのため、ただでさえ非常にハードだった状態が極限状態になった。2回目の手術のあと、私は新しい職場にいて、話題を追いかけながらロンドン中を駆け回っていた。腹部の傷跡は治りきっておらず、私のホルモンは活動を停止していた。
けれども、40代の男性の雇い主に対して、「自分は、女としての活力がゆっくり衰えてきていて、自分のアイデンティティも失われていて、本調子じゃないんです」とは言えない。
新しい職場の同僚にだって、「仕事の後の飲み会はパスさせて。さっき13センチもある針をお腹に刺して、まだ痛いし、あざになってる。アドレナリンが出て、すぐ泣くし、震えもきてる」とは言えないだろう。
一番の発見は、この体験がとても孤立したものだということだ。生理がタブーだとすれば、更年期という言葉を口にすることは、それを超えたレベルのタブーなのだ。
私から、体の状況を打ち明けられた人たちは、どう反応したらよいか、あるいは何と言えばよいか分からなかった様子だった。驚いて口をぽかんと開ける、視線をさまよわせる、数秒間の気まずい沈黙。更年期という言葉は、会話を中断させてしまう。優しく気遣い、同情してくれた人もいたが、そのほかの人たちは明らかに戸惑っていた。
20代の友だちを目の前にすると、私は自分に起きていることがいたたまれないほど恥ずかしく思えた。若く活気にあふれ、しっとりした肌の彼らは、自信そのもののように見えた。それに引き換え私は、ぜい肉がつき、疲れ果て、完全にしぼんできている気がした。彼らはこの話題を気詰まりに感じるに違いないと思ったので、自分では面白くなくても、自虐的ユーモアをたっぷり混ぜて、手短かに話した。
この体験によって私は、更年期が不名誉になっている現実に気がついた。ほかの人の話ではなく、自分自身の経験があったからだ。4人に1人の女性が、ときには15年ほど続く衰弱性の症状を経験する。だが、更年期の話題を避けていたら、どうやって、雇用主や医療提供者により良いサポートを求め、パートナーや友だちからもっと理解してもらえるだろう。更年期の現実を白日の下にさらし、もう少し頻繁に皆の目に入るようにしなければ、変化など望めない。オープンに話し合い、現実と正面から向き合うことが当たり前の世の中にできないなら、それは女性への裏切りだ。
今、私は更年期を終えた。6か月間の治療が終わり、将来のために考えるべきとても重要な問題はあるものの、ゆっくりと自分を取り戻しつつある。長い眠りから目覚めたばかりの卵巣を抱え、次に何が起きるかをじっと待っている状態だ。
最高のシナリオは、更年期によって、残っていた子宮内膜症の細胞がしぼんでなくなり、一時的に、あるいは、完全に病気が治るというものだ。もうひとつの、あまり嬉しくない可能性は、病気が再発すること。子宮内膜症は高い確率で再発する病気なので、これは受け入れなければならない。
この6カ月の間に、私は、体感として未来と向き合うことになった。そしてそのお陰で、自分が今大切だと思うことを成し遂げていこうと、強く思うようになった。そして、非常に現実離れした困難な課題に取り組む私をしっかりと支え、受け入れてくれたパートナーを、心から誇りに思い、感謝した。私は、前より打たれ強く、柔軟で率直な人間になった。
雇用主にはまだ、自分の厳しい状況を知らせていない。しかし、沈黙の文化に戦いを挑むため、自分のことをもっと詳しく周りの人に説明しようと努めているところだ。治療の最中、私は、大きな仕事を断った。引越を伴うものだったからだ。そして、なぜその選択ができないかを正直に伝えた。私は、恥ずかしいと感じる必要などない、と思った。
私はずっと、未来が不確かであることを受け入れざるを得なかった。今から5年後に、人生がどうなっているか、保障はまったくない。主治医は、右の卵巣の嚢胞が3度目の再発をしたら、次の選択肢は卵巣の摘出だと言っている。もしそうなれば、大急ぎで家族をつくることを考えなければならないかもしれない。あるいは家族は持たないことになるかもしれない。どちらにせよ、そのときが来たら意思決定をすることになる。
私の健康状態は、非常に厄介だ。しかし、「子どもを産めるか否か」が私という人間を定義するわけではない。そのことは忘れないでいるつもりだ。

