
被災地の幽霊
ある学生が書いた卒業論文が話題になっている。「呼び覚まされる霊性の震災学」(新曜社)に収録された「死者たちが通う街—タクシードライバーの幽霊現象」だ。
東北学院大の工藤優花さんが宮城県石巻市のタクシー運転手が実際にあった幽霊について聞き取り、まとめたものだ。
津波被災地で幽霊をのせたタクシー運転手がいる。そこだけが切り取られ、「幽霊はいる」「非科学的なもので、論文とはいえない」といった声がネットにあふれた。

現場から問う死生観 『死者』『喪失感』と向き合う
卒論を指導した社会学者の金菱清教授は、苦笑混じりに語る。
「幽霊をみることもよりも、幽霊現象を通して死生観、『死者』との向き合い方を考察することがこの論文の主題なのに」
金菱さんはフィールドワークを専門とする社会学者だ。

大学進学を決めた1995年に、阪神淡路大震災を経験している。その時、疑問を抱いたのは目線の位置だった。崩れ落ちる高速道路、被害があった神戸市内。強調されたのは上からの映像だ。
「伝えられる映像の多くは、上空からみる鳥瞰図目線になっていて、そこにいる人の目線が抜けている」
復興も同じだ。常に地図上の科学的なシミュレーションがベースになり、鳥瞰図から一見、合理的な計画が打ち出される。

割り切れない思い
「大事な人を亡くす、行方不明になる。それだけでなく、街そのものが変わったという喪失感がある。復興を考えるなら、現場に住む人が持っている人間観、死生観、感情から考えないといけない」
死者や喪失と人はどう向き合うのか。学生たちと東日本大震災の被災地を歩き、インタビューを重ね、調査を続けている。
幽霊現象はまさに、被災地域の死生観が象徴的に現れている事例だと考えている。
「生きている人と死者の中間に、行方不明に象徴される『あいまいな死』があります」
「当事者のあいだでも、生と死はきれいにわかれていない。遺体が見つからないため、死への実感がわかず、わりきれない思いを持っている人の気持ちとどう向き合うのか。幽霊現象から問われているのは慰霊の問題であり、置き去りにされた人々の感情の問題なのです」

夏場、コートを着込んだ女性は「南浜まで」と告げた
工藤さんがタクシー運転手の体験を聞き取った石巻市では、津波などによる死者は3277人、行方不明者は428人に達している。
論文から、証言を抜粋してみる。
震災で娘を亡くしたタクシー運転手(56歳)は石巻駅周辺で客を待っていた。震災があった3月11日から数ヶ月たった初夏、ある日の深夜だった。ファー付きのコートを着た30代くらいの女性が乗車してきた。目的を尋ねると、女性はこう言った。
「南浜まで」
「あそこはもうほとんど更地ですけど構いませんか。コートは暑くないですか?」
「私は死んだのですか?」
女性は震えた声で応えた。運転手がミラーから後部座席を見たところ、誰もいなかった。
「『東日本大震災でたくさんの人が亡くなったじゃない? この世に未練がある人だっていて当然だもの。(中略)今はもう恐怖心なんてものはないね。また同じように季節外れの冬服を着た人がタクシーを待っていることがあっても乗せるし、普通のお客さんと同じ扱いをするよ』。ドライバーは微笑んで言った」
「おじちゃん、ありがとう」。少女はすっと姿を消した
別の運転手(49歳)は小学生くらいの女の子を乗せた、と証言している。2013年の夏、時間は深夜だった。コート、マフラー、ブーツを着た少女がひとりで立っていた。不審に思いながらも「ひとりぼっちなの」と話す少女。家の場所を答えたので、そこまで連れて行き、手をとって少女を降ろした。
「おじちゃん、ありがとう」
そう話した少女は、すっと姿を消した。
運転手は「『お父さんとお母さんに会いにきたんだろうな〜って思っている。私だけの秘密だよ』。その表情はどこか悲しげで、でもそれでいて、確かに嬉しそうだった」。
幽霊現象に遭遇した各タクシー会社の記録では、無賃乗車があった扱いになるという。客を確かに乗せたが、代金は支払われなかったという扱いだ。

「(亡くなった人が)会いにくるの」
被災地で幽霊の話を聞くのは決して、珍しいことではない。取材をするなか、私も思い返したことがある。石巻市内の居酒屋で聞いたこんな話だ。もうすぐ、震災1年を迎えようという時期だった。
この店を切り盛りする50代女性は、震災後、店を休み、炊き出しなどボランティア活動をしていた。見慣れた街の様子は一変していた。遺体を前に泣き崩れる遺族、そして行方が分からない家族を連日探す人々を何度も見たという。
「ご遺体が見つからないんだよ。あんなに悲しいことはないよ」
「だからなのかね…」。私1人になった店内で、女性は私のコップにビールを注ぎながら、こう口を開いた。
「言いにくいことだけどね、会いにくるのよ。見つけてほしって」
「誰がです?」
「亡くなった人が」
これも震災の年、ある夏の日だったという。車で津波被害が甚大だった地区を走っていたところ、コート姿の女性が立っていた。
「なんで、この季節にコート?」
驚いて通り過ぎたあと、すぐにサイドミラーで確認したが、誰も立っていなかった。
この女性も、楽しい思い出話を語るように微笑みながら話していた。

「『幽霊』なんて言うな」 運転手が持つ畏敬の念
工藤さんの調査と共通しているのは、恐怖感がないことだ。単なる怪奇現象ではなく、自分たちが出会った相手への敬意がある。
工藤さんは、タクシー運転手への聞き取りを重ねる中で、こんな経験をした。
「私が『幽霊』というと、そんな風に言うなと怒る方がいました。きっと、『幽霊』という言葉に興味本位だと思われる響きがあったからでしょう。怪奇現象とか、心霊写真とか恐怖を楽しむような言葉だと思われてしまった。『亡くなられた方』とか『(亡くなった方の)魂』というと、お話してもらえました」
運転手から、こう問われたこともある。
「きみは大事な人を亡くしたことがあるかい? 人は亡くなると、眠っているように見えるんだ。あのとき、こうすれば良かったと後悔する。亡くなっても、会いに来てくれたら嬉しいんじゃないかな」
彼らは「幽霊」の存在に理解を示し、温かい気持ちで受け入れている。そこにあるのは死者に対する畏敬の念だ、と工藤さんはそう考えている。

生と死の中間にある「あいまいな死」
金菱さんは、東日本大震災を特徴づけているのは「『あいまいな死』が多いこと」であり、「地震から津波到達まで時間があったため、『もっと自分がこうしていれば、助かったのではないか』という後悔の念が強く起きること」だと指摘する。
「あいまいな死」は、生きている人にとっては、本人が死んだのかどうか明確にはわからない。「本当に私の大切な人は死んでしまったのか」と問い続け、死を受け入れられない。
そして、「あのとき、電話をしておけば…」「もっと声をかければよかった」と自分を責め続けることになる。仮に葬儀をしたとしても、その気持ちはおさまえることはない。
無念に寄り添う
運転手らの言葉には「あいまいな死」とどう向き合うか、そのヒントが詰まっている。彼らは「あいまいな死者」の存在を肯定し、人々の無念さにすっと寄り添っている。
「大事なのは、幽霊現象があるかないかという問題ではない。体験した人が『死を受けいれられない』という声に寄り添い、その存在を肯定していること。中間領域を消さずに、丸ごと肯定し、死者に対して敬意を払っていることが大事だ」と金菱さんは話す。
死者への敬意は別の調査からもうかがえる。

死者への敬意
ゼミ生の小田島武道さんは同じ石巻市内で、仮埋葬という形で土葬した遺体を、遺族の要望で掘り返し、さらに火葬した葬儀会社の取り組みを調査した。
土葬された672人もの遺体を、葬儀会社のスタッフたちは作業服姿で掘り起こしにあたった。作業服姿は敬意を欠いているように思えるが、そうではない。
土葬され、梅雨、夏場が近くなり腐敗も進む、遺体の泥を丁寧に拭い、棺に納めるには作業服しか選択肢がなかったのだ。一人一人の遺体に合掌し、効率を優先せずトラックを使わなかった。遺族感情を重んじ、霊柩車を模した10台の車で遺体を運んだ。
被災者は投げかける「人は死んだら終わりですか?」
ニュースや記録を通じ、私たちは死者や行方不明者を数字としてまとめてみてしまうことが多い。しかし、そこには一人一人の死があり、それぞれの家族や地域の感情がある。死も一様ではない。
自分たちの死生観にもとづいて、生と死をきっぱりわけることは、中間領域の存在を否定することであり、あらゆる死と向き合ってきた当事者の感情を否定することにつながってくるのではないか、と金菱さんは問う。
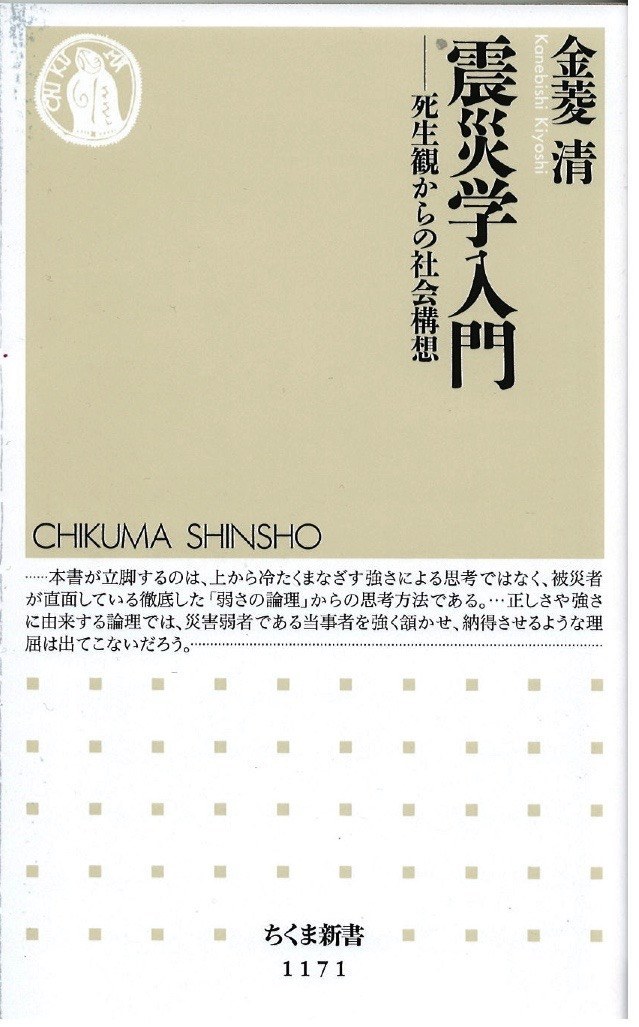
金菱さんは新刊「震災学入門」(ちくま新書)の中で、中学生の子供を亡くした被災者が、生前に通っていた中学校で使われていた机に刻んだ言葉を紹介している。
「街の復興はとても大切なことです。でも沢山の人達の命がここにある事を忘れないでほしい。死んだら終わりですか?」
金菱さんは言う。
「この問いにどう応えるでしょうか?被災地の人々が多様な死者へ払っている敬意から私たちはもっと学ばないといけない。死者の思いを受け止めない慰霊は、誰の感情に寄り添っているのか。もっと被災者の視点から問われないといけないのです」

