黒づくめな服装に、髪型はモヒカン。福祉施設の園長を務める福森伸さんの出で立ちは、肩書きから想像されるであろう枠を容易にはみ出している。
鹿児島に「しょうぶ学園」という年間1万人の来訪者が集う知的障害者、精神障害者の自立支援を行う施設がある。「障害者×アート」の領域を開拓したパイオニア的な存在だ。

利用者は言われた通りの作業をして、1日を過ごす。以前はそんな形だった施設のあり方を園長の福森さんは劇的に変えてきた。
だが、最初から自由な施設をあり方を体現してきたわけではない。
昨年12月に刊行された著書『ありのままがあるところ』で綴られたのは、脚光をあびる裏で葛藤を続けた30年余りの日々だった。
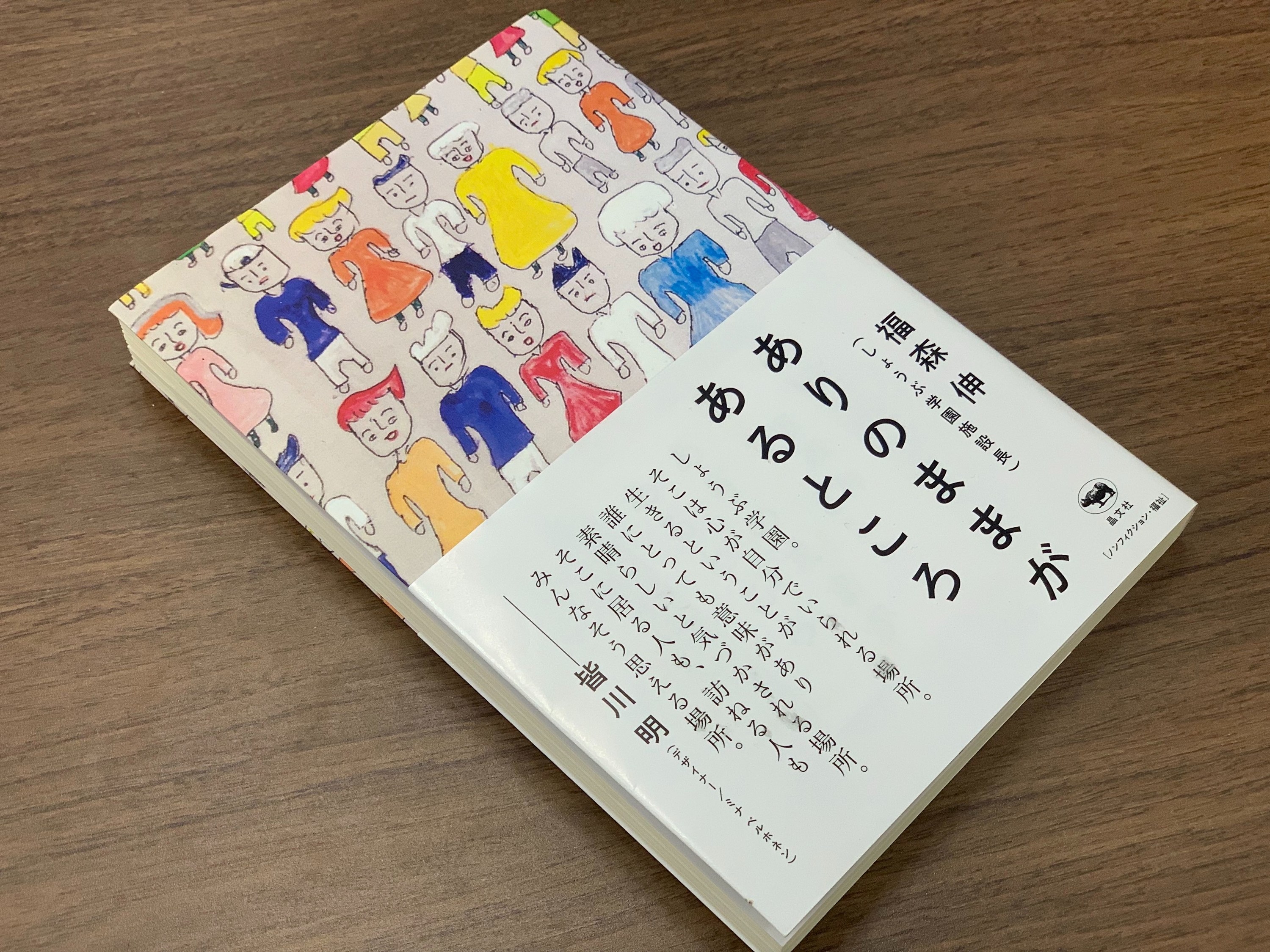
福祉の勉強をしていなかったからこそ
「結局、福祉の勉強をしていなかったことがよかったんでしょうね」と福森さんは言う。
「働き始めてから15年くらいの間は目の前のことに没頭して…40歳くらいの時かな、そこから福祉の勉強をしはじめたんですよ。社会福祉士の資格を取ったのは40歳を過ぎてからでした」
福森さんは笑いながら語る。
「しょうぶ学園」は1973年に両親が開園し、運営してきた施設だった。
大学卒業後、3度、就職活動に挑戦した。出版社への就職を夢見たこともあったが、願いは叶わなかった。

その後、ゴルフのキャディ、レストランの料理人など東京やアメリカでアルバイトをしながら暮らしたが、24歳になったとき、故郷・鹿児島へ戻ることを決める。
「パターナリズム」指導訓練への懺悔
帰ってから最初の10年間は利用者の「指導訓練」にあたる日々を送った。
寝て起きて、歯を磨き、朝礼をする。「そんな彼らの生活が、体育会系の寮生活のように見えた」と福森さんは言う。
働きはじめた当初の思い出を振り返るとき、顔には後悔の色がにじんだ。
福森さんは日本体育大学で学び、ラグビー部に所属していた。人に規律正しさを求め、厳しく接することは「得意だった」という。「何かおかしい」、時折感じた違和感は心の奥に押し込めて、目の前の利用者の指導にあたった。

「僕はもともと上下関係、先輩後輩という関係性に慣れ過ぎていた。日体大でラグビーに打ち込んで、耐える力も持っていましたから。でも、施設の利用者は望んでその環境を選んできたわけではない。そんな人々に何かを耐えさせることに意味があるのか、問い続けました」
良かれと思って、相手の利益のために、と本人の意思も問わずに介入する、指導訓練というパターナリズムには、懺悔の気持ちがいまもある。

「知的障害を持つ人々は好きなものが好き。ときにはTPOをわきまえずに感情を発露してしまうこともある。そうした彼らの感情を僕らはこれまで抑えてきました。学園のルールを言い聞かせなければ、彼らが秩序を守れるとは思ってもみなかった」
「最初は、指導訓練を良かれと思ってやっていた。でも、果たしてこの指導訓練は何のためなのかを考えた。そして、施設は利用者たちが幸せになるためにあるはずだと気付いたんです」
葬儀で笑い声を上げた利用者がいた。親族の葬儀から元気に帰ってきた利用者もいた。施設に帰ってきた時の第一声は「たくさん食べた、お代わりした」という一言だった。
以前なら、「ここで笑っちゃダメ」、「そういうことを言ってはいけません」とたしなめてきた。だが、そうした「ありのまま」でいる人を、今はそのまま受け入れたいと福森さんは思う。

当初は自由にものづくりをする環境を整えることにも否定的だったと明かす。利用者たちは指示を与えないと要領よく動けないと思い込んでいた。
だが、ある日、指導しているだけでは「もう無理だ」と限界を感じた。時同じくして、利用者たちが物作りをしている姿を見たとき、それまで自分の頭の中にあった誤解に気付いた。
「なぜ1円にもならないものを、そんなにニコニコしながら楽しそうに作っているのか」、不思議でたまらない。
心赴くままに作業をする時間を作ると、そこには何かをつくることに一途に打ち込み続ける人たちがいた。
二十年以上前、10人の職員が次々に退職した

学園を変えるため、それまで利用者が取り組んでいた割り箸の袋入れといった下請けの仕事をやめた。
代わりに焼き物や家具を作り、パンを焼くことをはじめた。指導にあたる職員たちにも、新しい役割を期待した。
「僕はその頃はね、学園の決まりを少しずつ削除していったんですよ。そして、もっと外出できた方がいいでしょう、お酒も飲めた方がいいでしょう、と」
「自分の意見を言ってくれ」と、職員たちにも新しい考え方を求めた。だが、面と向かって意見する職員は少なかった。今から二十数年前のことだが、そんな時、10人の職員が次々に退職した。
新しいあり方を探ろうとする中で、それまでの「指導訓練」を真面目に続けてきた職員との意識の開きに気付くことができずに起きた出来事だ。

「当時の僕はもう、前に進むだけ。みんなはこんなバカ息子にはついていけないと思ったんでしょうね」。福森さんは、淡々とした口調で振り返った。
そして一瞬の間をおいて、「後悔はない」と語る。
福森さんの方針に理解を示していなかった人は多かった。
「結局、周りの人が良いと言ったものが良いという人がいるんですよ」、社会の流れの変わり身の早さを何度も思い知らされてきた。
園の門を閉ざしたくはない
改革の旗振り役を率先して務めた福森さんも、たった1度だけ、それまでのやり方を守ろうとマニュアルの整理などを行い、「保守的になった時があった」と明かす。それは父親が倒れ、学園の運営を一手に担った2003年のことだ。
「責任がきた途端に、保守的になって…ああ、僕はズルい人間だなって思ったよ。責任を負わなくてはいけなくなったら保守になるのか、って。それまで自由奔放を求めて、好き勝手やらせてもらっていながらですよ」
2016年、か神奈川県相模原市の障害者施設「やまゆり園」で19人の入所者が殺害される事件が起きた。事件後、外部との交流が盛んなしょうぶ学園のセキュリティを問う声が寄せられることも少なくない。
それでも、ここまで開いてきたしょうぶ学園の「門を閉ざしたくはない」と福森さんは言う。
「あの事件以降、コメントを求められるたび、我々には門を閉ざす義務や必要があると思いますか?閉ざさないといけないのでしょうか?と逆に問いかけたくなるのです」
「1%のリスクを防ぐために、99%の自由を奪いたくはない。あれは"事件"です。1つの"事件"のために、全ての施設が外部への門を閉ざすことに僕は反対です」
「ノーマル」なんてない、だからこそ

「知的障害を持つ人の多くは、同じ行為を繰り返すことが少なくない」。だからこそ、「応用力が効かないということはマイナスなこととして受け止められがちだ」と指摘する。
だが、学園を運営する中で「それは、一途であるという裏返しの側面がある」ということに気付いた。繕えないことを、悪だとは思えない。
最近も利用者4人と組んだバンドで良い演奏を引き出そうと、リードしすぎたと反省しているのだという。「俺は間違っていた」、そう断言する福森さんは笑顔だ。

その上で、こう問題提起する。
「僕らは身の丈を超えて無理をすることを、向上心と言ったり、挑戦心と言ったりして、美や善と捉えるけれども、それだけが良いことなのか?」
根底にあるのは、障害によって「できないこと」に目を向けるのでなく、「できること」や長所に目を向ける向き合い方だ。

「しょうぶ学園の利用者たちは、将来のためではなく今できることをやる傾向にある。安心した暮らしをしたい人は安心して暮らせるようにするべきだし、挑戦をしたい人には挑戦できるような基盤が必要。最近はどちらが正しい、どちらかだけに入れ込むのではなく、両方の生き方が存在することが大事なのだと捉えられるようになりました」
「普通の暮らし」とよく耳にするが、少数派の人たちと多数派の人たちに共通する「普通」はあり得るのか。あるとしたら、誰が決めるのか。
「普通の暮らし」を実現しようとするノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンに向けた動きは、障がい者に対する社会の認識の変化を促すようでいて、結局のところ社会よりも「障がい者」の変容を重視しているように読み取れないだろうか。
ーー『ありのままがあるところ』(晶文社)

「利用者の考えに沿って生きていたら、自分の生き方を考えさせられまくって…何が普通なんだろうか?ということに行き着いたんですよ。ノーマルとされるものがないならば、ノーマライゼーションなんてものもないじゃないかと」
そう福森さんは静かにつぶやく。
「障がい者」をありのままに受け入れていく思想こそが求められるのである。なぜならノーマルとは何かは永久に曖昧なのだから。
ーー『ありのままがあるところ』(晶文社)
こんな言葉で、著書を締めくくった。
障害者と健常者、そんな線引きがあるとするならば、「僕はその間にいたい」。
多様性という言葉が、ごく一般的に使われるようになった。だが、自分と他の誰かは違うということを前提に生きることには常に摩擦が付きまとう。その道は決して楽ではない。並大抵の覚悟では、きっと怯んでしまう。
利用者も職員も間違いを積み重ねながら、それでも扉を閉ざすことだけはしたくない。しょうぶ学園、あらゆる人の「ありのまま」がそこにはある。
