静かな録音ブース。男が声を吹き込むことで、情熱は完成する。
ナレーター窪田等。1998年から続くドキュメンタリー番組「情熱大陸」でナレーションを務めてきた。
「最初はオープニングの曲も違ったんですよ。葉加瀬太郎さんになってからノリのいい曲に変わったねと言われてね」
番組当初、女性ナレーターと週替わりに担当していた時期もあったが、20年の間「情熱大陸」に関わり続けた人間は窪田ただ一人だけだ。
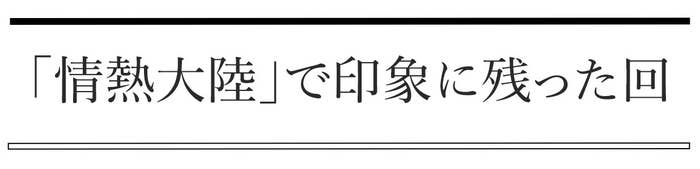
起用のきっかけは窪田がオープニングナレーションを務めた「F1グランプリ」だった。
窪田の声を聞いたF1好きの初代プロデューサー河村盛文が「一緒に仕事がしたい」と「情熱大陸」の話が舞い込んだ。
「とにかくドキュメンタリー。一人の人、普通の、一生懸命な人を追いかける番組だからと言われて。説明はそのくらい。ナレーション収録って最初に綿密な打ち合わせがあるとかではないんですよ」
初回で取り上げたのはプロゴルファーの丸山茂樹。当初は2年で100人を取り上げると聞いていたが、番組は今年4月で20年。密着取材した人物は述べ1000人を超えた。
「毎回取り上げる人も違うし、ディレクターも違う。だから、いつも新鮮。20年やってきたという意識はないです。毎週楽しみながら、収録現場に向かってます」
取材中、窪田は何度も「飽きない」と繰り返した。

印象に残った回について聞くと、2017年のクリスマス直前に放送した、中継先から生でナレーションを読んだ回を挙げた。
「最後にしゃべることがなくなってしまって、時間が余っちゃった。音楽が流れたあとで、しゃべらないと無音で10秒。それはまずい。困ったな、言っちまえとアドリブで『メリークリスマス』と言って。うまくいってよかったです」。
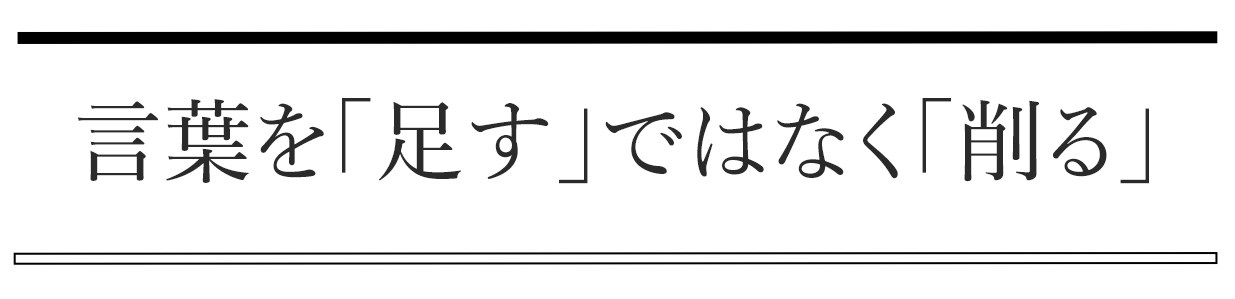
2010年1月17日に放送された画家の石井一男を取り上げた回も胸に残っている。
「録り終わった後、ディレクターから『窪田さん、あそこ変更してください』と言われて。石井さんが影絵で遊ぶシーンで『石井は影絵で遊んでいた』というナレーションだったんです。それでもいいじゃないですか。でも『遊んでいた』だけにしてくれと。ナレーションで説明してしまうより、ひと言。言葉を削ると情景が引き立つ」
足すではなく、減らす作業。ナレーションを入れるために消されていた映像の笑い声を活かしたいからと、窪田自らコメントを削るよう提案したこともある。

番組ではナレーションの言葉が、取材相手を持ち上げすぎてないかにも気を使っている。
ある時、台本に書かれていた「今や、この世界にはなくてはならない存在として輝いている」との言葉に対し、プロデューサーが注意した。
「『まだ上があると考えている人に対し、頂上まで近いとナレーションで語るのは逆に失礼なんじゃないか』って。その話を聞いた時、プロデューサーって優しいんだなと思った。テレビは少しのことでも、いかようにも番組で面白くできる。でも、ドキュメンタリーでそれをやると、せっかく出演してくださった方に失礼にあたることがある」
こうした作り手たちだからこそ、取材相手が他では見せない表情を見せてくれる。窪田は「情熱大陸」が続いた要因を、ディレクターやスタッフの一生懸命さと語る。
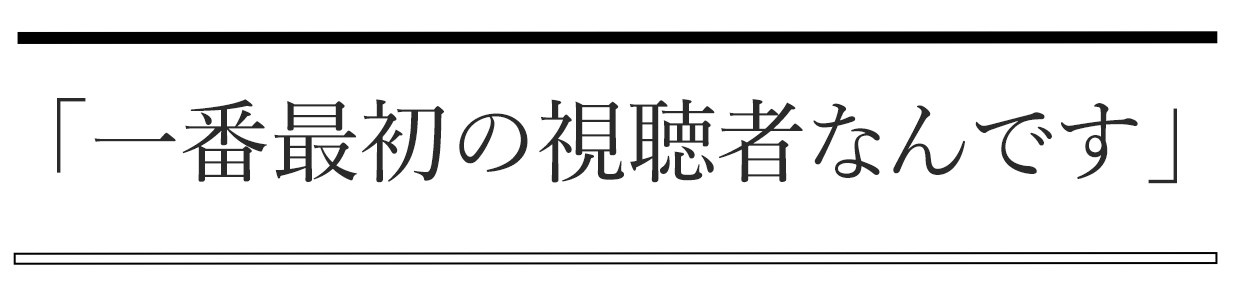
ナレーションの収録は放送前日の土曜日になることもある。ギリギリまで番組を作り込むためだ。
収録現場ですんなりいかないこともしばしば。ある時は、台本を一から直すからと、ディレクターに5~6時間どこかで時間を潰してきてくれと言われたこともある。
「普通のナレーターなら怒っちゃうかもしれない。でも、僕は面白がっちゃう。金魚鉢の内側の演者じゃなく、スタッフ側にいたいんです」

窪田自身も台本に対して提案する。こだわるのは「初めて映像を見た人がわかるかどうか」。
実は番組で取り上げる人物の情報を全く入れず、視聴者と同じ視点で収録に臨んでいる。
「ディレクターはずっと編集をして何度も見ているけど、番組は初めて見る視聴者がわからないといけない。だから、台本を渡されたとき『いや、これではわかりにくい』とすり合わせする。一番最初の視聴者なんですよ。色々聞いて分かっちゃうと作り手側と同じになっちゃうから、なるべく最初に感じたことを言わせてもらう」
「初めて見た時の『あっ、こういう変わった人なんだ』という感覚が語調に入ってもいいんじゃないかって。作家さんが遊ぶときもありますよ『なんか、おかしな雰囲気だ』『なんか、ちょっと変だ』と入れたり。そうやっていうまいところで煮詰まっていく」
ナレーターとしての仕事を逸脱しているのではないか。時に考える。
「一字一句正確に読むのがナレーター。たしかにそう。でも僕の場合は、スタッフ側にいたいから、こうしたらどうと提案する。もしかしたらナレーターの境界を超えているかもしれない。でも『情熱大陸』ではそれも許されるんじゃないかとやってます」
とことんこだわりたいし、付き合いたい。だから「情熱大陸」の収録の後には仕事を入れないようにしている。
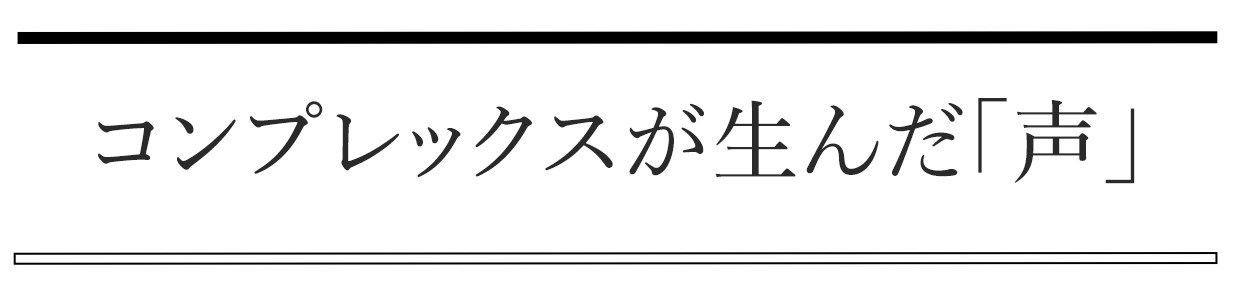
1951年、山梨県生まれ。小学校の頃に担任からアナウンサーになればと、声を褒められたことを覚えている。好きなものは飛行機に宇宙。ごくごく普通の少年だったという。
高校卒業後は飛行機の整備の仕事に就きたいと考えていたが、叶わず富士通へ入社。無線装置の調整をする仕事に就いた。自身を演者ではなく、技術屋と考える原点はここにある。
仕事にも慣れ、マレーシアへの転勤話が持ち上がった21歳の頃、通勤で使う電車の中吊り広告に「CMナレーター養成講座 受講生募集」とあるのが目に入った。
何かをやりたいと思っていた時期。会社が終わると講座に通い、原稿を読む心地よさを知った。

1年のカリキュラムが終わる頃にはポツポツをCMの仕事が入り始め、やがて仕事を辞めて、ナレーター一本で暮らすことを決意する。
ただコンプレックスもあった。
「演劇を志していたわけではないから。基礎をやって来た人とはやっぱり違うじゃないですか。たった一年やそこら勉強して、あとは誰についたわけでもない。独学ですから。自分で模索しながらだし、不安があるんですよね。だからどんな仕事もおごらず、こうやれと言われたらやる。そうしていかないと残っていけないと思ってました」
アナウンサーだとちょっと正統派すぎる。役者だと逆に崩しすぎる。その真ん中、他とは違うナレーションを目指した。
バックボーンがないことが、今日の窪田のナレーションを築き、やがて「情熱大陸」の起用につながった。
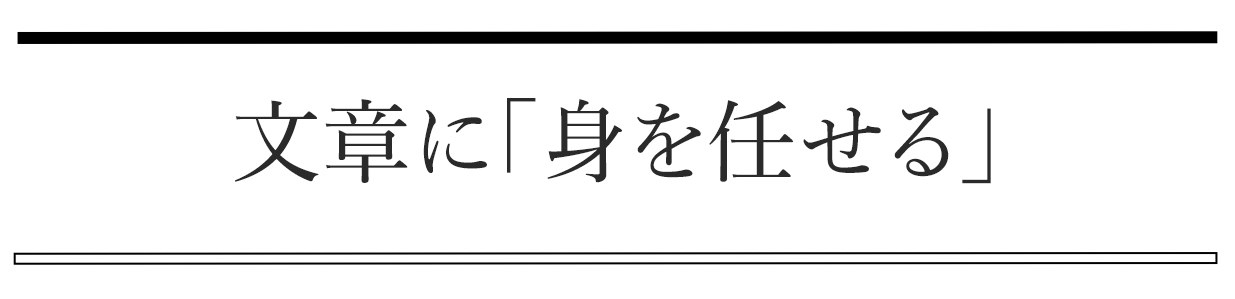
現在からは想像できないが、若い頃はラジオCMの仕事など短い作品が多かったことから、長く語るナレーションが苦手だった。
企業の説明映像のナレーションを担当したが、ちょっとしゃべっては間違える。なんでしゃべれないんだ。失敗するたびに録音ブースで自分の頭を何度も叩く。恥ずかしさがこみ上げた。
だから新聞の社説やコラムなど、とにかく長い文章を自宅で声を出して読み続けた。すると文章の流れがわかるようになってきた。
「慣れなんだなと思います。文章の流れに身を任せる。その時は苦しかったけど、転機だったかもしれないですね。若い子には言っているんですけど、誰だってそういう時期はあるんですよね。楽天的だからそんなに苦労したとは思いませんけど、人に迷惑をかけるのがとにかく嫌で、今でも思い出しますよ」

ナレーターとして確固たる地位を築いているが、変化にも敏感だ。現在のナレーションの主流は強い声、目立つ声。
そこに合わせに行くべきか、葛藤がある。まだまだこの仕事をやり続けたいとの思いがあるからだ。
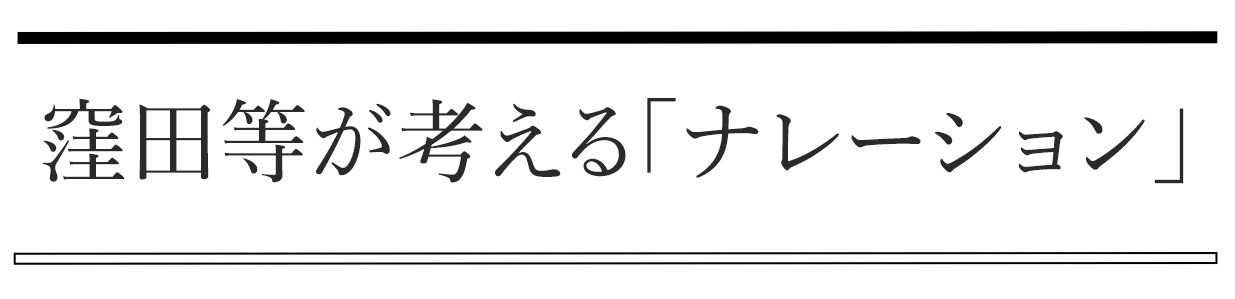
では窪田にとってナレーションとは何なのか。
「バラエティー番組だとナレーションが目立つこともありますけど、ドキュメンタリーは主役がいるものなので、主役になっちゃだめ。あくまで介添人。なくてもいいけど、あった方がより豊かに感じる存在。誇りは持っていますよ。字幕スーパーじゃわからないだろうって」
平面の文章をどうやって空間に向けて、匂い立たすことができるか。そこに面白みを感じている。
「自分と違う目線が大事。80点は取れるんですよ。でも自分がかっこいいと思ったタイミングでなく、ディレクターや音楽や効果音をつける音効からの指示に合わせると、自分では気づかないかっこよさが出る。そういう時に心が震える。ナレーションはみんなで作るんです。時短、時短の今の時代のやり方には合わないかもしれないですね(笑)。でも『情熱大陸』ではそれができています」
仮に自身の「情熱大陸」があったら、ラストシーンに、どんな言葉を語りたいか。
そう質問すると、意外な答えが返ってきた。
「考えたことがないですし、その日が来るのが嫌ですね。たぶん最後の仕事になるだろうから。もっとやっていたい。もっとしゃべっていたい。情熱大陸のナレーションをずっとやっていたい。20年。年数で考えると長いけれど、でも毎週その日がやってくるから。楽しみな日がやってくるから」
収録の日が今でも待ち遠しい。窪田等の情熱は尽きない。
