待って、ウッディってこんなにおじさんだったっけ?
「トイ・ストーリー4」を観て少し驚いた。いつもと変わらず元気で勇敢なウッディが、少し歳をとったように感じた。いや、自分が大人になったからだろうか。
「トイ・ストーリー」が日本で公開されたのは1996年。既に20年以上も前の物語だ。しかし、おもちゃは本来、歳を重ねることがない無機質なもの。変わらない存在であるはずだ。

「ウッディは第1作目の時点で古いカウボーイ人形でしたからね。でも、時間の経過とともに、ウッディも変わり続けてきました」
そう語るのは、ジュシュ・クーリー監督。現在39歳。1作目が大ヒットした当時、まだ15歳だった。
彼は「トイ・ストーリー」と一緒に育ってきた。
完璧な3部作の後に、これ以上何を語るのか
「この作品と共に育った世代の一人として、続編の監督を務めるのは大きなプレッシャーでした。
『トイ・ストーリー3』の終わりは素晴らしかったですし、そこから何かを変えようとは思いませんでした。ウッディとアンディのストーリーは、前作でおしまいです。ただ、ウッディにはまだ語るべき物語があると考えたんです」

「トイ・ストーリー」3部作は、これまでウッディとアンディの関係を描いてきた。
1作目のウッディは、バズの登場により嫉妬に苦しみ、それを克服する。「2」では、いつか来るアンディとの別れを意識し葛藤しながら、それでも共に過ごすことを決意した。
そして最終章といわれた「3」では、役割を終えたおもちゃが、それぞれの存在意義を模索しはじめる。
監督が今回ウッディに語らせようとした、終わった物語のその後とは何なのか。

「トイ・ストーリー4」は、"empty nest"の物語
「実は、ウッディのキャラクターを発展させるプロセスにおいて、ウッディを『親』として考えているんです。
彼の親としての仕事はずっと、こどものそばにいてあげることでしたが、『トイ・ストーリー3』では、大学に行くアンディを見送りましたよね。
自分の役目として18年間もやってきた子育てが終わってしまい、これから何をするのか。自分は何者なのかという問題に直面するわけです。
言ってみれば今回は”empty nest”の物語なんです」
empty nest (空の巣)は文字通り、長い子育てが終わった後の喪失感を指す言葉だ。

「トイ・ストーリー3」で、片付いてしまったアンディの部屋を見た母親が目に涙を浮かべる場面がある。空っぽの部屋に響く声が印象的なシーンだ。
ウッディもまた、彼女とともにアンディを育てる親の一人だった。
「これは人生で自然に起こることですし、特に大人にとって意味を持つストーリーになります」
子育てが終わっても人生は続き、新たな葛藤や発見がある。「トイ・ストーリー」の世界では、おもちゃも人間と同様だ。
最新のおもちゃは、敢えて登場させなかった
変わったのはおもちゃの内面だけではない、こどもたちの関心も、時代とともに移ろってゆく。
ウッディが一人の少年の成長を見守る間に、おもちゃたちはさらに古ぼけた。モデルとなったおもちゃの多くは、すでにアンティークと呼ばれている。

3歳児がおもちゃよりもYouTubeに夢中になる現代において、素朴で時代遅れのおもちゃたちは相手にされるのだろうか。
ウッディたちだけではない。今回、初登場したキャラクターもWi-Fiに対応した最新モデルではなく、古くて地味なおもちゃばかりだ。
監督は今作ではむしろ、おもちゃたちの古さをストーリーに活かしていると話した。
「『トイ・ストーリー』シリーズの面白さの一つは、新たなおもちゃを市場に出してきたことです。すべての作品で新しいおもちゃを登場させてきました。

なので、今回は逆をやってみようと思ったんです。そして若い世代が知らない古い時代の、見たことのないようなおもちゃを登場させてみました。
また、アニメーションの技術が進化したことで、古びた風合いや、経年を感じさせる表現も前より豊かにできるようになりました」
古いおもちゃの哀しさと強さ、そして人間臭さ
例えば新たに登場するギャビー・ギャビーは、アンティークのままごと人形だ。製造不良で内蔵のボイス・ボックス(おしゃべり機能)が壊れているため、遊んでもらった経験もなく、アンティークショップの棚で忘れ去られていた。
故障さえ直ればこどもに愛されるはずと夢見る彼女の前に、同じ型のボイス・ボックスを持つウッディが現れる。

愛されることのないまま古びた人形と、アンディの宝物だったウッディの対比が残酷に浮かび上がる。ウッディに対する憧れや嫉妬、古いおもちゃとしての焦りは、やがて彼女を暴走させていく。
愛されることだけに執着し、忘れられていく自分の存在意義に悩む彼女の姿からは、観るものをぞっとさせるほどの人間らしさが滲みでている。
振り返れば、おもちゃたちはいつも、人間の弱さや不安を代弁してきた。
「ウッディは常に恐怖と不安を抱いてきました。例えば、『トイ・ストーリー』では新しいおもちゃの登場によって自分の仕事を失うのではないかという恐怖がありますし、『トイ・ストーリー2』では、自身が古いコレクターズアイテムだと知り、そこには明らかに時の流れがあるわけです。
そうした人間らしい感情を持っていることが、ウッディが、そして作品が長く愛されている理由だと思います」

監督によると、悲しい悪役ギャビー・ギャビーは、ウッディの「鏡の存在」として作られたのだという。
「ウッディがかつて、クローゼットに仕舞われて遊ばれなくなったように、彼女も16年間同じ店に放置されてきました。
最初は彼女を恐れていたウッディも、彼女が置かれた状況を理解するにつれて同情するようになります。彼女の中に、彼自身を投影するんです」
古くなり忘れられることは、おもちゃにとって致命的だ。その葛藤は、ウッディも痛いほどよくわかる。
そしてウッディがそうしたように、彼女もそれを乗り越えなければいけない。
おもちゃに飽き、忘れ、失くす。それがこどものあたりまえ
これまでにも、こどもがおもちゃに興味をなくしたり、うっかりどこかに失くしてしまうのは自然なこととして描かれてきた。
そもそもこどもは気に入らないおもちゃで遊ばないし、簡単に忘れたり壊したりする。残酷だが、こどもは完璧ではない。
「トイ・ストーリー4」には、そんな現実を突き付けるシーンが幾度も登場する。

「すべてのおもちゃがウッディのようにこどもに遊んでもらい、大切にされるわけではありませんから、現実味のある点ですよね」
ギャビー・ギャビーも、幸運ではなかった多くのおもちゃのひとつだ。彼女との出会いによって、ウッディは新たな目標を持つようになったと監督は言う。
「つまり、恵まれない他のおもちゃのため、自分に何ができるかを考えるようになるんです」
これまではアンディとウッディの美しい関係性がメインテーマだったが、今作はこどもとおもちゃの関係の多様性が強調されている。
持ち主を失っても、おもちゃの人生は続く
その中でも、公園のこどもたちと遊びながら自由に生きる、いわば「野良おもちゃ」となったボー・ピープの姿は、ウッディにとっても観客にとっても大きな驚きだ。
「トイ・ストーリー3」では姿を見せなかった、シリーズのヒロイン的存在ボー・ピープだが、今作ではその別れの秘密と奇跡的な再会が描かれる。
「ボー・ピープの帰還というアイディアは、企画の早い段階からありました。彼女を『持ち主の居ないおもちゃ』として再会させることで、ウッディの世界観を大きく揺さぶるだろうと思いついたんです。持ち主を失うのは、ウッディが何よりも恐れてきたことですから。
ウッディにとっては、外の世界で一体どうして生き延びられるんだ? となりますよね。特にボーはもともと電気スタンドの部品で、陶器でできているわけですし」
それまで、アンディやボニーの部屋で暮らしてきたウッディの視線は、外の広い世界に向けられるようになる。

「ボー・ピープはサバイバーとして、たくましく生きているんです。
そして、持ち主を失くすのは必ずしも恐れることではないと示してくれました。
彼女はとても賢くて、常にウッディの数歩先をいっている。新しい視点を与えてくれるキャラクターとしてこの物語において大きな意義を持ち、ウッディは彼女から多くを学ぶんです」
ウッディと一緒に、観客も大人になり、歳をとった。しかし結局のところ、「トイ・ストーリー」が大人向けの映画になってしまったわけではない。監督は次のように話した。

「『トイ・ストーリー』シリーズに限らず、ピクサー作品が目指しているのは、すべての人に語りかける作品です。なので、観客にとって、各々異なる価値を持つ物語になるよう意図しています。
小さな子どもたちは、冒険するおもちゃたちを見るのが楽しいかもしれないし、大人は、物語の別の側面から更に深い意味を見出すだろうと思います」
世界中のこどもたちがウッディと出会って24年。まだ誰も知らない「トイ・ストーリー」が語られる。
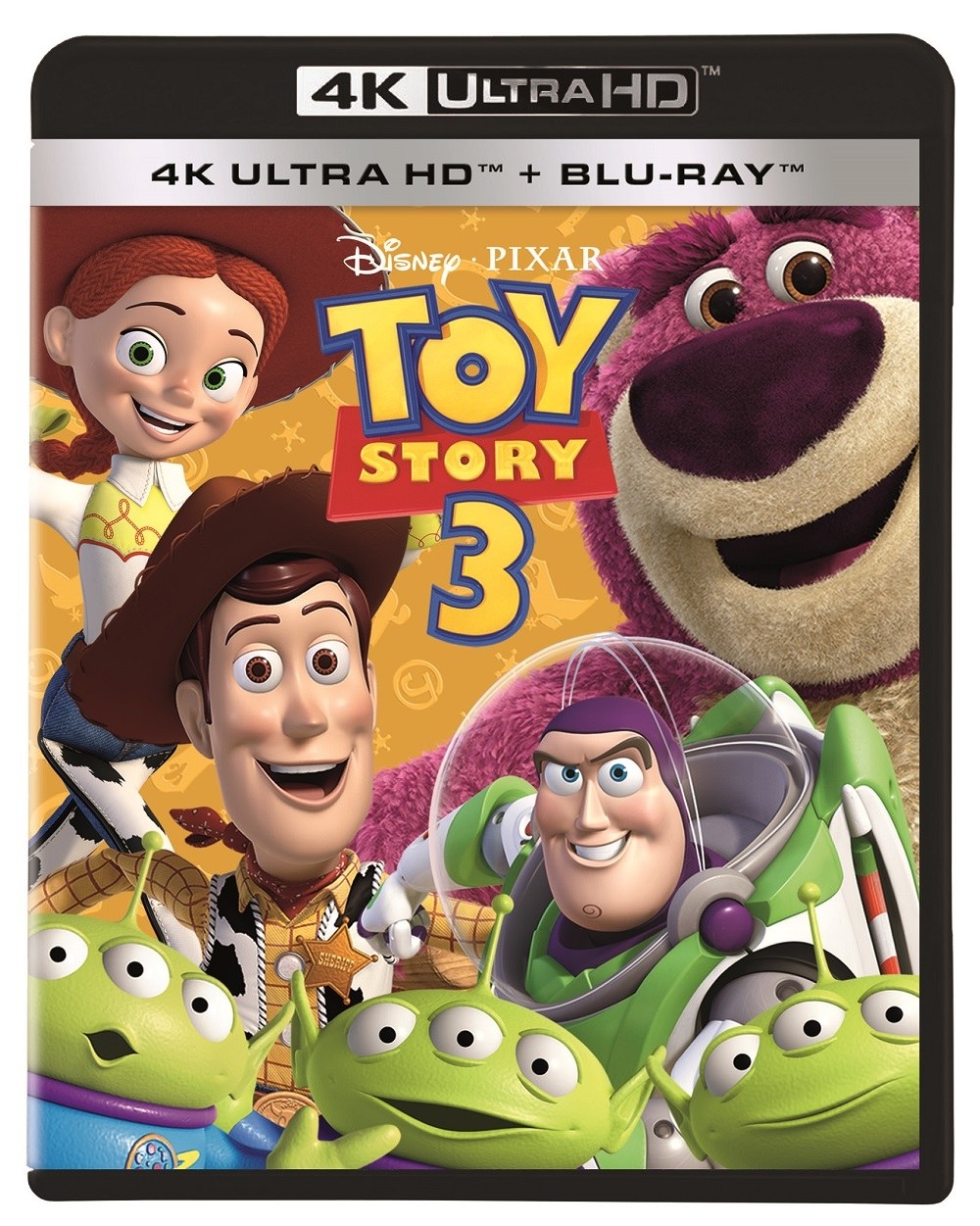
『トイ・ストーリー3』 ディズニー サマー・キャンペーン実施中 4K UHD、MovieNEX発売中、デジタル配信中 発売元:ウォルト・ディズニー・ジャパン
