お風呂の入りかた、見直してみない?
「お風呂に入っても逆に疲れてしまう」「すぐにのぼせてしまう」。そんな人は、入浴の仕方が適切ではないのかもしれません。
入浴法に関する本を複数出版しているバスクリンの石川泰弘さんに、オススメの入浴方法やお風呂の注意点についてききました。
1. 【シーン別】お風呂の入りかたのオススメを教えてください!

《平日、帰宅が遅く時間がない時》
「基本的には、忙しい日にも、短時間でいいのでお湯につかることをオススメします。
まず、お湯につかるだけで汚れはある程度とれます。バスタブにつかり、血行を良くし、体温を少し上げましょう。
これだけで、気持ちよく眠りにつくことができます。
もし難しければ、朝シャワーで汚れをしっかり落として、気分をリフレッシュしましょう」
《休日、時間をとってしっかりお風呂を楽しみたい時》
「ぬるめのお湯に身体を沈め、ゆったりとリラックスするのがオススメです。
また、ある程度の時間(15分以上)お湯に浸かることで血行が良くなります」
《とにかく体が疲れてしまった時》
「血行を良くすることと、体温をあげるために、10分程度の短時間の入浴を。
体温を上げすぎないことがポイントです」
《気分をリラックスさせて心身ともに休めたい時》
「湯温はぬるめ(心地良い温度)にして、全身浴でゆったりと浸かってください。
好きな色・香りの入浴剤を利用したり、灯りを少し落としてみるのも良いですね」
2. お湯の温度は熱めとぬるめ、どっちがいいの?

3. いつもシャワーで済ませてしまいます。湯船につかった方が良いですか?
「1980年代に朝シャンが流行してから、夜もシャワーだけで済ませる人が多くいらっしゃいます。
でも、汚れを落とし(つけ置き洗いを想像してください)、循環を良くすることを考えると、できればお湯につかる方が良いです」
4. 入浴剤って意味あるの?

5. 朝と夜のお風呂、どっちが正解?
「良質な睡眠をとることを考えれば、夜に入り、血行を良くし体温を上げるのがオススメです。
ちなみに、これはシャワーでは出来ません」
6. お風呂に長く浸かっていると気持ち悪くなってしまいます...
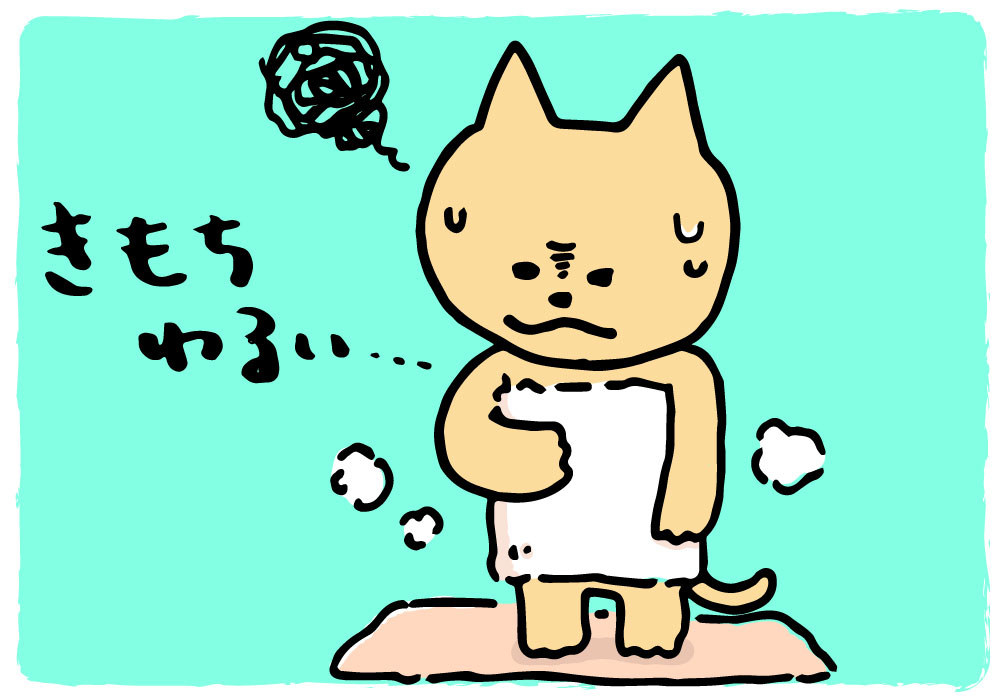
7. 寝る前にお風呂に入ると、身体が火照ってしまいます。どうにかなりませんか?
「お湯の温度が高いのかもしれません。 また、メントールなど清涼成分を配合した入浴剤を利用するという方法もあります。
ただ、汗をかける身体になっていることは、健康にとっては大切なことです」
8. サウナと水風呂を交互に繰り返すのが好きですが、注意点はありますか?
「まず、サウナ内では足下よりも頭部が温まりやすいので、のぼせないように気をつけましょう。
また、高温サウナに入ったあと、直ぐに水風呂に入ると血圧の変動が激しくなる可能性があるので、オススメしません。無理をせず楽しんでください」
9. お風呂でまったりお酒を飲むのは、やっぱりダメ?
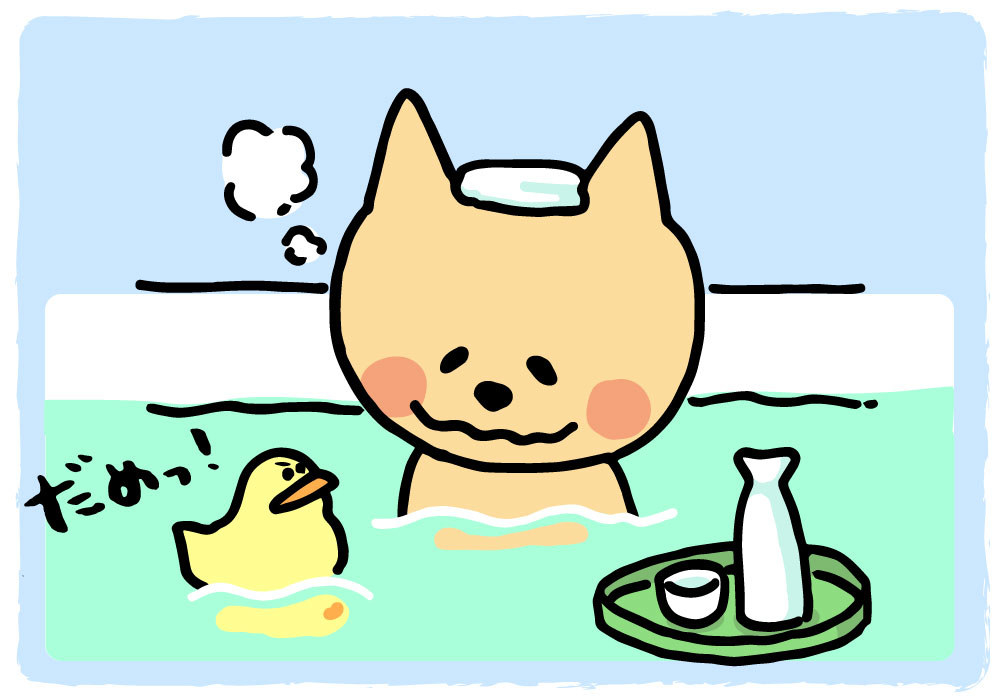
10. お風呂でだらだらとスマホをいじってしまいます。長風呂はの注意点はありますか?
「長く入ると汗もかきますから、入浴前・入浴中に水分をしっかりとることが重要です。
また、皮脂が必要以上に取れてしまい乾燥する可能性があります。その点を注意する必要があります」
今日はゆっくり、お風呂に癒されよう
忙しくていつもシャワーで済ましていた人も、休日に思いっきりリラックスしたい人も。自分にあった入浴方法でお風呂タイムを満喫できますように!


