なかなか知られていない「父親の産後のうつ」。
自分も育児を頑張ろうと願いながらも、「育児と仕事の両立」に苦しみ、潰れていく父親に社会の支援は薄い。
第3回目の今回は、産後にうつになった経験を、自ら発信しているライターの遠藤光太さん(32)に話を聞いた。

必要な支援や問題についても考えていく。
※この連載は、メディカルジャーナリズム勉強会の「ヘルスケア発信塾2021『伝え手』育成集中プログラム」で最優秀賞を受賞した作品に編集を加えたものです。
会社や妻は「休め」と言ってくれたのに… 受け入れられない自分
現在フリーランスのライターとして活動する遠藤さんは、1人目の子が生まれ5〜6ヶ月が経った頃、体調不良に見舞われた。朝体温を測ると34.6℃と異常に低く、頭痛・吐き気・めまい・胃痛などもあった。
内科を受診したところ、精神科受診を促され、そこで「抑うつ状態」との診断を受けた。
23歳で結婚し、24歳で妻の出産を迎えた遠藤さんは、今の時代でいえば「若い父親」だった。当時は会社員で、勤め先の新規プロジェクトで色々頑張りたいと思っていたのに重ね、初めての子の出産もあり、思い切りアクセルを踏んだ時の出来事だった。

当時は診断されていなかったが、自身の発達障害もあり、特性と合わない業務に自ら志願してしまった負担もあった、と振り返る。
会社側は理解があり、むしろ休職の際には会社や産業医に、「1ヶ月でいいから休んだ方が良い」と言われていた。それでも「とにかく早く復帰したい」「社会人2年目でこんなのではだめだ」と焦り続けていた。
保育士の妻も理解し、「今は休んでいていい」と言ってくれたのに、自分自身が一番、休むことを受け入れられなかったという。
結果として、状態は良くなったり悪くなったりし、むしろ回復には時間がかかってしまう。
「本当は共働きだし、給与を無理にあげようとしなくても大丈夫だったんです。でも子どもが産まれ、不安で色々空回りしてしまっていました」と遠藤さんは振り返る。
彼の中には「父親なんだから頑張らないと」「こんなんでは父親としてだめだ」という意識が常にあった。
育児を頑張りたい父親を追い詰める「有害な男らしさ」
遠藤さんは産後のうつの根底に、「有害な男らしさ」が強く存在したと考えている。
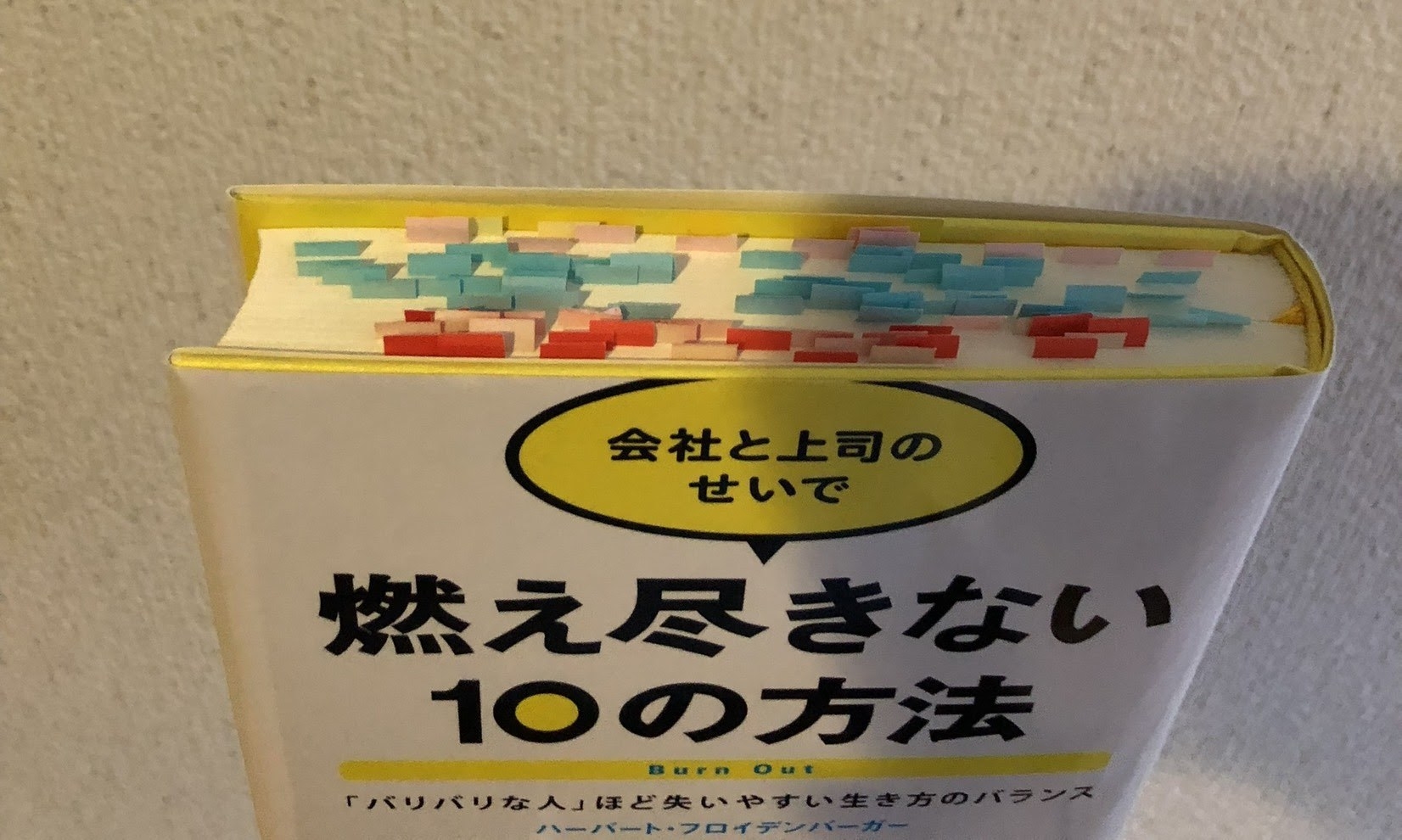
「有害な男らしさ」とは、「男性だからかくあるべき」といった固定概念のことだ。父親としての例を挙げるならば、「家族の為に頑張って働き、稼がなくてはならない」などといった意識を指す。
米国の研究(1)で、このような意識を保つ男性は、自殺率が2.5倍高いという事実が示されており、メンタルヘルスとの関連も指摘されている。
実際に子どもが生まれた時の気持ちは、「嬉しい、頑張らねば」だった。収入面では「より給料を上げねば」、感情面でも「父親として頑張らねば」という意識があった。
「育児もしたい」と思い、そこも頑張ろうとしていた。今思えば、理想と現実がかけ離れてしまっていたのだろう。
令和の今、男性も子育てをするのはスタンダードになりつつあるのは事実だ。そして、社会の男女の役割分担に関する意識は大きく変化している。
かつては「男は仕事、女は家庭」という文化があったからこそ、「有害な男らしさ」も当たり前に存在できた。でも、今の時代での「有害な男らしさ」は、むしろ育児に関わりたい父親を追い詰めてしまっている。
子育てにも悪影響を与える「有害な男らしさ」
この「有害な男らしさ」は父親を追い込むだけではなく、子育てにおいても悪影響がある、これを「二重の罠」だと遠藤さんは語る。
子育てを「タスク(やるべき仕事)」と見なし、目標設定してそれを達成する——。男性が社会で働く中で慣れてきた、そんな意識で子育てに取り組むことが良い、と語られることがある。この考え方に遠藤さんは疑問を投げかける。

「今日は何回おむつを替えることができた、とか、朝、何時に起きてミルクをあげられた、のように、あらかじめ目標を設定して、その達成に価値を置くのはどうなのでしょうか。自分はどこまで達成できているのか、周りと比較したりすることで追い込まれている父親もいると思います」
「それぞれの夫婦できちんと相談して、受動的に子どもをケアしていくことで十分、子育ては上手くいきます」
子どもを見守り、気づいた時にミルクやおむつ替えをやる。これを「受動的なケア」と彼は表現する。遠藤さんの妻は保育士だが、職業柄もあり、同じ考え方であるという。
「有害な男らしさ」を支える「有害な女らしさ」も
最近、遠藤さん夫婦は二人目の子どもを迎えた。
遠藤さんは久々に「新生児の育児」をしているが、まだ男性の育児をめぐる社会の状況は変わっていない。
例えばベビー用品のパッケージの写真や絵柄は、ほとんどが母親。父親は出てこない。出てくるとすると、「これを使えば父親でも育児ができる!」の様な消極的な文脈だと指摘する。
遠藤さんが予防接種などに連れていくと、奇異な視線を感じる事もあるという。保育園の面談に2人で行くと、面接担当者は妻ばかり見て話すこともある。
「有害な男らしさ」もあるが、まだまだ日本には「家事や育児は女性がやるもの」「育児関係の広告対象も女性が中心」といった「有害な女らしさ」も健在だ。
「アンコンシャス・バイアス」=「無意識の思い込みや偏見がある」という概念が少しずつ広まり、変わりつつあるが、それに苦しめられている人もまだまだ多くいる。
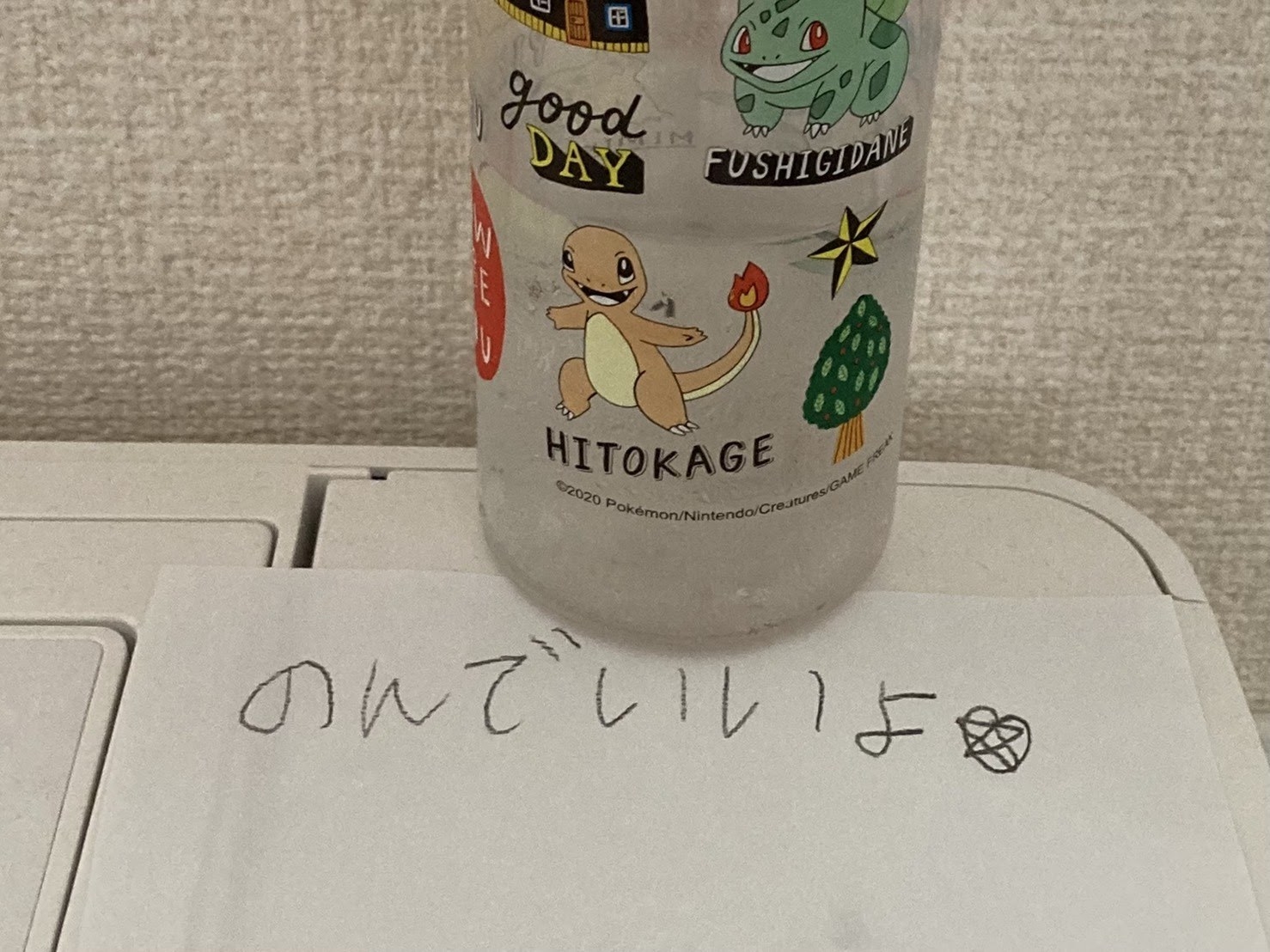
社会的支援も不十分だ。
遠藤さんがうつになったのは、8年前。当時、「父親の産後のうつ」という概念すらなく、「双極性障害」と診断されたという。
行政の支援員や医師も、「父親のうつ」には理解がなかった。前回の竹原氏も指摘していたが、そんな父親を支える医療職の養成も急務だろう。
どうする?男性の育児への理解不足
3回の連載を通じ、当事者・専門家双方の話を聞いたが、共通する問題は「周囲の理解不足」だったように思う。単に理解がないという話ではなく、文化背景や、無意識の部分で、まだまだ「父親の育児」が日本社会に浸透しているとは言えない。
育児情報は未だに母親向けがほとんどで、父親に適切な習得機会があるとは言い難い。核家族化の進行に伴い、育児などを経験する機会は以前より減少している。そして支援する医療・行政側も、無意識に差別してしまっている事もある。
しかし、今年度から男性育休制度が整えられ始めることもあり、「男性が育児をする」という流れが後退する事はないだろう。
「男性も女性も、育児と仕事を両立する社会」の為には、男女双方が変わっていかなければならない。男性・父親の動きは女性・母親に比べて遅れてはいるが、着実に変化してきている。
男女関係なく「一人の親」として、育児に取り組める時代を実現するために、多くの方にこの問題を知っていただけたらと思う。
(終わり)
【参考文献】
1. Daniel C, William F, Zohn R. Association of High Traditional Masculinity and Risk of Suicide Death: Secondary Analysis of the Add Health Study, JAMA Psychiatry. 2020 Apr 1;77(4):435-437.
【平野 翔大(ひらの・しょうだい)】産婦人科医、産業医、医療ライター
1993年生まれ、医学部卒業後、初期研修・産婦人科専門研修を経て、現在はフリーランス医師として産婦人科・睡眠医療・産業保健に従事しつつ、複数のヘルスケアベンチャーにメンバーやアドバイザーとして参画。資格:健康経営アドバイザー・AFP(日本FP協会認定)・医療経営士3級(登録アドバイザー)。


