「怒り」の経済学
笑う門には福来たる。
情けは人のためならず(※人に親切にしておけば必ず、巡りめぐっていいことがあるという意味のほう)。
これが最近の経済学の研究である、といったら驚くだろうか。
行動経済学を一般向けに紹介してきた、大竹文雄さん(大阪大教授)の新刊『競争社会の歩き方』(中公新書)の意義は2点ある。
第一に経済学が明らかしてきた、あるいは明らかにしようとしている最新の知見が詰め込まれていること。明日からでもビジネスに使えそうな知見がある。
第二にタイトルにもあるように「競争」の意味について考察していること。こちらは、長期的にみて人生にとって重要な意味を持ってくる要素がある。
まず第一の観点からみていこう。
怒らせると損をする

最近の経済学は、これまで「経済学」と聞いてぱっとイメージすることと、ちょっと離れたことが研究対象になっている。
例えば感情だ。
私たちは、人が感情に左右されることを知っている。幸福感でいっぱいならやる気はでるし、なんとなくうまくいかず気分が乗らない日は成果も乏しい。
幸福度が高いと、生産性が高まることを裏付ける研究も進んでいる。大竹さんもいうように、まさに笑う門には福来たるだ。
一方で、感情を軽視すると、人の生産性を下げることにつながるという研究もある。
部下がいるビジネスパーソン必読
「怒り」に着目した研究結果が紹介されている。ここは部下をもつビジネスパーソンにとって、まず必読のパートだ。
怒りっぽい上司が怒っているときに、わざわざ話をしようと思う人はいない。「落ち着いたときに話をしようかな」とか「時間を置くか」と考える。
人間が完全に合理的なら、与えられた情報に基づく意思決定は、感情に左右されることはない。
しかし、現実の人間はそんなことはない。怒りっぽい上司に限らず、人は感情によって判断基準が変わる。
経済学でわかっているのは、人を怒らせると協力をしなくなるという事実だ。
公共財ゲームと呼ばれる経済実験で明らかになった。
このゲームは、参加する4人全員が、みんなで協力すれば一番大きな利得を得られるという設定になっている。
しかし、自分が協力しなくても、他の人が貢献したおこぼれにあずかることもできる(つまり、ただ乗りすることもできる)し、他の人が協力しないなら自分も協力しないほうが得になる。
一番の利得を得られるなら、みんなで協力を目指すことが合理的だと思うだろう。ここで注目されるのが「怒り」だ。
怒った被験者は、協力行動をとらずに結果的に損をする傾向にあるという。
人は怒ってしまうと、利益があがる場合でも、協力行動をとらない。合理的に考えればみんなで協力しあうほうが得なのに、だ。
一方で怒っている人はリスクをとりやすくなるという実験結果もある。
ビジネスではリスクを回避するだけでなく、リスクをとるべき局面もある。リスクをとるかどうか、判断を迫られたときに怒りは有効に作用する可能性がある。
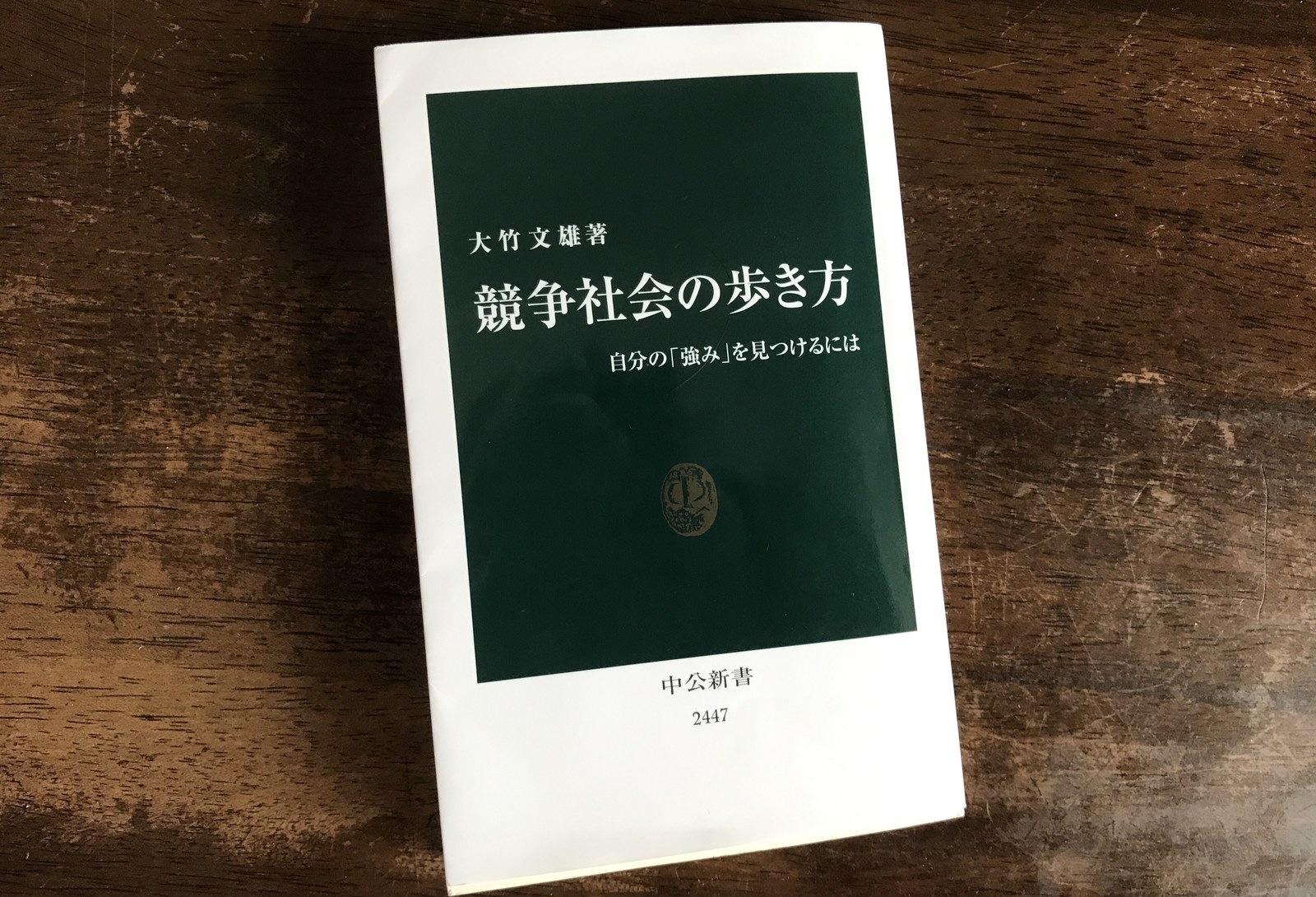
怒りの功罪を知ること
「怒り」の功罪を知っておくことは、職場の生産性を上げるためにも必要なことだ。大竹さんはこう指摘する。
特に職場では、同僚を怒らせないようにしないと、協力が得られず、職場の生産性が落ちてしまう可能性がある。部下をもった人は知っておくべきことだろう。(『競争社会の歩き方』)
上司の意図がどうあれ、部下が怒ってしまうと、協力は得られず、結果として全体のパフォーマンスを下げてしまう。
怒ってしまうと協力が得られず、重要な場面では生産性が落ちてしまうし、合理的ではない意思決定をしがちである。一方で、力仕事やリスクをとるべき時には怒りの感情は有効になる。(『競争社会の歩き方』)
怒りという感情への対処を知れば、ビジネスは円滑に進むことがわかる。
体験的なビジネス論を読むより、経済学の知見を身につけたほうが損をしにくくなるのではなかろうか。
競争はなぜ必要なのか?

この本は最新の研究成果を紹介しているだけではない。
これが第二の意義だ。
貫くテーマは「競争」とは何か、競争はなぜ必要なのか、である。
「競争」というと、ネガティブな印象を持ってしまう人がいる。いわく勝ち組と負け組みをわける、いわく競争に勝つためなら手段を選ばない人ばかりーーといったイメージがついて回る。
しかし、それは違うというのが、この本に込められた大竹さんのメッセージだ。
競争を否定した教育で、やられたらやり返す子供が育つ?
こんな研究結果が紹介されている。
競争より教育を重視する教育を受けた人たちは、なぜか人との協力に否定的で、やられたらやり返すという価値観になる傾向、所得の再分配にも否定的になる傾向にある。
競争はネガティブなものだから、みんなで協力をしようという価値観で教育を推し進めた結果、かえって非協力的な価値観が身についてしまうというのだ。
なぜか。
この本のなかで紹介されている教育社会学の議論でもあるように、反競争的な教育の裏に流れる価値観はこうだ。
「ほとんどの子供は100点を取れるような力を持っているはずであり、教育次第でほぼ全員で100点をとれる。これが正しい教育だ」
つまり、生まれ持った能力はみんなが同じであるという前提に立っている。
「みんなの能力が同じ」という思想が子供に伝わると、「能力が同じなのだから、所得が低い人は怠けているからだという発想を植えつけることにつながった可能性がある」
「つまり、能力が同じなら、助け合う必要もない、所得再分配も必要がない」となったのではないか、と大竹さんは考察する。
競争を否定した結果、助け合いに否定的な傾向が強まるとするなら、なんとも皮肉な結果だ。
競争の効果が描かれる『火花』

では、競争はなぜ必要なのか。それは自分の長所を見つけるためだ。
大竹さんの主張が端的にあらわれているのが、この本にも収録されている又吉直樹さんのベストセラー小説『火花』の書評だろう。
『火花』の主人公は売れないお笑い芸人だ。
現状からなんとか這い上がろうとする主人公と、究極の笑いを目指す先輩との関係を描いた青春小説というのが一般的な読み方だが、大竹さんはこれを経済学のエッセンスが詰まった小説だと位置付ける。
「競争」というテーマに絞って紹介する。
彼らは日々、面白い漫才を追い求め、他の芸人たちとの熾烈な競争を繰り広げ、常に市場にさらされている。
敗者は意味のない存在なのか?
市場の競争を勝ち抜き、華やかに売れていく芸人の陰には、膨大な数の売れなかった芸人がいる。
彼らはなんの意味もない敗者なのだろうか?
『火花』にこんなセリフがある。
(漫才を志す芸人が)「一組だけしかおらんかったら、絶対にそんな面白くなってないと思うで。だから、一回でも舞台に立った奴は絶対に必要やってん」(『火花』)
淘汰されたやつは無駄なのか、漫才の世界に競争がなかったら……という問いかけに対する答えが詰まっている言葉だ。
大竹さんは、このセリフから論を展開する。
競争社会で生きている私たちは、ある分野での競争で淘汰されると、別の分野への挑戦を続けていく。仮に、ある分野で淘汰されてしまったとしても、その挑戦自体は社会の無駄ではない。
勝ち残った人たちが社会により多く貢献するために不可欠な役割を果たしたのだから。(『競争社会の歩き方』)
競争で長所をみつけるということは……
競争は、少しでもいいものを生み出したいと思う気持ち、成長したいという思いを肯定する。
そして、競争のなかで、私たちは他の競争相手にはないもの、新しいものを目指そうと思う。
競争を通じて、長所を知るということは、短所を知るということでもある。
大きな目標のために自分だけではできないことがあると知るから、人は協力して目標に向かおうとする。
競争をすることと、協力しあうことの大切さは両立する。
そして、競争を勝ち抜くということは、同時に運にも恵まれた結果であるということも知る。
「もし、あのとき〜〜がなければ」いまの自分があっただろうかと思うこと。競争に敗れた相手がいるから、運に恵まれていたからーーいまの結果があると思うことで、他者に対する想像力も働く。
一見、浮世離れしていそうな経済学が教えてくれるのは、人間、そして社会を知ることの大切さである。
