厚労省が作った「人生会議」の啓発ポスターについて、議論が巻き起こっています。
このポスターの内容に疑問を抱く記事を書いたところ、賛否両論寄せられています。

この記事にご登場いただいた方々も筆者の私も、家族や医療者と自分が最後までどう生きたいかを話し合い続けることは大事だと考えています。
以下は、私が2018年12月に東京保険医協会の雑誌、月刊『診療研究』1月号に寄稿した記事「納得いく最期を迎えるために 家族、医療現場に求められること」に加筆修正した文章です。
ちょうど今回のテーマを、個人的な看取りの体験から考えた記事ですので、東京保険医協会の許可を得て転載します。
医療記者としての出発点は終末期のケアへの問い
私はインターネットメディア「バズフィードジャパン」で医療を担当する記者です。転職前は読売新聞で医療記者をし、辞める直前まで読売新聞の医療サイト「ヨミドクター」で編集長をしていました。
どちらの職場でも強い関心を持って取材してきたのが終末期の医療やケアです。
「ヨミドクター」では「さよならを言う前に〜終末期の医療とケアを考える」という終末期の医療やケアをテーマにした連載を続け、バズフィードに移ってからも終末期医療の記事を緩和ケアを専門とする先生方に繰り返し寄稿して頂いています。
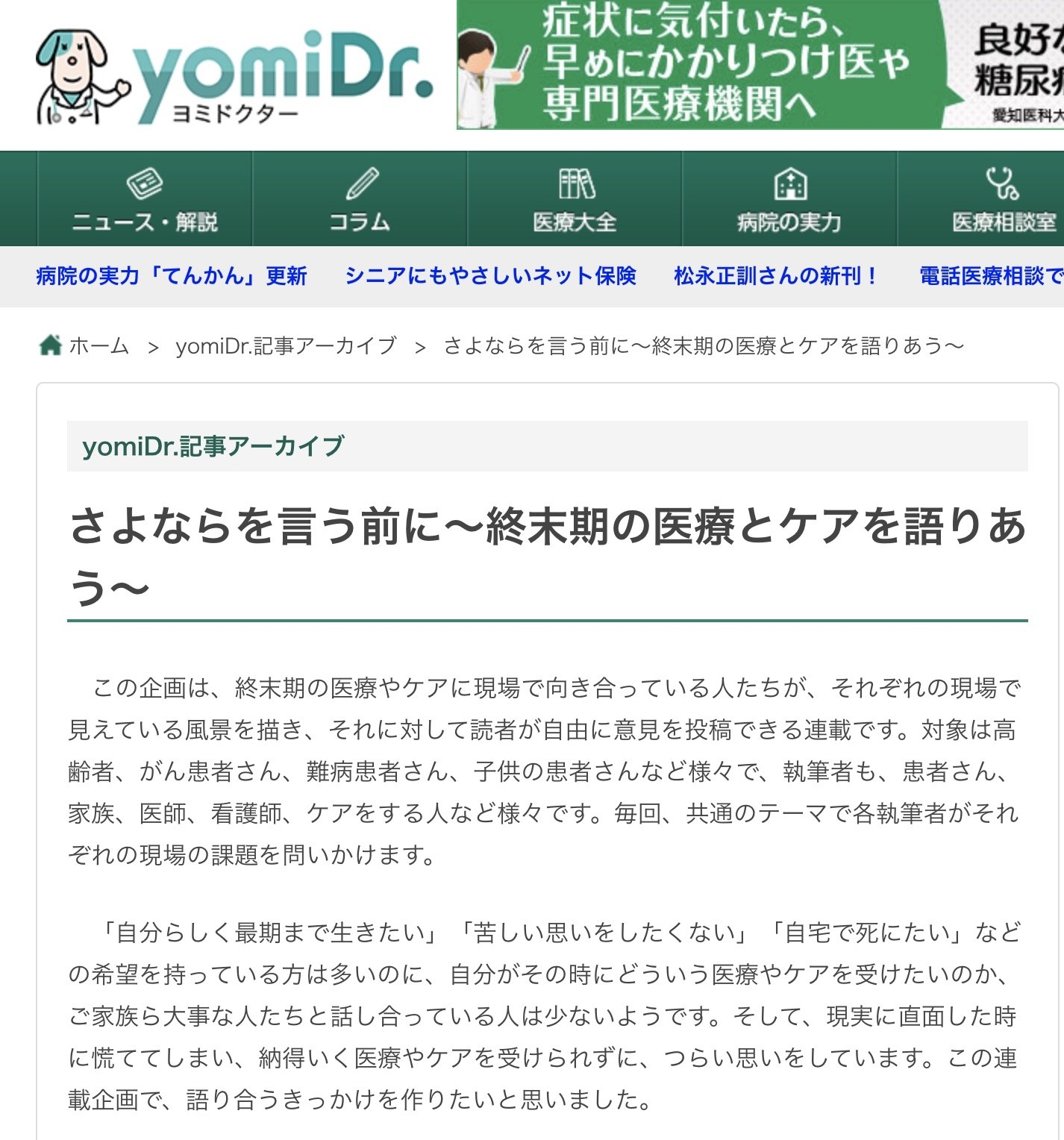
そもそも私が記者を志したのは、大学時代にホスピスでインタビュー調査をし、卒業論文を書いたのがきっかけです。大学生の時、父ががんになり、私は死への恐怖が頭から離れなくなっていました。
「死の苦しみに解決法はあるのだろうか?」
そんな問題意識から、死を前にした人や家族はどんな心身の痛みを感じ、医療者や周りの人はどんなケアができるのかを自分なりにまとめました。たくさんのホスピスや緩和ケアの本を読んでいましたが、自身の目や耳で受け取ったものはとても説得力を持って心に迫ります。
この問題をずっと追いかけたいと、当時、新聞社では唯一、医療の専門部署を持っていた読売新聞に就職したのです。
そして、記者になってから6年目の冬、父の看取りを私は経験しました。この経験から学んだことを中心に、納得いく死のために必要なことを考えてみたいと思います。
父の再発と看取りの経験
父のがんが再発したのは2004年の春のことです。私が大学生の時にステージ4の状態で見つかった父のがんは抗がん剤が劇的に効き、寛解状態が長く続いていました。「すっかり治った」と本人も家族も信じていた9年目の再発でした。
入院して抗がん剤治療を受けましたが、すでに全身に転移し、脳まで侵していたがんは、そのうち父から正常な意識も奪っていき、治療方針は、私たち家族が決めるようになっていきました。
いよいよ体調が悪化し、実験的な治療を勧める医師に対し、母はきっぱりと、「家に連れて帰って最期を過ごさせたい」と伝えました。
幸い、自宅近くに看取りも行う在宅医療や訪問看護も見つかり、在宅で看取ることを決めたのです。当時、警視庁担当として忙しく働いていた私もそのタイミングで介護休職をし、泊り込みで父の世話をすることにしました。
私たちは日常的に生き死にを語り合う家族だった
私たちは父が元気な頃から、どのように最後まで生きたいか、生き死にについて語り合う家族でした。
父は自身の父親や兄弟が皆、40〜50代でがんで亡くなっていたことから、「自分もがんで早死にする」と語り、母と共によく死や終末期医療の本を読んでいました。
「自分が死ぬ時は苦しいのは嫌だ。無意味な延命治療はするな。自宅で死にたい」と、常々私たちに言い聞かせていました。
それでも、いよいよ最終段階を迎えた時、父も私たちも動揺しました。
延命治療はしないと言っていたはずの父は、ギリギリまでほとんど効果も期待できないような抗がん剤治療を希望し、私たち家族はがんが父の意識を奪ってしまっても訪問医が静脈点滴をするのを止めませんでした。
やはり意識がなくても父は父です。生きていてほしいのです。何もしないで死に向かうのを見守ることが怖かったのでしょう。
しかし、無理に体に水分を入れた父は全身がむくみ、尾てい骨付近に大きな床ずれもできました。体位交換などの時に痛みに顔を歪め、訪問看護師がたんを吸引する時に苦しそうな顔をするのは家族にとってもつらい光景でした。
延命治療の停止 ベテラン看護師の家族に対するケア
そんなある日、父は右腕につけていた点滴の管を引きちぎりました。意識が朦朧とするせん妄状態だったのかもしれませんが、私たちは、それを父からの「無意味な延命治療はやめろ」という意思表示のように受け止めました。

点滴を中断することを伝えると、ベテランの訪問看護師さんは、「私もそれがお父さんにとって一番良いことだと思います。無理に水分を入れると陸の上で溺れたようになるので苦しいんですよ。お父様、今は楽になっているはずですよ」と説明してくれました。
私たちはほっとする思いでした。
看護師さんは、水分を含ませたスポンジで口の中を綺麗にし、渇きを和らげるケアも教えてくれました。最後まで父にしてあげられることがあるのは、家族にとっても救いです。
そして、今の状態やこれからの見通しを、私たちにわかりやすく伝えてくれました。呼吸が乱れ、血液中の酸素濃度が下がり始めた時も、「苦しそうに見えるかもしれませんが、麻薬物質に似たものが体内に出て、本人は楽になっているんですよ」と安心させてくれました。
亡くなる直前には下顎を上げるような下顎呼吸があることも教えてくれ、本人には苦痛がないことも伝えてくれました。
「そうなったらすぐに医療者を呼ばなくていいですよ。耳は最後まで聞こえると言いますから、いっぱい話しかけてあげてください。十分お見送りをして、落ち着いたら連絡をくださいね」と言ってくれました。
家族だけで穏やかに過ごせた別れの時
2004年11月1日の早朝、私が見守っていた時に下顎呼吸が始まり、私は交代で睡眠を取っていた母を起こしにいきました。別れの時だとはわかっていましたが、なぜか気持ちは落ち着いていました。
家族だけで思う存分、父への感謝の言葉を伝え、最後の一呼吸をするのを見届けました。母は涙をこぼしながらも、「こんなに穏やかな気持ちで見送れるとは思わなかった」と言いました。
ゆっくり家族で過ごした後に連絡を取り、訪問してくれたその看護師さんは「一緒に体を綺麗にしましょう」と共に体を拭かせてくれました。
生きている人にするように、動作ごとに父に声をかけ、床ずれには薬を塗って、ガーゼも清潔なものに替えてくれました。「お気に入りの服を着させてあげましょう」と一緒に私が誕生日にプレゼントした服を着せてくれました。
それは大事な人を亡くしたばかりの家族にとって、最上のグリーフケア(悲嘆のケア)だったように思います。
元気なうちの話し合いが父の望みを実現させた
振り返ると、父も家族もいざとなると慌てたのですが、父が元気な時から繰り返し、「苦しいのや痛いのは嫌だ。無意味な延命治療はするな。自宅で死にたい」と言ってくれていたおかげで軌道修正できたのだと思います。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題を間近に控えた今、元気なうちに家族や医療者とどのような医療やケアを受けたいか話し合っておく「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の必要性が叫ばれています。
つい先日は、これを各家庭で促すために「人生会議」という愛称も発表されました。
元気なうちに、自分は終末期にどうしたいのかを身近な人と語り合っておくことは、納得いく最期を迎えるために必要なことの一つだと思います。
方針を迷ううちに、「精一杯のことをしてあげてください」「先生にお任せします」と医師に告げ、なし崩し的に延命治療が開始され、中止するきっかけもつかめないのは日本ではよく見慣れた光景です。
自分のことであれば「無意味な延命治療はやめてほしい」と思っても、家族のこととなれば、本人の意思がわからない状態で治療しない決断をするのは勇気がいります。一度始めた延命治療を止めることは、自分が家族の死に手を下すような気がしてなおさら難しいでしょう。
父が点滴を引きちぎった時、もし事前に本人の意思を聞いていなければ、つなぎ直してくれとお願いしていたかもしれません。しかし、希望を聞いていたおかげで、「父が望んでいたことです」と医療者に伝えることができました。
しかも家族は全員一致していました。離れたところに住む家族が死ぬ間際に来て反対するという「遠くの親戚問題」もよく聞きますが、何せ父は母や私たち姉妹はもちろん、葬儀などで田舎に帰る度に親戚にもしょっちゅうこの希望を話していたのです。
紙の記録として残すことも大事ですが、家族や親戚など周囲の人の「記憶に残す」ように、葬儀など家族や親戚が死に向き合うチャンスの時に、互いの希望を語り合っておくことは合意を形成するために大事なのではないかと思います。
医療に求められること チーム医療と柔軟な対応を
在宅での看取りを希望した私たちにとっては、自宅近くに在宅で看取りを行う訪問医や訪問看護師がいたことは幸運なことでした。こうした医療資源が身近にないために、希望を断念する人も多いことはご存じの通りです。
さらに、医療者が病状の進行に従って、今後の見通しを伝えることで家族に心の準備をさせ、家族の気持ちが楽になるような言葉で病状やケアの方法を教えてくれたのはとても救いになりました。私たちの場合はベテラン看護師がその役割を担ってくれました。
確かに緩和ケアに習熟した医師がいることは、患者や家族の大きな支えとなります。ただ、積極的な治療を施すことが少なくなる終末期では、患者や家族にとって医師以外の専門職の存在がとても大きくなってきます。

看護師は患者の生活や家族関係を把握して、その人の生き方に合わせたケアを提案する専門性があります。なんとか栄養を取らせたいと願う家族にとって栄養士の具体的な提案は大きな力になるでしょう。父は当時、介護保険が使えない年齢だったため、医療ソーシャルワーカーが様々な制度の情報を集めてくれました。
それに加えて、医療者が、患者や家族のその時その時の思いを汲み取ってくれる柔軟性があるかどうかが、納得の看取りには必要です。
人の心は揺らぎます。父の場合、最終的には抗がん剤も点滴も中止しましたが、その気持ちが固まる前に、「延命治療はしない」という元気な頃の希望を優先していたら、後悔が残ったかもしれません。
取りきれない苦痛に対し、眠らせて穏やかに最期を迎えさせる「鎮静」も、医師個人の「信念」によって施されないことがあると聞きます。苦痛が取りきれない人が3割程度おり、日本緩和医療学会のガイドラインにも示されているからには、患者や家族にその選択肢は提示されてほしい。
医療者には患者や家族の思いに沿った柔軟な対応をとっていただくよう望みます。
納得いく看取りはその後を生きていく家族を支える
家族ら身近な人たちで元気なうちから終末期に望むことを話し合っておくことは大事で、それを支える医療チームの柔軟な対応が必要だとも書きました。
もちろん、患者や家族の希望や病状の進行は様々で、医療資源にも地域差があり、希望を示していたからといって必ずしも思い通りの最期を迎えられるわけではないと思います。
しかし、どんなに危機的な状況に陥ったとしても、その都度、医療者が患者や家族の思いに耳を傾け、その気持ちに沿う形でケアをしてくれれば、納得をすることはできるのではないかと思うのです。
そして、納得いく死を迎えられたかどうかは、大事な人を亡くした後に家族が前を向いて生きられるかどうかにも関わってくるはずです。
私は父から教わったことを胸に、多くの人が納得いく最期を迎えられるように終末期医療やケアの報道を続けたいと思っています。

