HIV感染(※)を告げなかったことを理由に、病院の採用内定を取り消されたのは不当だとして、社会福祉士の30代の男性が病院を経営する社会福祉法人「北海道社会事業協会」(札幌市)を相手取り、慰謝料など約330万円を求めて裁判を起こしています。

6月11日に札幌地裁であった本人尋問で、病院側の代理人弁護士が、「感染は嫌だというのは差別なのか」「医者には自分の身を守る自由がないのか」「100%感染しないと言えるか」と、HIVに関して知識不足の質問を繰り返して、裁判官に制止される場面がありました。
HIVは非常に感染力が弱く、治療薬の進歩で、治療しながら普通に生活し、働ける時代になっています。
病院側の発言の何が問題だったのか、整理してみましょう。
※HIV(ヒト免疫不全ウイルス)。現時点ではウイルスを排除することはできないが、治療薬を飲み続ければ寿命を全うできる。治療をせずに、ウイルスが体内で増殖し、免疫が落ちることでニューモシスチス肺炎など23の病気を発症した状態をエイズ(後天性免疫不全症候群)という。
1.HIVはそもそも感染力が非常に弱い
HIVは、そもそも感染力が非常に弱いウイルスとして知られています。
針刺し事故で感染者の血液が体内に入ったとしても、感染する確率は0.3%とされています。
同様の針刺し事故で、日本人で130万人〜150万人感染者がいると推定される「B型肝炎ウイルス」の感染率は約30%、100万人程度感染者がいるとされる「C型肝炎ウイルス」の感染率は約3%です。
このウイルスが多く存在するのは、血液や精液、膣分泌液、母乳などの体液のため、主な感染ルートは、「性交渉」「血液感染」「母子感染」です。
この男性は、ソーシャルワーカーとしての採用だったと言い、患者の相談業務を行うのに、院内でこうした行為をすることは考えられないでしょう。医療従事者や介護従事者でもHIV に感染して病院で働いている人はたくさんいます。

この男性は現在、別の病院で働いています。
さらに、代理人弁護士の須田布美子氏によるとこの男性は抗ウイルス薬を飲み続け、ウイルス量は検査で検出限界以下に抑え続けられています。このことは、裁判でも明らかにされています。
治療を続けてウイルスが検出限界以下に抑えられていれば、たとえコンドームなしで性行為をしたとしても、感染しにくいことが「PARTNER研究」と呼ばれる研究によっても明らかにされています。
もともと非常に感染率が低いウイルスを、しかも検出限界以下までコントロールしている男性による感染を恐れる必要は、医学的には全くないのです。
2.医療機関はそもそも知らずに感染している人がいることを前提に診療しないといけない
自分が感染症に感染しているかどうかは、検査を受けなければわかりません。
厚生労働省エイズ動向委員会の「2017年エイズ発生動向」によると、2017年に新たに報告されたHIV感染者1389人のうち、既にエイズを発症していた人は413人で、約3割を占めています。
HIV感染の段階では自覚症状が必ずしもあるわけではないので、知らずに感染して、症状が進行する人も一定程度いるのです。
それは医療機関でも同じことが言えます。
医療機関は、知らずに感染している人が受診することを前提に、診療に当たらなければ、感染する可能性があります。
HIVどころか、1で書いたように、もっと感染力の高いB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスにさらされる可能性を前提に、感染予防をするのが医療機関では常識です。感染が明らかになっている人を排除したらリスクなしと考えるのは非科学的な態度です。
HIVも含め、一般的な感染症に対し、全ての医療従事者や介護従事者が日常的に取るべき感染予防策は、「スタンダードプリコーション(標準感染予防策)」で十分だとされています。
つまり、医療機関で通常守るべき感染予防策を行っていれば、HIVをことさら恐れる必要はないのです。
3.国のガイドラインでもHIV を理由に職場で差別しないよう求めている
厚生労働省(当時は労働省)は1995年2月に、「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(2010年に一部改正)を定め、HIV感染によって差別することのないように求めています。
そして、冒頭でこのように書いています。
労働者に対し、HIVが日常の職場生活では感染しないことを周知徹底し、職場において同僚の労働者等の科学的に根拠のない恐怖や誤解、偏見による差別や混乱が生じることを防止するとともに、感染者やエイズ患者が、仕事への適性に応じて働き続けることができるようにする必要がある。
医療機関については、「感染の防止について、別途配慮が必要であるところ、医療機関等における院内感染対策等については、『医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き(案)』等が作成されていることから、これらを参考にして適切に対応することが望ましい」
とありますが、この手引きも、通常の感染予防策をとるように求めている内容であり、感染者を職場から排除するように求めている文言はありません。
病院側の対応は国が示している方針とも異なっている可能性が高いと言えます。
それぞれの弁護士はどう考える?
今回のやりとりについて、病院側の代理人で、冒頭の質問をした小竹真喜弁護士に発言の意図について尋ねると、そのような言葉を言ったことは認め、病院とは事前に質問内容については相談していなかったことを明かしました。
その上で、「私たちの主張は裁判所の証拠資料として全て提出しているので、それを見ていただきたいとしか言えません」と詳しい説明は避けました。
一方、男性の代理人弁護士の須田布美子氏は、「原告が現在通っている病院では、日常業務で感染可能性はないことを診断書と共に提出してくれるなど非常に協力的です。HIVについて最低限の知識があれば、そういう対応になるはずです。勉強していただきたいと思います」と話しています。
感染症に詳しい専門医の見解は?
HIVに詳しい感染症専門医は今回の問題をどう考えるのでしょうか。
神戸大学病院感染症内科教授の岩田健太郎さんが以下のコメントを寄せてくださいました。
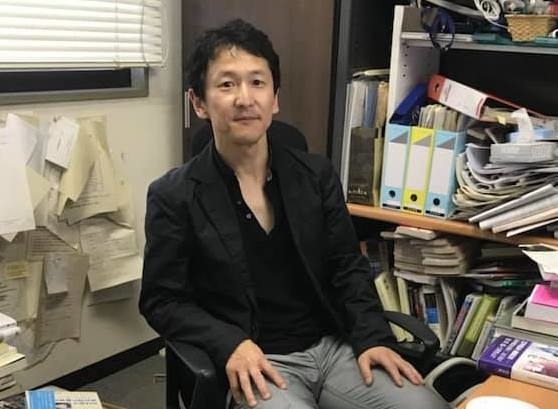
誠に情けない話だ。「恥を知れ」と言いたい。
1980年代前半、エイズの原因も感染経路も不明確だった時代には多くの医療者は恐怖におののきながら患者に対応した。ぼくの感染症の師匠、ダナ・ミルドバンもその一人で、彼女はニューヨークで発病し、死亡していくエイズ患者のケアを、「自らも感染者となる可能性」を飲み込みながら行なっていたのだ。
このような体験はぼくにはない。
HIVの感染経路は90年代頭には明らかになり、患者を診察する医師の感染リスクは非常に小さいことが分かっていたからだ。現在も毎週HIV感染者を外来で診察しているが、感染リスクに慄く必要もなく、ぼくは素手で患者をみている。先人の勇気と努力のおかげである。
ところが、21世紀の令和の時代になっても日本ではHIV、エイズというとまるで化け物でも見るようなパニックに陥る人が少なくない。一般の方ならまだ理解できなくもない。無知だからだ。
しかし、医療、医学のプロである病院や病院長たちがこのような思考停止に陥るとは言語道断である。はっきり言おう。こういう人たちは医者である資格はない。医者でいるにはあまりに偏見が強く、狭量で、かつ無知無学で不勉強だ。
毎年1000人以上の新しいHIV感染者が日本では発生している。治療が劇的に進歩し、HIV感染はかつてのような「死の病」ではなく、天寿を全うできる感染症となっている。新規感染者はコンスタントに発生し、患者は死なない。
このことは、HIV感染者総数が毎年純増することを意味している。HIV感染は基本的に性感染症であり、そのことは、多くの感染者が比較的若くて就労可能なことを意味する。
医療機関こそが、理不尽な偏見を廃すためにリーダーシップを取り、積極的に彼らの就労を支援しなくてはならないのに、感染が怖いから雇用しないとは何事であろうか。報道されるコメントには腹わたが煮え繰り返る思いである。
医療機関や医療従事者は、病気に関する偏見を持たず、社会にも正しい知識を啓発していく責任があるはずです。

