
はじまりは、7月上旬にかかってきた1本の電話だった。40代半ばの男性が、動揺した様子でBuzzFeed Newsに電話をかけてきた。男性は緊迫した不安げな声で、ついさっき、公衆トイレ内で同性と性的行為をしていたら警察に捕まったと話した。
男性は早口で経緯を説明した。それによれば、男性はロンドンのリバプール・ストリート駅のトイレで警官に取り押さえられ、駅内を引きまわされ、名前と住所をきかれ、尋問されたという。そして、また同じ場所にいたら逮捕する、そうなったら性犯罪者名簿に登録せざるをえないかもしれないと警告された、と。ここでは、この男性をティムと呼ぶことにする。
公衆トイレでの男性同士の性的行為と聞くと、まるで1950年代の白黒映像の一場面のようであり、同性愛が犯罪ではなくなってから50年が経ったいまも広く行われている行為だとは思えない人もいるかもしれない。だが、これはけっしてティムに限った話ではないし、彼と同じように警察に尋問されるのも珍しいことではない。
ティムの電話は予期せぬ結果につながった。2017年のいまではもう当然解決しているはずだと一般に思われている多くの問題と、これまでけっして答えられることのなかった多くの疑問があらわになったのだ。
同性愛者向け出会い系アプリ「グラインダー(Grindr)」や出会い系サイトが発達し、同性愛者の解放が進んでいるとされるこの時代に、いったいなぜ、男性たちはいまだにセックスを求めて公衆トイレへ行くのだろうか? その行為を、LGBTコミュニティとの関係を損なわずに取り締まるには、いったいどうすればいいのだろうか? 現行法は、その目的にかなっているだろうか? そして、社会全体のためになるように法律を適用するには、どうすればいいのだろうか?
こうした疑問は、警察(リバプール・ストリート駅の場合は、イギリス鉄道警察)の人員配分の難しさも浮き彫りにしている。テロの恐怖への対応に多くの人手が必要な21世紀では、人員の配分は大きな問題だ。さらには、無実の人のプライバシーを侵害しないで「トイレに行く一般人」を警察が監視することなどできるのか、という問題もある。
ティムから電話をもらってから、BuzzFeed Newsは数週間にわたり、公衆トイレで同性と性的行為をした経験のある人たちから話を聞いた。そのなかの1人は、世間的にも名の知れた人だ。なお、イギリスでは、セックス目的で使われる男性用トイレは「コテージ(cottage)」と呼ばれるが、アメリカでは「ティールーム(tearoom)」とも呼ばれる。オーストラリアでは「ビート(beat)」と呼ばれている。
この取材で明らかになったのは、一見したところよりもはるかに深く、はるかに複雑で、はるかに謎めいたパラレルワールドだ。それは、因習から解放された人たちの世界であると同時に、同性愛者であることを隠している人たちの世界だ。政治家やセレブリティが、ごく普通の人たちに溶けこむ世界でもある。そこでは、自己発見と現実逃避が、薬物依存や虐待、性暴力と混ざり合っている。
なかには、まだ少年だったころに、セックスを求めて公衆トイレに行くようになった人もいる。
そんなわけで、公衆トイレの形づくる風景には、いくつかの顔がある。ある人にとってそれは、自分の外側にある影だ。別の人にとっては、息のできない人生のなかで、時おり一気に供給される酸素だ。そして、そのほかの人たちにとっては、きれいに取り繕った異性愛的生活の拘束から解放された、喜びにあふれ、ときに反抗的でさえある欲望の爆発だ。
公衆トイレでの性的行為という限られた世界の調査として始まったこの探究はやがて、予想もしなかった広い領域を明らかにした。多くのゲイやバイセクシュアルの男性にとって、内心の世界はほとんど変わっていないこと、同性愛嫌悪の文化が児童の性的虐待を助長していること、そして、公衆トイレでの性的行為への対応が万人に影響を及ぼすことまでが明らかになったのだ。
その一方で、この行為は、批判と恥辱に取り巻かれている。そうした批判の声は、あらゆるコミュニティからあがっている。なぜそんなことをしなければならないの? 気持ちが悪い。汚らしい。
ここで明かされるひとりひとりの男性の物語では、そうした批判に対する反応が、渦を巻いて溶け合っている。驚くほど破壊的なやり方で、互いに共鳴していることも珍しくない。
どれひとつとして、単純な話ではない。
リバプール・ストリート駅のトイレへ続く階段を下っていたティムは、8人ほどの男性が小便器の前に立ち、まっすぐに前方の壁を見ながら自慰をしているのを目にしたという。顔を見合わせたのは、ティムともう1人だけだった。互いの体には触らなかった。そして、警官が入ってきたのにも気づかなかった。
「ちょうどイキそうになっていたときに、警官が現れた」とティムは話す。警官は3人だった。
ティムはがっしりした体型で、タトゥーを入れている。顔には深い笑いじわが刻まれ、非常に表情豊かに話をする。まるで、ひとつひとつの言葉の感触を、声の調子によって現出させようとしているかのようだ。ティムには二度にわたって話を聞いた。
「警官たちは、『一緒に来てもらえるか?』と言った。私たちは上の階へ連れて行かれて、『おまえたちのしていたことが、違法行為だというのは知っているか?』と訊かれた。そのあと、駅のなかを歩かされた」
その途中、警官の1人が立ち止まり、4人目の警官と話をしたという。「彼は相手の耳元で囁いた。相手が『おお、よくやった』と言ったのを覚えている」
警官たちはティムともうひとりの男性を、駅のタクシー乗り場の近くに座らせた。「騒擾(そうじょう)取締法を読み聞かされた。だいたいは子どもに関する話になった。『子どもが入ってきたらどうするんだ? あんなことをしたら性犯罪者名簿に載る可能性があるってことはわかっているのか?』警官は私たちを怖がらせようとしていた」
警官のひとりに名前と住所を訊ねられ、前科について質問をされたあと、別の警官から細かい尋問を受けた。戻る途中、警官は「警告だけで釈放するが、また同じことをしたときに備えて記録を残しておくため、写真を撮っておく」と言ったという。
ティムはそう聞いて混乱した。写真を撮る理由がわからず、単なる脅しの策なのではないかと思った。また、自分たちの詳しい情報がどこに保管されるのか、何が記録されるのか、情報はいつまで保持されるのか、といったことも説明されなかったという。そのあと、男性たちは釈放された。

この経験はティムを動揺させた。「きまりが悪く、恥ずかしかった」とティムは言う。近年では、公衆トイレでの性的行為への対応策に関して、警察の公式声明は出されていない。そのため、あれが市民の苦情に対応した一度限りのことだったのか、もっと大がかりな取り締まりの一環なのか、ティムには見当がつかない。テロ対策というもっと緊迫した懸念事項があることを考えれば、公衆トイレでの性的行為を優先して取り締まるのは間違いではないか、とティムは言う。
ティムが捕まる数か月前に、別の男性も、イギリス鉄道警察に捕まっていた。彼をアンドリューと呼ぶことにしよう。
アンドリューはそのとき、別の男性と並んで小便器の前に立っていたという。ふたりとも、自分の手で自分の性器を持っていた。アンドリューが隣の男性をちらりと見たとき、大きな声が聞こえた。
「警官がシンクのところにいた。『おまえら!見たぞ!ふたりとも、一緒に来い。逃げようとしたら逮捕するぞ』と言われた。警官たちは、小便器をのぞきこんでいた」
アンドリューによれば、制服を着た警官2人によって上の階に連行され、なぜここへ連れてこられたかわかるかと訊かれたという。アンドリューはそのとき、警官たちがカメラを身に着けているのに気づいた。制服に取り付ける小型デバイスで、イギリス鉄道警察が「身体装着ビデオ(BWV)」と呼んでいるカメラだ。
その後、ティムの話とほぼ同じ過程を経て釈放されたアンドリューは、カメラが回っていたのではないか、トイレで自分の姿が撮影されていたのではないかと心配しながら、その場を離れた。警察はそれについて言及しなかったという。
アンドリューによれば、自分のしていたことを認めれば刑事告発はしないと警官に言われたという。「告発されないのは幸運だ、そうでなければ性犯罪者名簿に名前が載るところだ、と言われた」とアンドリューは話す。その警官には、「子どもがあれを見たらどうするつもりだ?」とも訊かれたという。
この質問に対しては、BuzzFeed Newsが話を聞いた男性たちは、子どもが入ってきたらすぐに行為をやめると口をそろえている。未成年者がそうした行為を目撃するなど、考えるだけでぞっとすると語っている。
「ひどく怯えていた」。この経験全体について、アンドリューはそう語っている。「警察のしていることには同意できなかったから、異議を唱えたかった。でも、そうしたら逮捕されるだろうと(感じた)」
警察によるこうした介入の歴史と状況に関しては、現在、LGBTコミュニティのメンバーだけでなく、一部の警官も、納得のいかないものを感じている。そうした行為にどう対処するかという判断にはきわめて微妙なバランスが求められており、単純明快な答えを出すのが難しくなっている。
公衆トイレではずっと以前から、狙い撃ちの取り締まりやおとり捜査が行われてきた。ティムとアンドリューが語った恐怖や、多くの人、とりわけ年配のゲイやバイセクシャルの男性が抱いている漠然とした不安の源になっているのが、そうした年月のあいだに、一部の警官がとってきた極端な行動で、そうした行動は、非道な同性愛嫌悪だとして非難を招いてきた。しかし、トイレでのセックスが唯一のはけ口になっていたのは、同性間の性行為が違法行為にあたり、同性愛者であることをほぼ全員が隠さなければならず、多くの人が偽装結婚を余儀なくされていた時代だけではない。
1998年にロサンゼルスの公衆トイレで逮捕されたジョージ・マイケル(「ワム!」のシンガーだったミュージシャン、2016年12月に53歳で死亡)は同じ年、風刺的なナンバー「アウトサイド」で怒りを表現した。そのミュージックビデオでマイケルが、自分を罠にはめた警官に扮して彼を嘲ったのは、単なる個人的な理由によるものではなかった。公衆トイレでの性的行為の取り締まりは、職務質問と同じように、政治色を帯びた火種になった。一部の人は、いまでもそう感じている。
BuzzFeed Newsが取材した人たちに話を戻そう。白髪まじりのビジネスマン、マイケル(仮名)は、40年近くにわたって公衆トイレでの性的行為を続け、相手を探して国中をめぐってきた。50代になったいま、マイケルは、1980年代から90年代にかけて自分の身に起きたことを話し始めた。

あるときは、リバプール・ストリート駅でこんな光景を見たという。「警官が、先端に鏡のついた長い棒を持って(トイレに)来た。その鏡で、個室の上から中を覗いて、ドアを叩くんだ。でももちろん、そうすると、ひとりで用を足している人も覗いてしまうことになる。腹が立ったよ」。マイケルは、マンチェスター・ビクトリア駅でもこの手法を目撃したという。
マイケルは、イギリス鉄道警察と話をする場を設けた。「こんな話をした。『あんなのはまちがっている。コミュニティを取り締まるには、コミュニティのサポートが必要だ。あなたがたに必要なのは、あなたがたがいま怒らせている人たちから、外に疑わしい車がいたら通報してもらうことだ。あなたがたの(公衆トイレでの性的行為への)対策は、考えなしだ。そうやって警官たちを送り出すのは同性愛嫌悪を助長するだけだ』とね」
マイケル自身も、ロンドン東部のハックニーの公衆トイレで、警察のおとり捜査に引っかかった経験があるという。現在ではそうした捜査は行われていないようだが、警察は数十年にわたり、若い魅力的な私服警官(「プリティ・ポリスマン」と呼ばれる)を公衆トイレに送り込み、セックスの相手を探す仲間のふりをさせていた。
ロサンゼルス警察がジョージ・マイケルに使ったのも、この手だった。1950年代には、ロンドン警視庁が有名俳優のジョン・ギールグッドに同じ手法を使っている。どちらのケースも、逮捕と、公の場での辱めにつながった(それに対して、元英首相のエドワード・ヒースも、1950年代に公衆トイレでの性的行為で警告を受けたとされているが、この事実は本人が死ぬまで隠されていた)。
マイケルはその日、ハックニーで、それと知らずに警官に近づいた。「その男は、私の隣に立ち、性器を出して硬くして、自慰をしながらそれを振り始めた」。そう聞くと、やりすぎだと思うかもしれない。なにしろ、その行為をしている警官本人も犯罪をおかしていることになるからだ。だが、おとり警官がそうした行動をとるのは珍しいことではなかったという。
マイケルが反応するとすぐに、警官は「手荒になり、私を暴力的に扱った」という。「身分証明書を要求し、私の財布を取り出した。彼らがクレジットカードを出して、床に投げ捨てたのを覚えている」。マイケルは逮捕されなかった。ロンドン警視庁はBuzzFeed Newsの取材に対し、過去の捜査に関する申し立てにはコメントしないと回答した。広報担当者によれば、「現在のポリシーと捜査手法は、主要なLGBTパートナーの協力を得て策定された」もので、公衆トイレの「先回り的なパトロール」は行っていないという。
公衆トイレの取り締まりに関しては、ほかにもマイケルが覚えていることがある。「リバプール・ストリート駅では、べろべろに酔った女性たちが、男性と個室トイレに消えていくのを数かぎりなく見た。男性用トイレのだよ。それについては、何の対策もとられなかった。彼女たちは、起訴されたりしない」
マイケルは長年のあいだに、公衆トイレを取り締まっている警官に何度か話しかけてきた。そんなときには、ある状況を想像してもらうと、警官たちは態度を変える傾向があったという。「こんなふうに問いかけるんだ。『ちょっと想像してみてほしい。あなたが車で帰宅する途中、6つある(トイレの)うちのどれかに立ち寄って、中に入って、女性にフェラチオをしてもらえるとする。誰にも知られることはない。それでも自分は誘惑されないと思う?』ってね」
現在の公衆トイレの取り締まりが、過去を繰り返すことになってはならないと、マイケルは考えている。どのような形であれ、公衆トイレでの逮捕を優先事項にすると「魔女狩りになってしまう」とマイケルは言う。「実際は趣味の問題にすぎないのに、反LGBT感情を生んでしまう」
唯一の問題点は、そうした行為が現実に法に抵触するということだ。2003年の性犯罪法の第71項によれば、公衆トイレでの性的行為は違法行為にあたる。だが、性的行為が禁じられる場所として法律で具体的に言及されているのは、公衆トイレだけだ。そしてそこは、ゲイやバイセクシャルの男性のセックスの場として、以前から悪名高かった場所だ。
異性愛者が性的行為をすることの多い公共の場所、いわゆる「ラバーズ・レーン(恋人たちの道)」や待避車線、駐車場などについては、法律は言及していない。
それとは対照的に、性犯罪法の第71項は、公衆トイレでの性的行為を意図的に抑止しようとしている。この条項は、以前の法律をさらに強化し、公衆トイレでのあらゆる形の性的行為を禁じる内容になっている。
また、そのほかの一般法には、公共の場での性的行為に関する言及があるものの、異性愛者が好んで利用する場所では、そうした行為を阻止するための警察の取り締まりは、とりたてて行われていない。
差別的になったり、差別的に見えたりするのを避けるためには、法律の適用を平等で釣り合いのとれたものにする必要がある。状況をさらに複雑にしているのが、公衆トイレでの警察の取り締まりが、市民の苦情に応じて行われることも多いという事実だ。イギリスの一般市民のなかには、いまでも同性愛に批判的な人が少なからずいる。そこから、こんな疑問が生まれる。男性と女性がセックスをしているケースよりも、男性2人がセックスをしているケースのほうが苦情が寄せられやすいのだろうか?
イギリス鉄道警察のジェニー・ギルマー警視は、BuzzFeed Newsの取材に対し、市民が不安に思うのは犯罪行為そのものであり、誰がそれをしているかではないと強調した。また、ゲイやバイセクシャルの男性が警察の標的になっているという意見については、そのようなことは一切ないとはねつけた。
だが、イギリス鉄道警察の統計によれば、2012年から2017年にかけて、同警察の警官によって公衆トイレでの性的行為の「容疑者として正式に処理」された人(全部で91人)のうち、92%は男性だった。警官に行為を止められ、「非公式な指導」を与えられた人の総数は、イギリス鉄道警察では把握していないという。
BuzzFeed Newsが話を聞いた男性たちの警察とのやりとりについては、ギルマー警視はいくつかの点に懸念を示した。特に問題視したのは、取り押さえられた人の詳細な記録の保持に関して、情報が与えられていない点だ。

「どのような情報を取得し、それをどのように使うかを、警官は明確にするべきだ」とギルマー警視は言う。「そうしていないのなら、警官の側に問題があった可能性がある」。ギルマー警視によれば、そうした情報は、警察が使用する捜査情報データベースに保存され、場合によっては「無期限で」保持される可能性もあるという。
一方、身体装着カメラについては、「普及が進んでいる」とギルマー警視は説明する。「通常の状況下では、警官が身体装着カメラを起動させる場合は、事情聴取を行っている相手に、その旨を伝えることになっている」。アンドリューの話では、カメラの起動は伝えられていなかった。
棒の先端につけた鏡の使用に関しては、容認できるものではないとギルマー警視は言う。「私なら、部下の警官がそうした手法を使っていると知らされたら、甚だしいプライバシーの侵害とみなすだろう」。また、「プリティ・ポリスマン」については、ギルマー警視の知るかぎりでは、イギリス鉄道警察では使われていなかったと述べた。「とはいえ、ここ10年から20年のあいだに、状況は大きく変わっている」とも、同警視は付け加えた。
公衆トイレでの取り締まりがテロ捜査の妨げになっているという見解については、ギルマー警視は全面的に否定した。対テロの取り締まりは依然として「一番の優先事項」だと説明したが、ティムの取り押さえに4人の警官があたったのは「多すぎ」だとも述べた。
警察による取り締まり以外にも、公衆トイレでの性的行為を抑止する対策は無数にある。たとえば、トイレの案内係や清掃員の導入、監視カメラ、小便器間の仕切り、下に隙間のない頑丈な個室の壁などが挙げられる。
だが、そもそもなぜ男性たちは、セックスを求めて公衆トイレへ行くのだろうか? そしてそれは、どのように行われているのだろうか?
すべての公衆トイレが、性的行為に使われているわけではない。そのため、それを求める男性はたいてい、まずは特定のサインを探す。同性愛的な落書きや絵だ。BuzzFeed Newsが話を聞いた男性たちは、それ以外は行動がすべてだと語っている。彼らの説明によれば、意図を伝える一連の暗黙のルールがあるという。
ティムによれば、相手が性的行為を求めているかどうかを確かめるために最初にするのが、「どれくらい時間をかけているか」に注目することだという。「ちょっと長くかかっているようなら、(性的行為を)求めている可能性があると判断する。あとは、『やたらと振る人』とか、ちょっとした雰囲気とか、微妙な目線だね」
個室では、仕切りごしに意図を伝え合う。「咳払いがある」とティムは言う。「足が(仕切りの下から)少しずつ近づいてきたり、軽く打ち付けて、こちらも打ち付けるかどうかを確かめたりする」。個室の壁に穴が開いていれば、もっと簡単にことが運ぶという。「グローリー・ホール」と呼ばれるこの穴を通して、トイレットペーパーに書いたメッセージを渡したり、行為を始める前に覗いたりすることができる。
こうしたことのすべては、男性たちが公衆トイレでの性的行為を知るに至った経緯や、それが習慣になった理由とつながっている。
BuzzFeed Newsが話を聞いた男性のほとんどは、まだ若いときに公衆トイレでの性的行為について知った。当時の彼らは、同性愛者であることを隠しているか、LGBTの人たちと交流するほかの手段がないか、いずれかの状況に置かれていた。未成年だった人も多い。
先に登場したビジネスマンのマイケルの場合、こうした世界を知ったのは18歳だった。ロンドン東部の郊外で育ったマイケルは、1980年代はじめに、ニューベリー・パーク駅のトイレの壁で落書きを目にした。ユダヤ系のマイケルは、ユダヤ教の教えを忠実に守ろうとしていた。同性愛者であることを隠していて、ガールフレンドもいたが、その落書きに招き寄せられたという。
「よく、小さな表が書かれていた。歳とサイズと好みを書いた表だ。たとえば、23歳、7.5インチ(約19cm)、フェラチオとマスターベーション、という具合だ。ここは(ゲイの)人々が来る場所なんだという、はっきりとした高揚感があった」
ある日、個室で座っていたときに、マイケルは仕切りの穴を見つけた。「穴のほうに身を寄せたのを覚えている。すごく驚いたよ。反対側に目があって、まばたきをしていたんだから。そのあと、壁の向こうの男性は自分の性器を見せたので、意味がわかった。彼は個室を出て、こちらの個室をノックした。私は彼を中へ入れた」
仕組みを理解したマイケルは、同じ場所に戻るようになった。「この場所にくぎ付けになった」とマイケルは言う。だが、名を明かさない手軽なセックスだけを求めていたわけではない。「この肉体的な情熱のすべてを伝えられる人に出会いたかった。この情熱を、自分の愛する誰かに向けたかった」
マイケルは、公衆トイレで行う性的行為の魅力について、こんなふうに表現している。「現実逃避。不安を一時停止してくれる。個室にいると、安心して、ありのままの自分になれる。差別を消してくれる。社会的・職業的な仮面をつける必要もないし、なんの圧力もない」
公衆トイレ以外でそうした感情を吐き出せる場所は、マイケルにはなかった。父親に対して、自分は男性に惹かれていると打ち明けたときには、精神科医のもとに送られた。マイケルはのちにガールフレンドと結婚したが、公衆トイレでの性的行為を続けている。
BuzzFeed Newsが話を聞いた男性の多くに共通することだが、マイケルにとって、公衆トイレで過ごす時間は、現実の生活から逃避できる、別世界のものだった。だがそのあとは、すぐに現実が戻ってくるのが常だった。
「帰宅すると、いつも祈りを唱えた」とマイケルは言い、顔をうつむけた。「本当に悲しかった。当時は、ゲイの男性として自分を誇りに思える拠り所がなかった。自分の恋愛が普通のもので、ほかの人たちと同じなんだと考えることができなかった。(公衆トイレでの性的行為から)得るものはあったが、それは闇に包まれ、恥に汚されていた」
同性愛が異性愛と同様に広く受け入れられ、尊重されていたなら、いまごろは、同性愛者であることを隠して苦しむ人はいなくなっていただろうし、公衆トイレでの性的行為も下火になっていただろう、とマイケルは言う。「あれは、社会的な抑圧の副産物だ。社会はすぐに非難するが、そうした行為を生み出した責任の多くは社会にあることを理解しないといけない」
それから40年近くが経ち、みずからのセクシャリティを明かし、男性とつきあっているいまでも、マイケルは公衆トイレでの性的行為を続けている。「変えるのは現実的ではないと思う。自分という人間の、あまりにも深いところに組みこまれているから。それに、問題だとも思っていない。ただ、あまりやりすぎないように気をつける必要はある」
数々の暗い面がある一方で、すばらしい経験も数限りなくあった。「その場で会って、すぐに恋に落ちた相手もいた。終わったあとで、『コーヒーでも飲みにいかない?』と誘ったこともあった。どこかへ行って、魅力的な人と出会って、その出会いが情熱的で親密なものだったら、そこから外に出たときも、人間であるということがとても素敵なことに感じられる。自分は生きている、という気分になるんだ」
50代のスティーブは、アイルランドで育ってロンドンに移り住んだ。陽気で、セックスに対して開放的で、公衆トイレでの性的行為やハッテン場の公園での相手探しに関しては、好戦的ともいえる姿勢をとっている。
スティーブがこうした行動を始めたのは、まだ結婚していた40代のころだ。ある晩、チャリング・クロス駅のトイレで目にしたものが、彼の人生を変えることになった。
「小便をしていたら、3つほど横の小便器に、若い魅力的な黒人のゲイがいて、勃起した大きな性器を平然と撫でていた。なんてあからさまなんだ、と思ったよ。好奇心に負けて、2日後のラッシュアワーにまた行ってみたら、何人かがそれぞれ小便器の前にいて、全員が猛然と自慰をしていた」
その日から、スティーブは何度も通った。「圧力鍋の蒸気口のバルブみたいだった」。スティーブは、ティーンエイジャーのころから自分は同性愛者だと自覚していたが、その事実を怖れていた。その恐怖の起源は、ある発言にさかのぼる。
「家族ぐるみでつきあっていた友人に、性的ないたずらをされた」とスティーブは話す。7歳のときだった。11歳か12歳になったころ、兄のひとりに打ち明けた。「兄はこう言ったよ。『誰にも言っちゃいけない。もしそれが本当なら、おまえは同性愛者ということになる。父さんは、ゲイの息子がいたら家から追い出すと言っていた』ってね」
スティーブは、これまでに出会った男性たちや、情熱的で楽しい経験の話に加えて、警察や、同性愛者を攻撃する者たちとの遭遇についても話してくれた。自分の好みを説明する際には、スティーブは実用的な言葉を好んで使い、心理学的な解釈には抵抗を示した。
「男というものは、どうしようもないクズだ」とスティーブは陽気に言う。「公衆トイレやハッテン場の魅力は、すぐに利用できるところにある。自分に正直になって、『手あたりしだいにペニスをしゃぶるのが好きなだけだ』と言うべきだと思うね」
ティムとアンドリューは、どちらも40代で、どちらもリバプール・ストリート駅で警察に取り押さえられた。この2人も、公衆トイレでの性的行為をティーンエイジャーのときに知った。当時は、ほかに選択肢はほとんどなかった。
中年にさしかかり、成功を収めているティムにとって、過去を振り返るのは簡単なことではない。ティムがトイレで初めてグローリー・ホールを見たのは7歳のときだったという。衣料品などを販売する「BHS」(ブリティッシュ・ホーム・ストアーズ)の店舗にあるトイレだった。7歳のときに見たものを実際に体験したのは、それから10年後、自宅近くの公衆トイレでだった。
「そこに座って、『すごい、みんなここに来るんだ』と思ったのを覚えているよ。びっくりしたのは、いかにもな感じのゲイや、見るからにゲイとわかる人たちではなかったことだ。ストレート風の建設作業員とか、結婚しているビジネスマンとか、老人とか……」。ティムは、若かったころに公衆トイレでの性的行為で得たものを話し始めた。「興奮、安堵、自分に魅力があるという意識、求められているという感覚」
だが、ティムはそれに依存するようになった。ティムは「感覚が麻痺する」と語り、公衆トイレでの性的行為に心を支配され、催眠術のループのようなものに陥ったと説明する。
「不安とか鬱とかがあっても、(公衆トイレに)入ると、あっという間に抜け出せる」。反対に、そうした不安を増幅させることもあるという。「そのために1日仕事を休んだからとか、15回したからとか、選んだ相手があまり良くなかったからとか、そんな理由でね。それか、危険を冒したから、とか」
20代のあいだに、探検は中毒に形を変えた。自分にとっての「ワナ、牢獄」になってしまったという。
「(公衆トイレでの性的行為が、)あらゆることへの答え、あらゆることの頼みの綱になった。気分のいいときにも、悪いときにも、退屈なときにも、興奮しているときにも、ひっきりなしにあらゆる感情が手に入ったし、何も感じない状態になることもできた。ときには、ほとんど自傷的になることもあった。傷つくことになるとわかっているのに、やめられないんだ」
その後、公衆トイレとの結びつきが弱まるにつれ、ティムの精神状態は大幅に改善されたが、複雑な状況はいまも残っている。公衆トイレでの性的行為は、自己評価を高めることもあれば、打ち砕くこともあるとティムは言う。とはいえ、出会い系アプリよりもマシだという考えは変わらない。というのも、公衆トイレのほうが、写真などの外見で判断されることが少なく、グラインダーや「スクラフ(Scruff)」といったアプリでよく見られる、過剰な選別や何気ない残酷さから解放されるからだ。
「(公衆トイレだったら、)自分を売りこんだり、プロフィールを書いたりしなくてもいい。好きなものと好きじゃないものを説明したり、写真をアップしたりする必要もない」。いずれにしても、なぜ2017年のいまもセックスを求めて公衆トイレへ行くのかという疑問に対しては、適切な返答はひとつだけだとティムは言う。――「なぜ行ってはいけないのか?」という答えだ。
「主流派の文化圏にいる人たちに、こう言われている気がする。『ほら、これ(アプリ)があるなら、こっち(公衆トイレ)はいらないはずだろう』ってね。そんなの、人の勝手だろ?」
40歳のアンドリューは、田園地方で育った。地元の公衆トイレで初めて落書きを見つけたのは、12歳か13歳のときだった。正確には覚えていない。「そうした感情を持っている人を誰も知らなかったし、自分以外にゲイの男性がいるってことも知らなかった」とアンドリューは話す。その声はハスキーでかぼそく、遠く離れているような声音で、当時のことを振り返りたくないと思っているような印象を受ける。
当時のアンドリューは、同性愛者であることを表向きは否定しながらも、放課後にそこへ行き、複数の男性と出会った。「すごく楽しいというわけではなかった。(そこで出会った男性たちは)魅力的というわけではなかったから。でも、通い続けた」。魅力的な人がいるはずだと期待し続けていたが、いまになってみると、その根底に何があったのか、よくわかるとアンドリューは説明する。
「自分の存在を認めてくれるものを、探し求めていたのだと思う」
法律からすれば、アンドリューが未成年のときに経験したことは、明らかに性的虐待だ。だが、本人の受け止め方は、複雑に渦巻いている。公衆トイレで出会った男性たちに怒りを覚えたこともあったが、いまでは彼らに共感を感じているとアンドリューは言う。ゲイの男性にとって人生は、ほかの人たちとはまったく異なるもので、大きな困難が伴う。そのため、標準的なルールをあてはめるのは容易ではない。
また、アンドリューはこうも言っている。「誰かに公衆トイレに引きずりこまれたわけじゃない。自分が何に足を踏み入れようとしているのか、ちゃんとわかっていた」。もちろん、だからといって、法律上の問題が変わるわけではない。相手が未成年の場合は、同意は成立しえないからだ。
自分の経験のなかには害悪もあったことを、アンドリューは認めている。しかし、それが害悪だとわかったのは、のちに他者に助けを求めたときのことだ。
「セラピーで、自分のセクシャリティを認めるという考え方を突きつめてみたときに、(ああした体験をしたときに)ノーと言えるだけの自信があったらよかったのに、と思った。大人になったいまなら、もっと自信をもって交渉できただろうと思う」
アンドリューの経験は、ルークの経験に通じるものがある。ルークの物語は、この世界のひときわ暗い部分を呼び起こすものだ。30代前半のルークは、無精ひげが生えたハンサムな男性で、芸術関係の仕事をしている。
ルークは、イギリス西部にある、人口24万人程度の都市ストーク・オン・トレントで育った。「まさに」労働者階級の家庭で、蓄えはほとんどなかったという。
自宅近くの公園の公衆トイレで初めて落書きを目にしたのは、10歳のときだった。
「汚くて臭いトイレだった」とルークは話す。よく響く太い声には、随所にストークのアクセントが混ざっている。「『ここでしゃぶってもらった』とか『毎日、午後5時から7時までここにいる』とか書いてあって、ポルノみたいな絵もあった。ものすごく怖かったけど、同時にすごく興奮したのを覚えている。ああ、別の世界があるんだ、という感じだった。そのとき初めて、自分以外にもゲイの人がいるのを知った」
自分がほかの人とは違うとルークが感じ始めたのは、ちょうどそのころのことだ。だが、成長期のLGBTの人たちにとってよくあるように、ルークも、自分を肯定したり、安心させたりする手段を持たなかった。

「異性愛者の子どもだったら、性的・社会的なアイデンティティに目覚め始めたとき、すぐに共感できるリソースが手に入る。わかるわかる、それ知ってる、という感じになる。(ゲイの人たちには)それがない」
そのトイレで見たものは、ルークを虜にし、彼は何度もそこへ行くようになった。「そこは、(ゲイの)世界に通じる窓のようなものがある、唯一の場所だった。対話もなかったし、話し相手もいなかったけれども。私たちの生きていた時代と文化には、私の行ける場所はなかった。ああ、その時代にこうした思いをもてれば良かったのに」
ルークをふたたびその公衆トイレへ導いたのは、無知と好奇心だったという。だが、彼はそこで最初の性的虐待を受けた。一番古い記憶として、こんな出来事を覚えている。「すごく年をとった男が、トイレの個室の下から近づいてきた。男は膝をついて、私をつかまえようとした。怖かった。本当に怖かった」
その男性は、ルークをつかまえるには至らなかったが、ルークは誰にも話さなかった。孤立して怯えていたルークは、自分の気持ちもよくわからないまま、何度も何度もそのトイレへ戻った。「そのトラウマ的な経験が、磁力になった」とルークは言う。「この屈辱的な秘密の場所が、私が行ける場所だった」
ルークは学校でいじめられていた。芸術家肌の柔和な子どもだったので、いじめっ子たちは、彼らもルークもその言葉の意味さえ知らないうちから、ルークを「ゲイ」と呼んでいた。
11歳のころ、小便器の前に立っていたときに、別の男性に性的ないたずらをされた。「壁にくぎ付けになったような気がした」とルークは話す。強い力で押さえられていたからではなく、恐怖で体が動かなかったからだ。「声が出なかった」とルークは言う。「手足を動かすこともできなかった。世界中のお金をすべてあげると言われても、動けなかったと思う」
しばらくは公衆トイレに近づかなかったが、結局はまた行くようになった。12歳から16歳までのあいだ、そのトイレは、いじめからの逃避の場になった。
ルークによれば、母親はとても愛情深い人だったが、息子が同性愛者だとは知らなかったので、その愛がルークの心の奥底まで届くことはなかった。母親が抱きしめていたのは、ルークのまわりにある鎧だった。また、当時は1990年代後半だったので、教師が同性愛を説明することを事実上禁じた1988年地方自治法28条がまだ効力を持っていた。そのため、学校は同性愛者の子どもたちに、沈黙のほかには何も与えてくれなかった。
その公衆トイレは、ほかのものを与えてくれた。「結びつき」への期待だ。「こう夢想するようになった」とルークは言う。「いつか自分と同じような少年を見つけられる、ってね」
ルークは、そうした少年を探し始めた。つまり、地平線の向こうで魔法のような現実を形づくっている想像上の人物、自分を理解して救ってくれる象徴のような少年だ。その探求の結果、ルークは、地元にある別の2つの公衆トイレを見つけ出した。
「何時間も――本当に何時間も、行くあてをなくしたみたいに、公衆トイレの近くに座って、自分と同じ年ごろの少年が来ないかと待っていたのを覚えている」
だが、ルークが見つけたのは、たいていは年をとった男性で、なかには酔っている人や、ドラッグをやっている人もいた。同年代の子どもたちから疎外されて孤立し、自分が同性愛者だと誰かに打ち明けるのは危険だと感じていたルークは、常に口を閉ざし、自分のまわりに壁を築いていた。そのせいで、早い時期に安心して恋愛や愛情を探求することができなかった。たいていのゲイの子どもたちと同じく、遊び場でつなぐ手などなかったのだ。
ルークにとって、いじめによって醸成される不安の唯一のはけ口は、公衆トイレを訪れることだった。「この探求に出るたびに、気分が変わって、体のなかの化学物質も変化した。たくさんの痛みを癒す、薬のようなものだった」とルークは言う。やがて、それをしないではいられなくなった。「モルヒネを1滴たらすような感じだった」
だが、そうした解放感は長くは続かなかった。トイレの個室での出会いのあとは、「感情的にも身体的にも、ものすごく強烈な墜落」があるのが常だったとルークは言う。「これはすごく悪いこと、すごく汚くて、すごくまちがったことなんだ、という感情に襲われた」
若き日のルークは、感覚を麻痺させる強迫状態に置かれていた。「幽霊かゾンビのようだった。この世界で居場所がなかったから」
一度だけ、16歳のときに、公衆トイレのひとつで同じ年の少年に出会ったことがある。「キスをした」とルークは囁くように言った。「その子が、初めてのキスの相手だった」
だが、長いあいだ、ルークは自分のしていたことを秘密にしてきた。「みんながこのことを知ったなら、自分は人間として認めてもらえないだろうと思っていた。それほど大きなことだった」
そうした思いをさらに悪化させたのが、10代後半のころの体験だ。当時のルークは、夜間に公衆トイレに通い、さらに遠くのハッテン場へ足をのばすこともあった。「一度、レイプされた」とルークは話す。「それから、別の人にもレイプされそうになった」
性的虐待のほかに、少年期の孤立も、深い心の傷になっているとルークは説明する。「それが自分のあらゆる行動に影響していると思う。自分の感情的な反応について、いろいろ考えているけど、ほとんどは、元をたどればその時期に行き着く」
19歳でカミングアウトしたあと、20代半ばになってようやく、ルークは専門家の助けを求めるようになった。15年のあいだ抱えこまれてきた心の傷と恥辱はあまりにも大きく、その責任が誰にあるのか自分ではわからないほどだった。
ある日、転換点が訪れた。そのときのことを思い起こすと、ルークの声の調子が変わり、言葉がゆっくりになった。「誰かにこう言われていたのを覚えている。『あなたは、子ども、だった』と」
そのときまでは、自分に起きたことは自分のせいだと思っていた。「こう言われたよ。『いま、あなたが10歳の子を知っていたとして、その子たちと性的な関係を持ったとしたらどうなるか、と想像してみて』と。ぞっとする想像だった。10歳の子といったら、すごく……ほんの子どもだ。私が立ち直るには、あれは性的虐待で、あの人たちは性的虐待者だったと認める必要があったんだ」
公衆トイレで最後に興奮を覚えたのは2年ほど前のことだ、とルークは言う。有意義な心理療法を受けたあと、ルークは人生を変える発見をした。その発見を、ほかのゲイやバイセクシャルの男性たちがまだ知らないのなら、ぜひ知ってほしいと願っている。
「私が発見したのは、こういうことだ。これまでで最高のセックスを経験したのは、性的な関係を築きながら、それがもたらす痛みとか、自分がどんな気持ちになるかを口にしたときだった。以前は、性的な満足感は、その種の行動(公衆トイレでの性的行為)から見つかるものだと思っていた。でも実際には、最高の満足感を得られるのは、気持ちを通わせて、そんな体験をしたということを声に出して言えるときなんだ。感情的な解放は、性的な解放よりもずっと大きな満足感につながるんだよ」
とはいえ、警察による公衆トイレの取り締まりや、同性愛嫌悪の風潮については変えていかなければならないとルークは言う。「解決すべき大きな社会的問題が残っていて、ゲイの男性たちは行動を抑えこんで地下に潜らざるを得ない状況が続いている。まだそんなことをしているからといってゲイの男性たちを蔑むのは、恵まれた立場にいるからこそできることだ」
ルークが言うには、ほとんどの異性愛者は、異性愛が社会でどれほど支配的で、同性愛嫌悪が同性愛者の心の内をどれほど傷つけているのか、まったく理解していないという。「彼らはまだわかっていない」とルークは言う。「我々はほとんど進歩していない。我々はまだ、さまざまな申込用紙などで、LGBTという選択ができるよう闘っている段階だ。それは氷山のごく一角にすぎない」
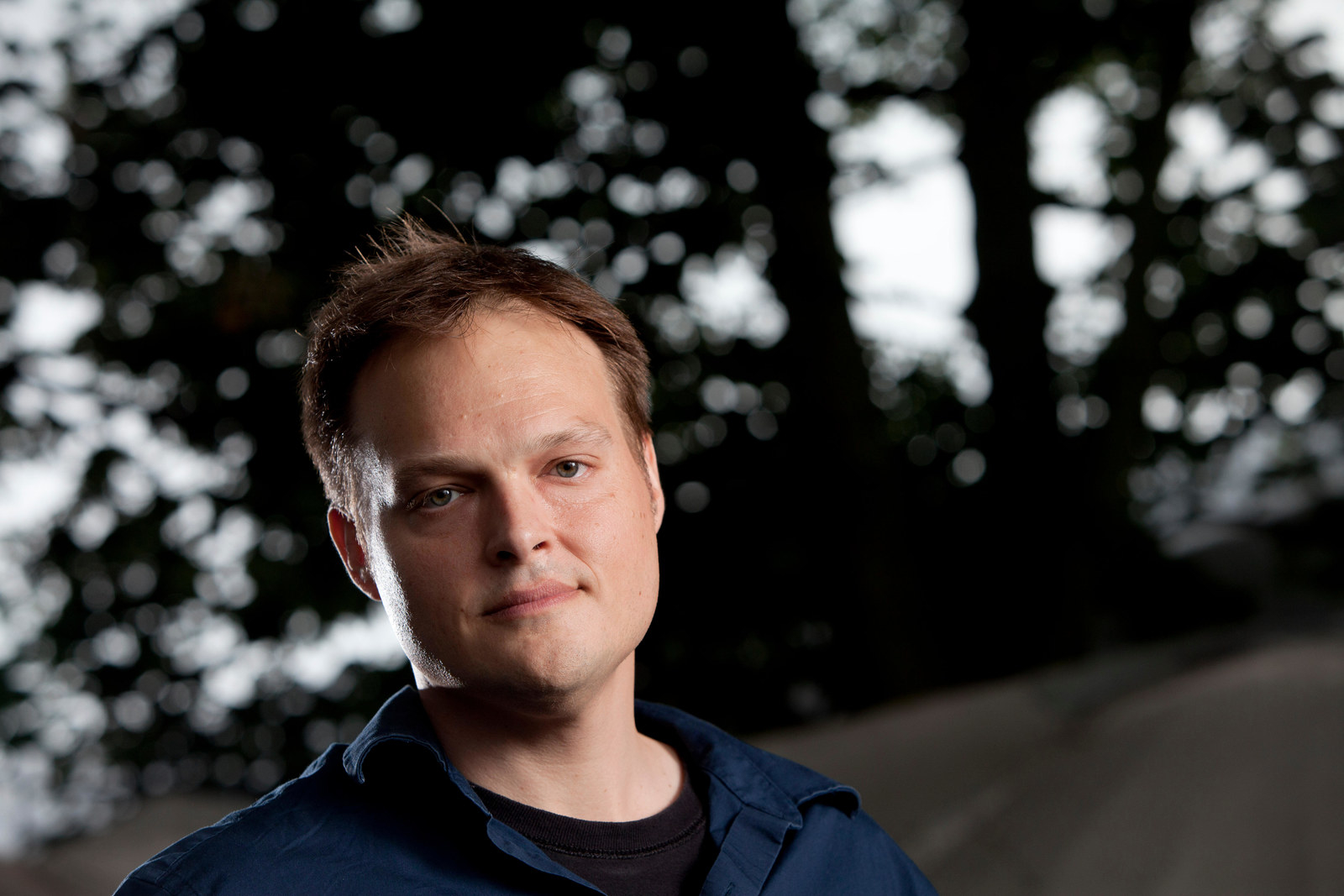
小説『What Belongs To You(君に属するもの)』のなかで、ブルガリアの公衆トイレでの性的行為を叙情的に描いたアメリカの著名作家ガース・グリーンウェルも、ルークと同じいらだちを抱いている。グリーンウェルはBuzzFeed Newsに対し、ケンタッキー州での少年時代について語ってくれた。白人と異性愛者が中心のかたくなな世界で、ほかのLGBTの人たちとのつながりを持たずに育ったグリーンウェルは、12歳のときに、壁に落書きのある公衆トイレを発見したという。「目のまえに、世界が丸ごと開かれた感じだった」とグリーンウェルは言う。とはいえ、そのときはまだ、行為に加わることはなかった。
14歳になるころには、地元の公園で、相手になる男性を定期的に探すようになっていた。セックスは、そうした行動の魅力、もしくは欲求の一部でしかなかった。
「そこで見つけたのは、同性愛者のコミュニティだった」とグリーンウェルは話す。「異性愛者をまったく意に介さず、異性愛者の承認を求めず、みずからを肯定するコミュニティを知ったのは、それが初めてだった。そのとき初めて、同性愛者であることが、楽しみと喜びの源になった」
グリーンウェルは、こう語っている。「快楽と一種の親密さを中心にして成り立つコミュニティには、強力で意味深い雰囲気があった。その価値は、継続時間で測れるものではない。たとえ20年も続かなくても、それは価値のあるものだ」。16歳になるころには、毎日通うようになっていた。
そのときの体験を、グリーンウェルは、やわらかいが力のある声で、ロマンチックに語った。その体験については、「ことさらに弁解しようとは思わない」とグリーンウェルは言う。
「全員が見知らぬ人同士の場で、情緒的かつ官能的な親密さを築くというのは、人生を深く肯定する行為だ。そうした関係の価値や、あの情交の瞬間を否定しようとする同性愛者の人生の物語は、私には受け入れられない」
グリーンウェルはそのころ、深い友情も築いたという。グリーンウェルは、先述したルークとは異なり、出会った男性たちから性的に虐待されたという感覚は抱いていない。それは、そうした出会いのなかで、みずから主体的に動いていたと考えているからだ。その一方で、当時の自分と同じ年ごろの子たちがハッテン場の公園で相手を探していると想像すると、恐怖に襲われるという。
同性愛嫌悪のない世界だったら、セックスを求めて公衆トイレへ行く人は存在していただろうか? そうした疑問や、警察のとるべき対策をめぐっては、意見の相違がある。実際の経験者の証言もさまざまだ。だが、この点では意見が一致している――。周囲の人たちや集団に適切に育まれ、人とのつながりや理解を得て、ありのままの自分を見せることができたなら、LGBTの子どもたちが危険な場所に引き寄せられることはなかったはずだ。
ゲイやバイセクシャルの男性の心の内面は、体験の違いによって、一生をつうじて変わっていくはずだとルークは考えている。ルークは一瞬、口をつぐみ、自分が経験した性的虐待や、逃れようとしてきた敵意や、別の場所で救いを見つけるまでにかかった年月に思いを馳せた。そして、穏やかだがはっきりとした口調でこう言った。「本当にすばらしいといえる場所があるはずだ。我々はそこにたどり着かなければいけない」
*いくつかの名前は変更されています。
この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳:梅田智世/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan

