安倍晋三首相が総理大臣を辞任することを発表した8月28日、ネット上では難病を抱えながら総理大臣の職務を遂行していたと擁護する声や、難病を抱える者は要職に就くべきではないといった批判が巻き起こった。
「安倍首相、約1カ月ぶり夜の会食 コース完食しワインも」(朝日新聞、9月11日)という記事が配信された折には、潰瘍性大腸炎を辞任の理由として挙げたことへの批難の声が上がっている。
両者の主義主張や政治的信条は異なるが、政権支持層も非支持層も病気を使って、自らの主張を正当化しようとしていた点では変わりはない。
こうした病気の「悲惨さ」を強調する社会の風潮に、危機感を抱く人がいる。

安倍首相と同じ難病、潰瘍性大腸炎を患う文学紹介者・頭木弘樹さんだ。
社会の中で、「潰瘍性大腸炎」という難病の悲惨さが強調される中、頭木さんが伝えたいこととは。
悲惨さの強調がもたらす過度な一般化
#潰瘍性大腸炎 について取材の申し込みが多数ありますが、「首相をねぎらう気持ちを国民全員が持てるように」という趣旨のものが少なくありません。 その意味するところは、"いかに悲惨な病気なのかを語れ"です。 私はお断りしていますが、他の方が出るでしょう。 "悲惨さの強調"は、とても心配です…
20歳で発症し、33歳まで、ほぼベッドの上で生活する日々を送っていた。40歳以降、健康な人よりも2周り近く遅れて「社会」に飛び込んだ。
難病となり絶望と直面した瞬間もあった。現在では、倒れたままの日々を支えた文学作品を世の中に紹介することを仕事とし、執筆した本にはヒット作も少なくない。
頭木さんは安倍首相が辞意を表明した翌29日、Twitterで「"悲惨さの強調"は、とても心配です」と警鐘を鳴らした。
「首相を労う気持ちを国民全員が持てるように」とのメディアからの取材依頼が複数届いたことに対し、呈した苦言だ。
「政権批判や擁護に、病気を道具として使わないでください」、頭木さんは言う。
メディアが取材をする上で、病気の悲惨さに焦点を当てた企画を立てることは「無理もない」と頭木さんは言う。これまで、頭木さん自身も幾度となく潰瘍性大腸炎の体験をメディアに対して語ってきた。
「メディアは基本的には、その病気の悲惨な事例を取材しますよね。『大したことはありません』と語る人を取材しても、きっと記事にならないでしょうから。これは仕方のないことだとは思います」
「ですが、当事者の方がその取材に答えて語ったことが一般化されて、ある種の偏見として作用してしまうことを危惧しています。その言葉は、その体験は事実です。でも、それだけをもって、『この病気はこういうものだ』と理解することは危ういことです」
自分自身が取材に答えた記事でも、病気によって生じるわかりやすい悲劇にばかり人の注目が集まることを知った。
ある時、自分の身に降りかかった悲劇をわかりやすく伝えるタイトルは反響を集めた。
読まれなければ、どれだけ素晴らしい記事であっても意味はない。だから人目を引くタイトルをつける。
そうした論理が一部にあることに理解は示しつつ、一連の出来事は「悲しい勉強だった」。頭木さんはつぶやく。
潰瘍性大腸炎とは?

潰瘍性大腸炎は国の「指定難病」に指定されている原因不明の病気だ。難病情報センターのデータベースによれば、大腸の粘膜に潰瘍などができ、下痢と腹痛を引き起こす。下血を伴う場合もある。
炎症が起きる「活動期」と症状がおさまっている「寛解期」があり、炎症を抑えながら寛解を目指し、その寛解を長く維持するための治療が行われる。
薬物治療による効果が見られない場合や大量の出血がある場合には大腸の摘出手術を行うこともある。
頭木さんは大学3年生の時に発症し、寝たきりの生活が13年間続いた。食事制限も非常に厳しく、食べることができたのは豆腐と卵とささみ、そして裏ごした野菜のみだった。
「食べることはできた食べ物は4つだけ。ずっとその繰り返しです。13年間で食べ過ぎてしまったので、未だにささみは大嫌いなんですよね(笑)」
薬物治療には「プレドニン」という免疫を抑える副作用のある薬を使うため、周りの人が咳をしただけで風邪をうつされたこともあったという。
「プレドニン」のもう1つの副作用は骨が脆くなること。その副作用は使用を続けるごとに蓄積していく。
副作用の蓄積が続き、薬の使用量を減らすため、手術を受けることを勧められた。だが当初、「手術を受けるのは嫌だった」。
注射すら苦手だった頭木さんにとって、この手術を受けるという選択は覚悟を要した。だが、日常的に使用するプレドニンの量を減らすため、33歳のとき、手術に踏み切った。
当事者なのに聞いてもらえないのはなぜ?

手術を受け、外で人と接する機会が増えた頃、頭木さんはある不思議な体験をした。
自身の潰瘍性大腸炎の症状を説明すると、「それはテレビで聞いた話と違う」と反論を受けた。あるいは、知人の潰瘍性大腸炎患者のケースを例に挙げ、「そんなに大変そうにするのはおかしい」と指摘を受けた。
こうした体験は1度や2度ではない。
「非常に不思議な経験でした。当事者が目の前にいて、その人が自分のことを話しているのに、全く信じてくれない。身近な例やマスコミによる情報の刷り込みは怖いと、その時に実感しました」
「1度、この病気とはこういうものであるという情報をインプットすると、なかなかその認識を変えることは難しいものです」

第一次安倍政権が幕を下ろした後、それが持病である潰瘍性大腸炎の悪化のためであったことを安倍首相が雑誌で語った。その直後、「総理大臣を辞めるほどの病気だ」というイメージが社会に広がったと頭木さんは振り返る。
「当時のインパクトはすさまじいものでした。総理大臣を辞めるほどの病気というイメージが一部で一般化されてしまったために、『僕の場合は仕事ができます』と伝えても、『途中でやめることになるんじゃないか』と指摘する声もありました」
そして、また、その偏ったイメージの氾濫が起きた。
安倍首相の辞意表明後、政権支持層と非支持層それぞれが病気を使った言説を用いたことが突きつけたのは多様な「病気の使われ方」だった。
「今回、SNS上に氾濫した病気の『使われ方』の多くは問題のあるものでした。しかし、病気が過度な一般化をされ、人々が病気に偏見を持つということを象徴する出来事であったと感じます」
「この休みのなさは…時々投げ出したくなるんです」

「絶望には孤独がもれなくついてくる」
難病になり、実感したのは治らぬ病を持つということの孤独だった。
潰瘍性大腸炎と診断を受けた時、その当時は主治医は「一生、治らない病気です」「一生、親御さんに面倒を見てもらうしかありません」と宣告された。
ふとした瞬間、横にいる家族がテレビを見て笑っている姿を目にして、孤独を感じた。自分にとっては片時も忘れることはできない病気の存在を、自分以外の誰かはその瞬間だけは忘れることができる。
「難病であることを忘れられる瞬間があったら、どんなにいいかと思うんです。ずっと続くということは、すごいことです。この休みのなさは…時々投げ出したくなるんです。病気もね、週1日は休みがあったら、患者さんもずいぶん明るくいられるんじゃないかと思いますよ」
今この痛みはこの世界で自分しか感じていないのではないか。そう感じることも少なくない。
たとえ、同じ病気を持つ人同士であっても、症状が異なるために完全にわかり合うことは難しい。わかってもらえないと知った時、「本当に自分は一人だ」としみじみ思う。
ぼくには誰もいません。
ここには誰もいないのです、不安のほかには。
不安とぼくは互いにしがみついて、夜通し転げ回っているのです。(カフカ, 『絶望名人カフカ × 希望名人ゲーテ - 文豪の名言対決』)
「時々、親が子どもに『自分が代わってあげたい』と言うでしょう。あれは、本当に代われるものなら、一瞬でもいいから代わって欲しいですよ。少しの間交代して、外に出て、ビールの1杯でも飲めたらどれだけ幸せか」
難病になることは「宇宙人に出会ってしまったようなもの」と頭木さんは表現する。
「自分だけ見たこともない宇宙人に出会ってしまったとしたら、その体験を人に話したとしても完全には伝わりきらないですよね。だって、相手は見たこともない生き物ですから。病気についても、そういうもどかしさがすごくある。自分しか知らない何か、しかもそれが辛い出来事である場合、これは非常に孤独感が強いものです」
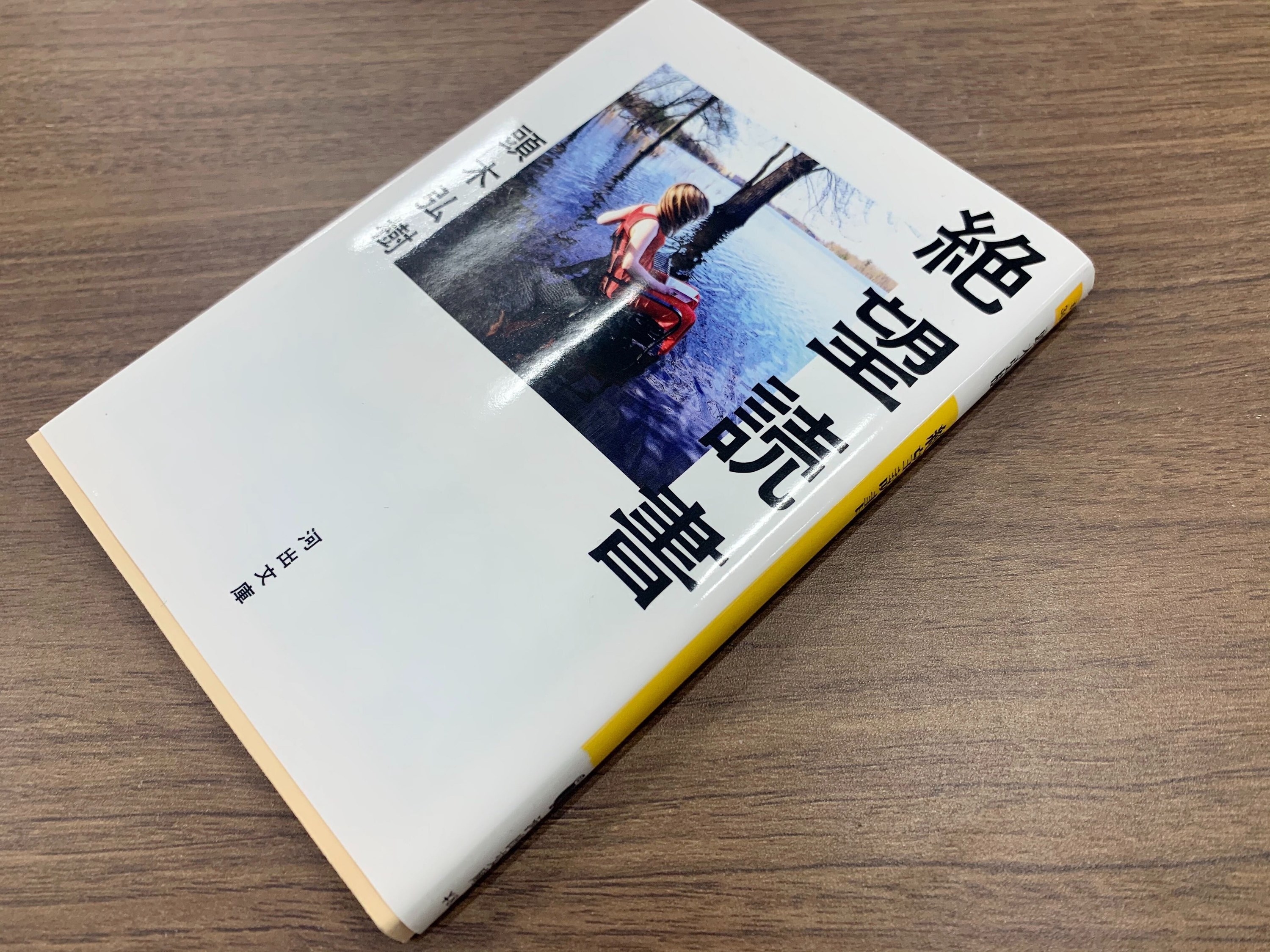
そんな難病を抱える絶望、孤独の中で文学に共感することで救いを感じた。
もしも病気になることがなければ…生きることができたはずの物語を思うことも少なくない。絶望を味わうとき、「こんなものは自分の人生ではない」と言いたくなる瞬間がある。
今では自身の経験をもとに、絶望した期間をどう過ごせばいいのか教えてくれる文学作品を集め、紹介する。
なぜ、皆同じような教訓を語るのか

難病になり辛かったのは孤独だけではない。
背中には社会や他人が思い描く「良い患者」であることを求められるプレッシャーがのしかかった。
「大抵の人は、苦しんでいる病人を見ることはできれば避けたいと思うのではないでしょうか。できることなら、明るく、楽しく、病気になって大切なことに気付くことができたと語る人たちと接していたいと思うのは自然なことかもしれません。ですが、それは、実際に病を抱えて生きている人が口を閉ざしてしまうことにつながりかねないと感じます」
患者が愚痴を語ることすら歓迎しない空気を時折感じるという。社会からは「面白く」「ユーモアを交えて」語ることが歓迎される。
「病人になった途端、芸人になることすら求められる。そんな無茶振りはね、困るんです」
「それに、笑えるように面白おかしく話すことで、事実自体が歪んでしまうこともあります。それはもう事実ですらない。ユーモアを持って語りましょう、伝えましょうという風潮を作ることは危険です」
「本を書く上で、わざと笑わせようと思ってふざけた表現を使うことはありません。冗談を交えることもほとんどない。でも、それでも笑える瞬間がある。それこそが体験を語るということなのだと思います」
人生はクローズアップで見れば悲劇だが、
ロングショットで見れば喜劇だ。(チャップリン)
今では、このチャップリンの言葉の意味を噛み締める。
激しい下痢に襲われ、トイレに向かって点滴台を担いで走った自分はあの当時、必死だった。まさに悲劇の真っ只中にいた。だが、そんな自分の姿は俯瞰して見れば「笑える」。
だから、あくまで淡々と当時の様子を伝えようと努める。
頭木さんは様々な病気を経験した人の体験談に耳を傾けるうちに、病気で辛かった体験は一人ひとりユニークで面白いものである一方、病気で得た教訓は誰もが皆同じような表現になることに気が付いた。
病気のおかげで素敵な人に出会えた。精神的に成長することができた。自分の人生の大切さを知ることができた。それらは患者自身の正直な気持ちかもしれない。
だが、どうしてここまで似通った表現に行き着くのか。考える上でヒントとなったのが、カミュが残した言葉だ。
彼はそこで、その話相手と自分とは、同じことを話していなかったことに気がつくのである。彼のほうは、実際、長い反芻と苦悩の日々の奥底から語っているのであり、相手に伝えたいと思うイメージは、期待と情熱の火で長い間煮つめられたものである。これに反して相手のほうは、あり来たりの感動や市販の商品みたいな悲しみや、十把人からげの憂鬱などを心に描いているのである。
(カミュ, 『ペスト』)
「これは恐ろしい言葉ですよね。僕は、まさにカミュが言ったことが起きてるのではないかと思います。伝わらない経験を積み重ねていく中で、やがては皆に通じる言葉の領域で語ることに慣れてしまう。でも、それはその当人にとって、本当に良いことなのでしょうか?」
「高い山に登った人にしか見えない景色や深い海に潜った人にしか見えない景色があるように、病気をした人にしか見えない景色がある。しかし、この傾向が今後も続けば、ますます社会から病気による発見がなくなっていきます。その人しかしていない貴重な体験やその語りが押し込められてしまいます」
では、どうすれば、病気を患う当事者は自身の体験を閉ざすことなく語ることができるのか。
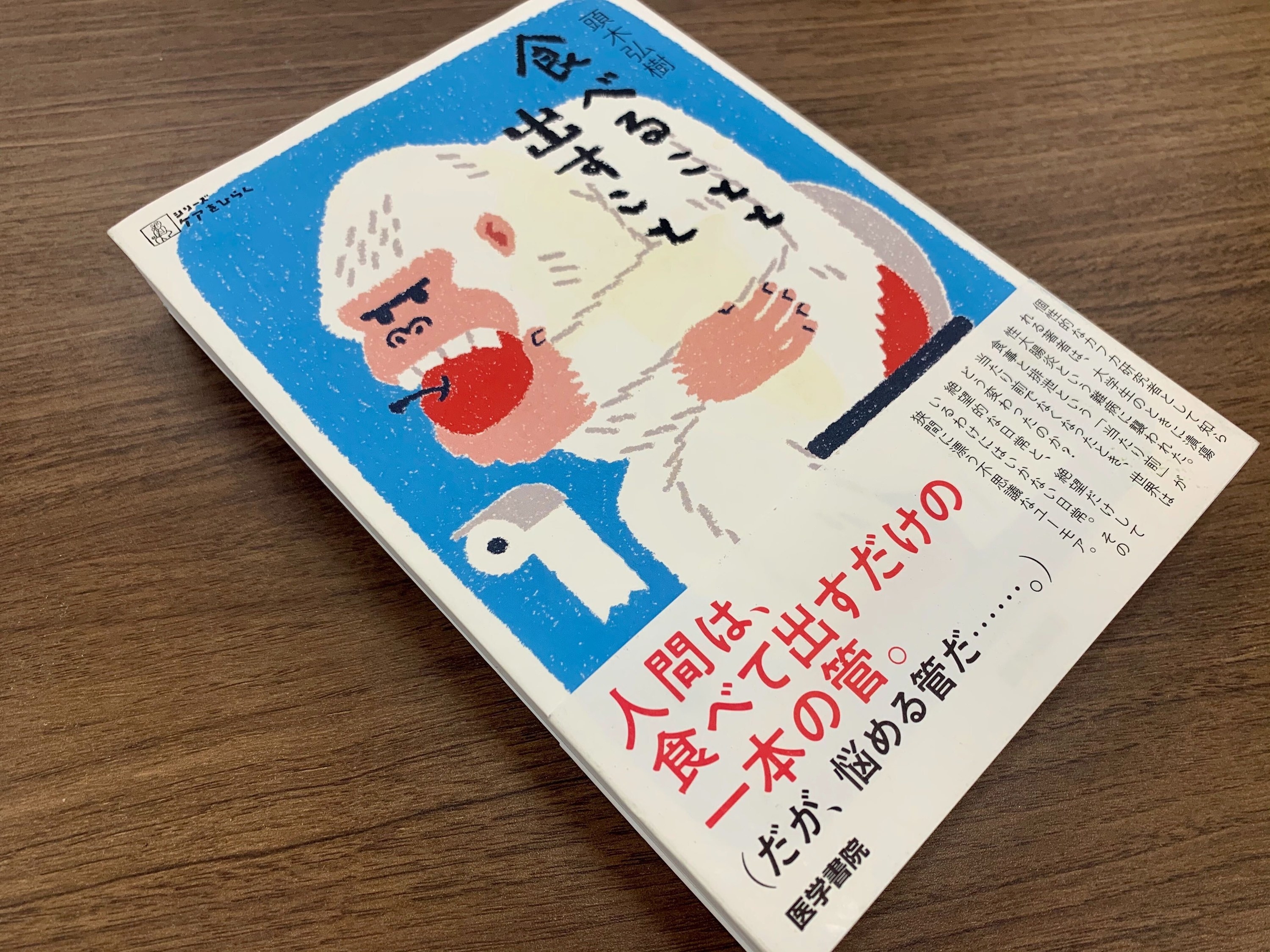
頭木さんが1つの例として挙げるのは、『食べることと出すこと』(医学書院)の編集を担当する編集者・白石正明さんの耳の傾け方だ。
「彼は僕の話をめちゃくちゃ面白がってくれる。普通なら、『そんな大変なことがあったんですか…』と気の毒そうに言うところを、『そんなに面白いことがあったんですか!』と彼は笑ってくれるんですね。でもね、これは失礼なことではないんですよ。彼のおかげで、そうか僕の話はそんなに面白いことなのか、と気付くことができるんです」
純粋な知的好奇心から病気の体験談に耳を傾けること、それができれば病を持つ人が語ることを抑制せずに済むと考える。
病気になることは決して特別なことではないはずだ。
「自分の知らない国へ行ったことのある人の話って面白いですよね。同じように、病気の国に行った人がそこでした経験を、知的好奇心を持って周囲の人が聞いてくれたら良いのではと思います。健康な国の人々の話に合わせるのではなく、そこは違う国の話だと思うことも必要なのではないでしょうか」
6人部屋の病室で知った、「本当のところは誰にもわからない」

ある病気の当事者の話が発信される時、それはあくまで、一人の患者のケースに過ぎない。しかし、そうした実情を正確に理解してもらうことは想像以上に難しい。
病気の種類も、そしてその症状も人ぞれぞれ多様だ。
「一人ひとり症状は違います。他の人はそうでも、私は違う。こうしたことは受け入れられにくい。だって、そんなことを言われてしまったら、どう助けたらいいのかわからなくなってしまいますからね。助けたいと思って声をかけたのに、『傷ついた』と言われるような経験は誰もしたいとは思わないでしょう」
LGBTをはじめ多様な在り方が近年、可視化され続ける中で「多様性疲れのようなものがあるからこそ、私たちの病気を理解してくださいと呼びかけるだけでは難しいのではないか」と頭木さんは言う。
「こうした表現は配慮が足りない」「こうした伝え方をすべき」と認識が刻々と変わっていく社会の中で、「いつ地雷を踏むかわからないのならば、そんな人と向き合いたくはない」という方向に流れてしまう人が生まれてしまうのではないか。
そんな一抹の不安を抱えながら、頭木さんは社会を見つめる。
わかろうとすることは常に過度な一般化と背中合わせだ。それに、そもそも「全てを理解する」ということは不可能ではないか。
自身が患う潰瘍性大腸炎についても、症状が重いケースから軽いケースまで全てを把握することは「当事者ですらできていない」と語る。
ならば、当事者以外にその理解を求めることは無茶なことなのではないか。
患者会など、その病気の存在を伝える活動は重要だが、もう一方で「わからないままに、どう対応するか」という知恵を社会の中に根付かせていくべきと今は思う。

「その人以外には本当のところは誰にもわからないということを、私は6人部屋の病室で知りました。全く違う病気を持つ人が集まる中で、互いに『お前には俺の気持ちはわからない』と散々言い合ってきた。だからこそ、理解するということの難しさがよくわかります」
「でも、『自分以外の人間にはわかるはずがない』と言ってしまったら、そこで終わってしまう。『どんなに辛いか、想像することはできない』『本当の意味でわかることなんてない』と理解することこそ、必要なのだと思います。『わからない』ということがわかるだけで、実は十分なんです」
「本当の理解」というものは果たしてあるのか。そうしたものを掲げてしまった途端、「理解できないものがある」という前提が見えなくなってしまう。
「経験しないとわからない」というのは事実だ。だが、「今、自分の目の前にいる人は自分の想像の及ばない何かを抱えているかもしれない」と思うことで生じる「ためらい」にこそ、意味があると頭木さんは強調する。
「わからないなりでいいんですよ。白黒つけられない、曖昧なところに止める。今は、そうした曖昧さに耐える力こそ必要なのだと思います」

