華道家の片桐功敦さん(45)が福島県南相馬市と浪江町に足を運んだのは、2013年9月のことだ。
すでに震災と原発事故から2年半が過ぎていた。しかし、津波で破壊されたうえ原発事故で手つかずとなった地には、生活の痕跡を伝えるものがまだ、そこかしこに転がっていた。
片桐さんはその場で花を見付け、その場にあるランドセルに、長靴に、車に、花を生けた。生けることで、もはや使われることがない物が訴えるメッセージを、より多くの人に届けようとした。
そんな片桐さんの表現技法に勇気づけられた地元の学芸員がいる。
華道家と学芸員、そして地元に生きる人々。一見交わらなさそうな人々がつながり、震災から10年となる2021年に向けて動き出している。

片桐さんは大阪府在住。「花道みささぎ流」家元の家庭に生まれ、24歳で家元を襲名している。
2013年、原発の周囲20キロ圏で咲いている花を探して生け、写真に収めてほしいという依頼が、福島県立博物館から届いた。
声が掛かった当初は、長く滞在しようとは考えていなかったという。それでも現場に足を踏み入れ、あの光景を見ると、考えは変わった。腰を据えて花を生けずにはいられなくなった。
「本当のところ、そこの土地の人間にならないと、遠慮なく表現することはできないでしょう。遠慮せずに表現しようと思うと、一歩か二歩、中に入っていかないと無理ですから」
「生死の現場」で花を生け続けた理由

南相馬でアパートの1室を確保し、2013年12月から2014年8月末までおよそ8ヶ月を過ごした。当時は原発作業員が多く移り住んでいたため、空室を見つけることは簡単ではない。
「中途半端なことはしたくなかった。どうせ、いつかは作品として発表しなくてはいけないとわかっていた。そのときに自分がわかっていないことを、わかったふりをして口にしたくなかったんです」
心に決めたことがある。「外から何も持ち込まず、何も持ち出さない」ことだ。そこで起こったことを、そのまま生ける。これこそ、自分のすべきことだと感じた。
1人で歩き、花を探してはその場で生け、写真に収めた。だれに言うわけでもなく、そんな活動を続けた。

「あの辺に住んでいる人は、一人ひとりがそれで一本小説が書けるんちゃうかってくらい強烈な体験をしていた。だから、最初の頃は人と付き合うことを避けてました」
「人って共感する生き物でしょう。でも、その家の人のことを知ってしまえば、花が生けられなくなると思いました」
だが半年が経った頃、地元の人に「見つかった」。地元紙の記者が片桐さんのことをどこからか聞きつけ、取材にやってきたのだ。
記者は開口一番、真正面から質問をぶつけてきた。
浜通りで被災した人たちが、あなたがいまやっていることを見て、どういう風に感じると思いますか?
「えらい直球な質問やな、って思いましたよ」。笑いながら振り返る。
だが自分自身、その問いが避けては通れないものだということは、深く理解していた。生半可な気持ちで手を出すことは許されないということも、分かっていた。

片桐さんは小学6年生だった1985年、父親を群馬・御巣鷹での日航機墜落事故で亡くした。父がいないため、24歳という若さで祖父から家元を継ぐこととなった。
だからこそ、人が命を落とした現場で花を生けるという行為が他人の目にどのように映るのかは、自覚していた。活動に不信感を感じる人がいることも想像できる。
それでも「生死の現場」を歩き回って、花を生けた。
「花を生けずにはいられなかったんです」
冷静に、かつ絞り出すように、片桐さんは言う。
「落ちているランドセルを目にして、その瞬間を物語っていると感じたんです。これに生けへんかったら、他の何に生けんねんって」

「こんなこと言うと、不謹慎だって言われるかもしれませんが」、そう前置きしたうえで、南相馬で花を生けた日々は「楽しかった」という。
「言ってしまえば、生けたい花がそこにあって、生けたい器がそこら中に転がっていた。だから続けられたんです」
「重たい題材だけど、同時に得難い時間だったんです」
こうした言葉がエゴイスティックに聞こえることは十分に理解している。
被災地に寄り添いたいと願う人々からの批判が寄せられることも覚悟の上で、片桐さんはあえて当時の気持ちを淡々と吐き出した。

「いままでは、なるべく当たり障りのない言葉で、自分の逃げ道を作りながら喋っていました。でもね、もうやめたんです」
被災の当事者でなければ、「配慮」が働いて言葉に慎重になってもおかしくない。「こんなことを言っていいのか」という自制心が働くこともありうる。
なのになぜ、ここまでさらけ出すことをいとわないのか。
「いまの僕の発言を、地元の人は怒らないだろうって思うんです」

地元の女性に初めて自分の作品を見せたとき、こんな言葉をかけられた。
津波で家族を失ったり、津波の記憶が怖くて、ぐちゃぐちゃになってしまった街を見るのが嫌で、まだ足を運ぶことができない人の代わりにお花を供えてくれたのね。
それまで、行動が正しいのかどうか迷う自分もいた。しかし、この言葉に背中を押された。
「瓦礫と呼ばれてしまうものに花を生けた」片桐さんへの感謝
南相馬での日々を語る上で、欠かすことのできない人がいる。南相馬で生まれ育ち、南相馬市博物館の学芸員を務める二上文彦さんだ。
片桐さんとは同い年。いまでは友人の1人として、仕事の枠を超えた交流を続けている。片桐さんの作品を、南相馬市博物館でも展示した。
二上さんは、アートが何か、震災でアーティストに何ができるかはわからなかった、という。それでも望みを託した背景には、2011年3月11日から抱き続けていた思いがある。
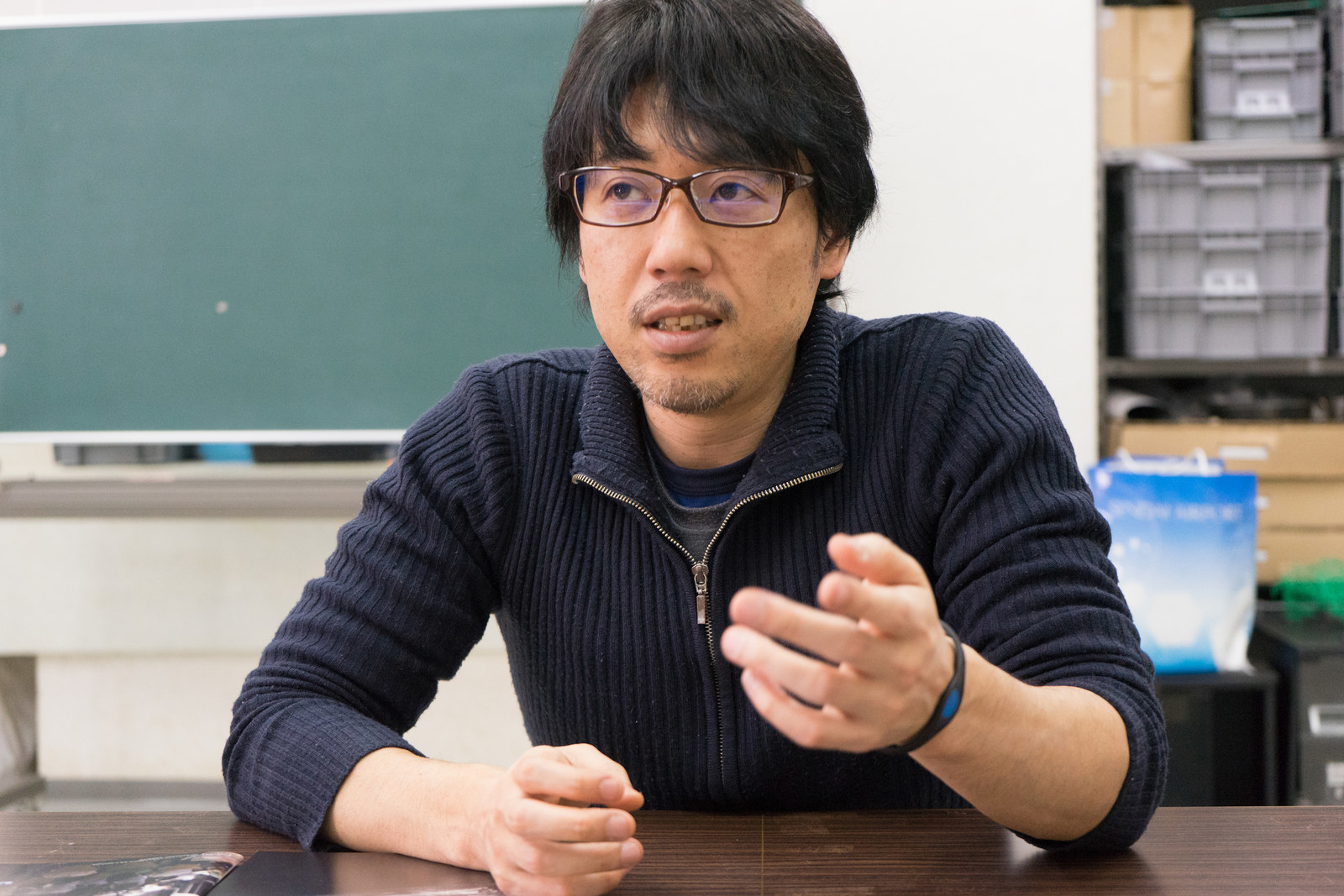
「何を持ってきたらいいんだろうと迷っているうちに、色々なものがなくなってしまった」
二上さんは2011年当時を振り返り、「何も残すことができなかった」とつぶやく。
震災直後、沿岸部には様々なものが流れ着いた。ぬいぐるみやランドセル、靴などが残されていた。これらを記録のために保全することは、学芸員の使命の一つだ。
しかし、もしかしたら誰かがそこにあるものを探しているかもしれない、もしかしたら誰かが取りにくるかも、そんなことが頭をよぎり、持ち出すことができなかった。
「これ以上、視覚的に訴えかけてくるものはない。でも、僕にはそこにあるものを『震災遺構』だと割り切って持ってくることはどうしてもできませんでした。それが学芸員の職務だと割り切れなかった。自分の弱さ、力不足だったと思います」
学術的な「正攻法」では残すことができなかったものを記録する。その役割を託されたのが、アーティストである片桐さんだった。

片桐さんが南相馬と浪江町で生けた作品の写真はまず、南相馬市博物館で展示された。
拒絶反応を示す住民もいた。だが、来場者の反応は想定外のものだった、と二上さんは語る。

凄惨な現場に花をひとつ生けるだけで、全く違う風景が浮かび上がる。写真を見て、綺麗だねと涙を流す人々がいた。
「普通なら『瓦礫』と呼ばれてしまうものに彼は花を生けた。そこにある一つひとつのものは、震災前まで誰かにとっての大切なものだったんです。片桐さんは瓦礫をゴミとして扱うのではなく、大切な花器として扱ってくれた」
展示会で来場者が記入したアンケートを恐る恐る覗くと、つづられていたのは感謝の言葉だった。
誰も言わないことこそ、アーティストが叱られる覚悟でやる

片桐さんは南相馬・浪江で記録した写真をまとめた写真集を『Sacrifice』と名付けた。直訳すれば「生贄」や「犠牲」という意味になる。なぜ、このタイトルを選んだのか。
「人間は、1人で生きることはできない。となると、死ぬこととは、否応なく誰かに何かを伝えることだと思うんですよ。あの場所で亡くなった人たちや失われた物は、いまだに僕らに何かを伝えようとしているはずです」
「そこで発せられているメッセージをどうキャッチしていくのかは、残された僕ら次第なんじゃないでしょうか」

2021年、震災から10年目を迎える福島で個展を開催したいと考えている。
「人間が自然とどう折り合いをつけて生きていくのか、この問いに向き合うことは福島にいなくともできます。そのとっかかりとなる作品をまずは1つ、大阪で展示しました」
除染された土が詰め込まれたフレコンバック。そこから生えた桜の木は満開に咲き誇っている。
「汚染土」から桜が咲いたとき、人はその美しさに心を動かすのか。それとも恐怖の対象として見るのか。
震災から8年。2月下旬から3月上旬まで大阪で開催した個展に登場したこの作品は、見る一人ひとりに重い問いを突きつけた。
福島で見聞きしたこと、出会った人との思い出が血肉となり、いまの片桐さんを支えているという。
「誰も言わないことこそ、アーティストが叱られるのを覚悟でやらないと。全員の問題であるはずのことを福島だけに押し付けている現状は変わりませんから」
2021年に向けて、動き出した

震災から8年、南相馬市博物館では震災と原発事故を真正面から取り扱う展示は避けてきた。市立博物館として、被災した住民も来館することを踏まえて「情報の出し方を忖度しすぎた」と二上さんは振り返る。
だが、「歴史的な出来事である震災と原発事故を福島第一原発に最も近い博物館である南相馬市博物館で取り上げることは、自分たちの使命だ」と決めた。
震災から10年という一つの区切りを迎える2021年に向け、何ができるのかを模索しているという。
「10年目というタイミングを一つの免罪符にして振り返らなくてどうするのか。地元の小学生たちでさえ、もうあの日のことを知りませんからね」

「ちゃんと伝えたい」と二上さんは口にする。だが「ちゃんと伝える」とは、事実を整然と伝えるだけに止まらないという。
「震災前、うちの展示で涙を流した人はいませんでした。人の心に伝わる伝え方って、視覚的なものだったり感覚的なものが占める割合がすごく大きい、とアーティストたちに教えてもらったんですよ」
2011年3月11日にここで何が起きたのか、そしてそこで生きる人々が震災後の日々をどのように生きたのか。目に焼き付けてきた一つひとつを「ちゃんと」伝えるために、二上さんは日々頭を悩ませている。
アーティストからそこに生きる人々へ。バトンはつながった。
BuzzFeed Japanでは、あの日から8年を迎えた東日本大震災に関する記事を掲載しています。あの日と今を生きる人々を、さまざまな角度から伝えます。関連記事には「3.11」のマークが付いています。
東日本大震災の関連記事は、こちらをご覧下さい。

