(この話に登場する人物にモデルはいますが、仮名を使う などご本人とわからないように詳細は変えて書いています)
自分はまだ大丈夫、今日と同じ明日が来る、と信じる病人の気持ち
一瞬視界が真っ白になりました。「ひどく煙った部屋だな」私がロクロウさんの部屋のドアを開け、中を見渡すと、6畳程度の部屋にある使い古したベッドには、痩せた男性がテレビを観ながら、静かに横になっていました。

脇にはたばこの吸い殻が大量に並ぶ、灰皿がありました。ロクロウさんは、私と目が合うと、その躯体とはおおよそ似つかわしくない、鋭い目つきで私を見つめました。
とある病院から、肺がんのロクロウさんのことを初めて紹介されたのは、1週間前のことでした。病院からは、「外来の受診も、入院も、本人を説得しても、全く応じない。家族も困っている。病院としては、何も手助けができない」ととても困っていることがよく分かりました。
私は、緩和ケアを長く専門にし、今も自分のクリニックと、市内の総合病院で働き、主にがんで苦しむ方々を診療しています。自分のクリニックでは、自宅まで往診し、病院に通うことができなくなった方のために、特に緩和ケアが受けられるよう、診療を続けています。
「住み慣れた自宅で最期まで過ごしたい」と強く心に決めて、自宅に療養している方は少数です。多くの人達は、自分が最期にどこで過ごしたいかを、はっきりと決めているわけではありません。
どんな状況になっても、ベッドで寝たきりになり、トイレまで歩くのがやっとになっても、自分の最期はまだまだ先の事、今考えなくて良いと思うのが、病人にとっては普通のことなんだと今の私にはよく分かります。今日と同じ明日が来ると、どんな状況でもずっと思い続けているのです。
なので、病人はいつも自分のことを冷静に、客観的に考える事はできず、どこかのんきです。刻々と状況が変わる毎日の変化をみて、「この先大丈夫なのだろうか」と不安を感じ、焦り、悩むのは、一緒に暮らす家族であることがほとんどです。
どんな状態になっても「自分はまだまだ大丈夫」と病人はいつも考えているのです。
病院が嫌いな人のためでもある、在宅緩和ケア
ロクロウさんは、ずっと以前から1日中タバコを吸い続けていました。「タバコを吸えなくなるので、入院は絶対にしない」と宣言し、病院の医師、看護師、そして家族の説得にも全く応じることはありませんでした。
「この部屋から一歩も動かん」と、自分の住み慣れた部屋でまさに、引きこもってしまったのです。
ロクロウさんは、元々多くの職人を束ねる棟梁でした。昔気質の、ぶっきらぼうなしゃべり方はしますが、男気があって義理人情に厚い方です。ものの話し方は、はっきりとしており、無駄なことは言いません。
一度「こう」と決めたら、もう他人の、家族の言うことは聞き入れません。「もう病院へはいかん」とロクロウさんは、頑なに診療を拒否してしまったのです。
そして、私がロクロウさんの自宅へ往診する事になりました。在宅医療は「家にいたい病人」のためというよりも、「病院が嫌いな病人」のためでもあるのです。病院が嫌いな理由の大きなものは、まずタバコを吸う病人、そして次に多いのが医療者とのやり取りで、心を傷つけられた病人や家族です。

ロクロウさんは、タバコを吸い続けていて、そして病院の医師とのやり取りで、心を傷つけられていました。
肺がんが分かったとき、病院の医師から、「これだけタバコを吸っていれば、肺がんになるのも当たり前です。もう、がんは広がり、またあなたの年齢では治療もできません。仕方ありません。自業自得ですよ。」と言われ、とてもショックを受けたと、家族から予め聞いていました。
ロクロウさんは、私が最初に会ったとき、肺がんのため寝たきりの状態で、壁伝いにトイレまでどうにか移動することがやっとでした。がんの痛みがあり、身体を動かすのもゆっくりでした。
自分が頼ることができる医師はおらず、孤独に苦しんでいたのでしょう。私が最初の診察で、「まず身体を診せて下さい」と言い、聴診器をあてていたときです。「どうせお前もオレを治すことはできんやろ」と怒り混じりに、しかし弱々しい声で言ったのです。
3回目の診察は主治医として認められるかどうかの大切な日
私は、ホスピスで長く働いていたときから、自分の中で決めていたことがあります。それは、診察を始めた病人は、3回会うまでは、とにかく相手の話を聞き続けると言うことです。ただ聞くのではなく、病人の中にたまっている言葉を、引き出せるようにまず心がけます。
「どうせお前もオレを治すことはできんやろ」と言われたとき、こう思ったのです。
ああ、自分は今試されているな、本当に信頼して良いのか、ロクロウさんの面接試験を受けているのだなと。
私はただ、「治せるところはきちんと治しましょう」とだけ答えました。そして、「明日もまた来ます。今日の診察の続きをしましょう」と伝え、出直すことにしました。
次の日、ロクロウさんの家にまた行きました。私は、「昨日の診察から今日まで、短い時間でしたが、どんな風に過ごしていましたか」と尋ねました。病人自身が体験している毎日の時間、そして自分の身体を通じて感じていることを、聞いていきました。
ロクロウさんは、昨日からどんな1日を過ごしていたのか話してくれました。自分の部屋で夕食を食べ、ほとんど残してしまい、風呂に入ろうと思ったけど、自力で入れずあきらめた。夜はトイレに何度も起きて眠った気がしないと。自分から「右の胸が痛く、立ち上がるときに大変だ。お前に何とかできるのか」と最後に言われました。
緩和ケアは、いつも真剣勝負だ
これはロクロウさんとの真剣勝負だと思いました。どれだけがんの医療用麻薬を使い慣れていても、必ず成功するとは限りません。私は、「まず、副作用の少ない普通の痛み止めを使いましょう。そして明後日また診察に来ます」と答えました。
そして、また次の診察の日がきました。また同じように、前回の診察から今日までのことをずっとロクロウさんに話してもらいました。
1日のほとんどをベッドで過ごし、そしてタバコを吸い続けているようでした。「タバコは美味しいの?」と私が尋ねると、「最近は美味しくない。でも他にやることもないからな」と答えるだけでした。
3回目の診察では、ロクロウさんの様子も少し変わってきました。自分から色んなことを尋ねてもいないのに話し始めるのです。
「自分が若いときは、仕事の後、ぱーっと若い衆を連れてな......」と若い頃の景気の良いやんちゃしていた頃の話、「オレにもあちこちに女がいてな......」ととても家族には聞かせられないような話(いつも診察は二人っきりでした)。
そして、こう話し出したのです。
「死なせてほしい」と言われたらどう答える?
「なあ、先生、もうこの病気は治らないし、もう生きている意味がないんだ。先生の力で何とか早く死なせてもらえないだろうか」
真剣なまなざし、表情で話し始めました。
私は末期がんの病人を診療することを長く続けてきたので、かなり多くの方から、同じように「死なせてほしい」と頼まれてきました。以前は戸惑い、「安楽死したい」という病人の願いを、どう現実に実践したら良いのだろうかと悩んだこともありました。
しかし、今は自分なりに、病人から「死なせてほしい」と言われたときにどうしたらよいのか、やっと分かってきました。私は、ロクロウさんの目を見ながら、声のトーンを落とし、そしてこう尋ねたのです。
「どのくらい真剣に死にたいと思っているのですか? もし方法があるのなら今すぐにでも死なせてほしいと思っているのでしょうか?」
ロクロウさんはこう言いました。
「頼む、今すぐにでもやってくれ」
私は、「気持ちは分かりました。確かに聞き届けました」と答え、そして、「その前に、今よりももう少し痛みをきちんと治療させてほしい」と頼みました。
病人の多くは、3回目の診察で大切な話をします。そしてその時初めて、面接試験に合格したことを私は知るのです。
「死なせてほしい」というロクロウさんの言葉は、私が彼の主治医として認められた「合格通知」なのです。医師と病人の間に信頼関係ができると、その時「死なせてほしい」と、心の内を話す関係になるのです。
痛みの治療、緩和ケアは、信頼されてこそ任せてもらえる
「合格通知」をロクロウさんからもらった私はやっと、緩和ケアの医師としてまともな仕事を始めることができました。「がんの痛みの治療をさせてほしい」と私から彼に頼んだのです。
もしかしたらうまくいかないかもしれません。でも信頼関係ができてくれば、きちんとやり直せます。私はロクロウさんの痛みに合わせて、麻薬を処方することにしました。「この痛みは必ず麻薬を使えばきちんととれます。うまくいくように私も努力します。うまくいかなければ直ぐに次の方法を考えます」と伝えました。

その日からさらに数日が経ち、私と一緒に、ロクロウさんの治療とケアに参加している訪問看護師と薬剤師それぞれからも報告を受け、痛みがなくなっていったことを知りました。次の診察では、痛みを感じなくなったロクロウさんは、こう言ったのです。
「前に会ったときは『早く死なせてくれ』と言ったけど、今は気持ちも変わってきた。少しでも長生きしたい。だから頼むな先生。妻の気持ちも以前より落ち着いてきたようだし。前は、家族に迷惑をかけないように、自分が早く死んだ方がみんなのためになる思った」と。
そして、その後もタバコの煙で真っ白になった部屋で診察を続けました。私の予想を超えて、体調は落ち着き、寝たきりの状態は変わりませんでしたが、その後も平穏に日が経っていきました。診察の度に、ロクロウさんは「少しでも長生きしたい」と私に言い続けたのでした。
安楽死を支持することと、自分が安楽死を選ぶことの違い
そしてある日、NHKで、「彼女は安楽死を選んだ」という番組が放映されたのです。
新潟に住む難病の女性が、スイスで安楽死(医師による自殺幇助)を受けた過程を記録した番組でした。登場する本人の言葉には、安楽死に対する信念の強さが、そして戸惑い、悲しみ、迷いながらもスイスまで同行した姉二人の言葉には、女性への慈愛が溢れていました。
私も番組を観ましたが、これを自分の診療している病人が観たら、どう感じるのだろう、どう動揺するのだろう。どんな影響があるのだろうと考えてしまいました。
番組が放映された後に、ロクロウさんの診療に行きました。ずっとベッドに横になってテレビを観ていた彼も、やはりこの番組を観ていたのです。
彼に率直に「やはり、自分も安楽死を受けたいと思いますか?」と尋ねると、彼はこう答えました。
「番組の女性は安楽死を受けたかったんだろうなあ、その思いが果たせて良かったと思ったよ。でも、自分は以前、死にたい、死にたいと言っていたけど、今は少しでも長生きしたい。だからもう安楽死はいらない」と答えたのです。
私は、ロクロウさんの言葉を聞いてある研究を思い出していました。その研究は、2000年に発表されたアメリカでの調査でした。
実際に、末期がんや、寝たきりに近い重症患者(988人)と、その介護者(893人)に、安楽死について尋ねた調査でした。
その結果、患者の60%は、安楽死を支持しているが、自分自身が安楽死を受けたいと考えているのは、10%に過ぎないことが分かりました。痛み、息苦しさやうつ状態にあるとより安楽死を求めてしまうことも分かりました。
また、しばらく経ってからあらためて患者にインタビューをすると、安楽死を自分自身も求めていた患者の半数が、考えを変えていたことが分かりました。
この研究では、患者は実際にどのような治療やケアを受けていたのかは分かりません。しかし、医療者との関わりを通じて、考えが変わっていくことが分かります。
病人の気持ちは揺れ動き、変わるもの それに伴走する緩和ケア
また、私と同じく緩和ケアを専門とする医師は、こんな意見を述べています。
「神経筋疾患の方が、将来、呼吸ができなくなったら、人工呼吸器を使ってまで生きていたくない」と言っていたとしても、実際に人工呼吸器を使うようになり、周囲の医療者や介護者のケアを受け、気管切開の管理にも慣れてくると、再び生活を楽しむ姿を見られることがあります。
大腸がんで、人工肛門が必要になった方も同じようなことがおきます。人は障害などによって生活の質が落ちることに対して、実際以上にマイナスに見積もることが知られています(障害バイアス)。その結果、本人にとって有益な治療を一時の判断で拒否することにもつながりかねません。
ロクロウさんも、私との関わりを通じて、「死にたい」から「少しでも長生きしたい」と考えを変えていきました。私が実践したのは、話を聞くこと、痛みを緩和すること、そして人として彼を尊重することでした。
このような実践が緩和ケアなのです。

緩和ケアでは、病人、家族の話を聞くことの技術を洗練する研究が多くなされています。ただ天性の聴き上手では駄目で、医療のプロフェッショナルなコミュニケーションの訓練をきちんと受け、そしてさらに研鑽していくことで初めて実践できます。
また、医療用の麻薬をきちんと使いこなす技術と経験を身につけること、そして、病人を治療の対象者として見るのではなく、人として尊重し、どのような価値観も受け容れる心構えが必要なのです。
私が最初にロクロウさんと出会ったとき、彼は孤独で、緩和ケアを全く受けられない状況でした。だからこそ安楽死を強く求めていたのではないでしょうか。
安楽死を求めていた彼も、緩和ケアを受けることで、すっかりその考えを変えました。そして、NHKの安楽死に関する番組を観ても、動揺することなく、やはりあの番組の女性のように安楽死したい、再び「死にたい」と気持ちが翻ることはありませんでした。
生きることのつらさを緩和すると、安楽死は考えなくてよくなる
「少しでも長生きしたい」ロクロウさんは繰り返していました。それが本来人間の本当に求めているものであると私は確信していますし、緩和ケアは、治せない病気の人達に対しても、「痛みといった苦痛な症状を、治せるところはきちんと治し、少しでも長生きするため」にあるものなのです。
NHKの安楽死に関する番組を観た病人ではない一般の視聴者は、安楽死ができる社会を歓迎しているかもしれません。「もしも自分があのように病気で寝たきりになったら、もう早く死なせてほしい」と、まだ寝たきりではないときは思うのです。
しかし、現実に本当に寝たきりの状態になったほとんどの人たちは、きちんと緩和ケアを受けていれば安楽死を求めなくなるのです。
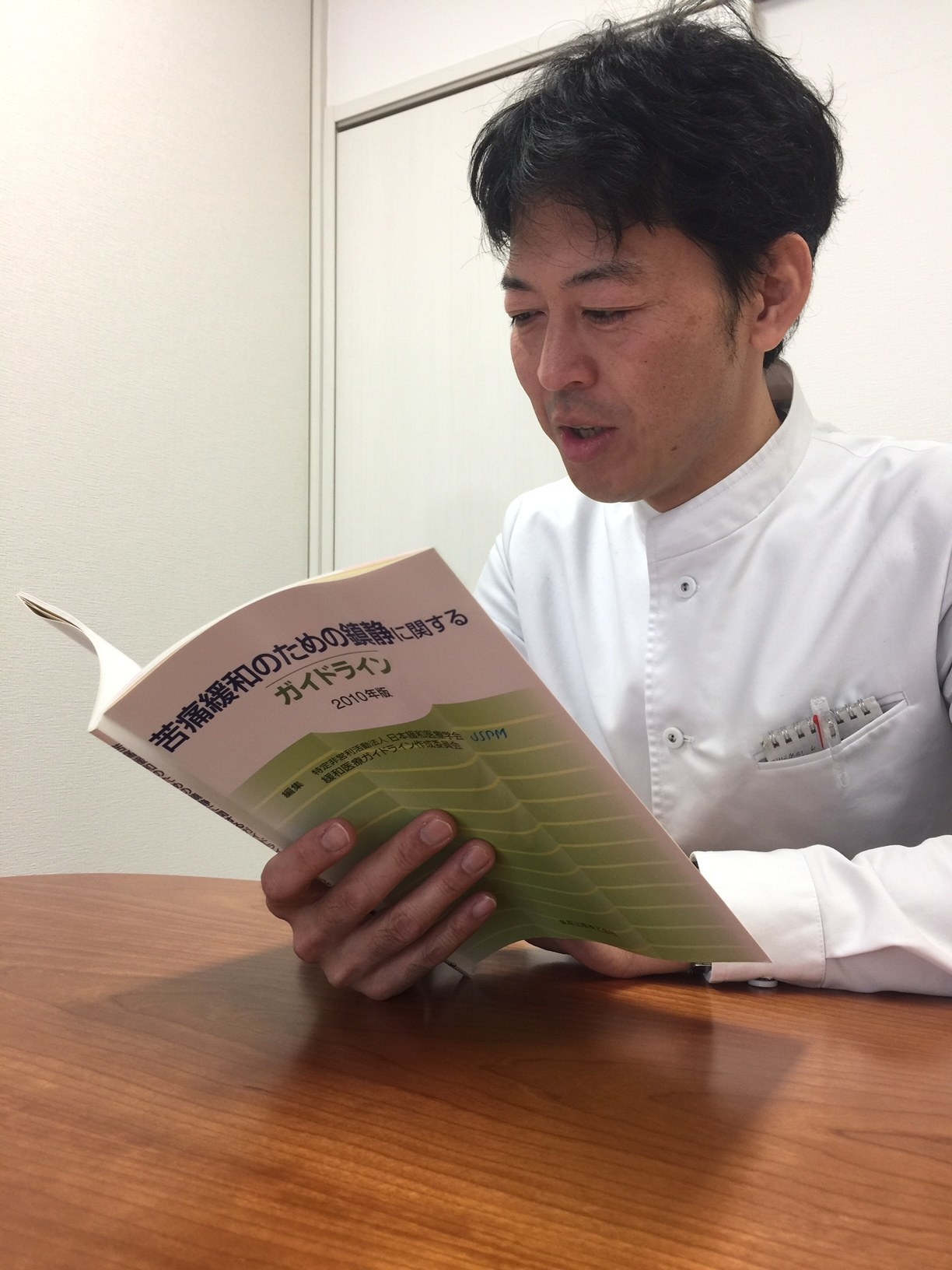
「安楽死を求める個人の願いは叶う社会の方が良い」と主張する一般の方もいます。でも、安楽死はやはり自殺です。医師をはじめとする医療者は、人が自殺しやすい社会に加担してはなりません。
スイスでもカナダでも、ひとたび安楽死を合法化してしまうと、緩和ケアを受けるべき人たちが、ますます受けられなくなることが、分かっています。
現時点で、この日本でも、緩和ケアを受けられる人たちは、一般の病院では、1割にも満たないと報告されています(ただし入院し専門的な緩和ケアを受けている人数)。複数の同僚と様々なデータから検討しましたが、せいぜい全てのがん患者のうち、緩和ケアを受けられているのは2割くらいではないかと推測しています。
ですから、私は、緩和ケアの専門家として、なおのこと安楽死ができる社会を目指してはならないと考えています。
安楽死を願う人達のために、世の中の仕組みを変えることよりも、もっと多くの病人が、いや全ての病人が緩和ケアを受けられる世の中に変えることが、今本当に求められていることなのではないでしょうか。
そのような世の中になるように、がんの診療をしている病院では、通院している患者にも緩和ケアが受けられることを義務づけたり、緩和ケアの学会に患者自身が参加できるようにしたり、私のように緩和ケアを市民の方々に伝えるような機会を増やすようにしてきました。
この国の緩和ケアは少しずつでも良くなっています。「全ての病人が緩和ケアを受けられる」までは、私は安楽死を支持することはできません。
【新城拓也(しんじょう・たくや)】 しんじょう医院院長
1971年、広島市生まれ。名古屋市育ち。1996年、名古屋市大医学部卒。社会保険神戸中央病院(現・JCHO神戸中央病院)緩和ケア病棟(ホスピス)で10年間勤務した後、2012年8月、緩和ケア専門の在宅診療クリニック「しんじょう医院」を開業。著書 『「がんと命の道しるべ」 余命宣告の向こう側 』(日本評論社)『超・開業力』(金原出版)など多数。


