ERの「音」
「いたぁい!」「いたぁぁぁーい!」
10コース50mプールほどの広さのER(救命救急センター)に断続的に響く、甲高い声。80代前半の女性患者、Aさんは「疼痛による体動困難」で救急搬送された。
医学的には血圧が60mmHg、心拍数160の「ショック」。命の危険がある状態だが、Aさんはわずかに意識を保っていた。仰向けで寝ても大きくたるむ腹部から、極度の肥満だとわかる。手足はむくんでパンパンに腫れ上がり、臀部には黒ずんだ皮下組織がのぞく床ずれができていた。
Aさんには重い高血圧と糖尿病の病歴がある。しかし、本人は通院を嫌がり、医療を拒否。家族が自宅で介護していたという。その家族も「これ以上は看きれない」とDNAR(Do Not Attempt Resuscitation)、つまり、もし心肺停止の状態になっても、心肺蘇生を望まない意志を示していた。

肥満とむくみにより、採血や点滴が難しい。刺し直しをする度に、Aさんは繰り返し声を上げる。
「いたぁい!」「いたぁぁぁーい!」
「ごめんなさいねえ」「もう少し、ガマンしてくださいねえ」大きく、聞き取りやすいように一字一句をはっきりと伝える医師の声。
脈拍や血圧などのバイタルサインを知らせる「ピッピッピッピッ」「ポーンポーンポーンポーン」という機械音。時に慌ただしく走るスタッフの足音。
鳴り止まない消防や院内各部署からの電話。そして近づく、次の救急車のサイレン。これらの「音」はつまり、そこに医療者の仕事があることを意味する。
今日もERは「音」で満ちている。
行き先が決まらない患者たち
2019年1月初旬、記者は藤田医科大学病院のERにいた。
同院ERの救急車の受け入れ数は2018年度で約9,500台。今年度は1万台を超えるペースだという。
厚生労働省医政局地域医療計画課のデータ(2016年度実績)によれば、救命救急センターの救急搬送数は平均値4,973人、中央値4,779人。全国的にも上位の施設だ。
特に、一般的には三次救急(重症患者)を中心に担う大学病院のERとしては、かなり多い受け入れ数といえるだろう。地域の医療関係者の間では「“藤田医大病院ER”ではなく“藤田市民病院ER”だ」と揶揄する声もある。
同院がある人口約7万人の愛知県豊明市には、総合病院が他にない。
地域医療を支える柱として、同院救急総合内科教授で救命救急センター長の岩田充永さんは、病院の掲げる「救急搬送は断らない」という方針を現場に徹底する。
また、「ウォークイン」と呼ばれる、自力で救急外来に来る患者が多いのも特徴だ。このようなERは「北米型ER」と呼ばれている。
「何が重症で、何がそうでないか、患者さんにはわからない場合もあります。歩いて救急外来に来た患者さんが、初期の急性心筋梗塞や大動脈解離だった、というようなエピソードは枚挙にいとまがありません」
「救命救急センターは最後の砦でもあります。総合病院がたくさんある大都市と違い、この地域では北米型でなければならない、というのが私の持論です」

救急総合内科所属の医師、約30人が持ち回りで、救急外来・ICU・総合内科の3つの部門を開く。科として43床ものベッドを持つのも珍しい。
これは「救急の他に、がん治療や移植医療など高度医療も担う大学病院では、総合内科のベッドなしではERから患者の行き先がなくなってしまう」(岩田さん)から。これは今の医療の課題だという。
「例えば、高齢の肺炎疑いの患者さんがいたとしましょう。年齢や持病などから総合的に“要入院”と判断したとしても、一般的な病院では縦割りの弊害で『持病は循環器内科と神経内科と腎臓内科。さあどこが入院を担当する?』という話になってしまう」
「その結果、リスクを残したまま帰宅させてしまう可能性さえあるのが現実です」
医療情報サイトm3の調査では、1,763人の医師に対してのアンケートで「臓器別講座(専門科)の弊害を実感したことがあるか」という質問に、勤務医の27%が「ある」と回答している。
医療が高度に専門化する中で、このように「行き先が決まらない患者」が生まれ、その行き場を失くしている現状がある。そうした患者たちを受け入れるためにあるのが、同院の救急総合内科だ。
しかし、この理想を追いかけるがゆえに、現場は時に修羅場となってしまう。
「やばい、止まらない」
1日の救急車は「20台も来ればバッタバタ」と苦笑するのが、日勤ERリーダー医師の都築さんだ。この日は15時までに、すでに30台の救急車が同院に到着していた。
15分から20分に1人のペースで搬送されてくる患者。その度に、採血、点滴の経路の確保、問診、CT撮影への移動、検査結果の確認、カルテのチェック、治療方針の相談……。これらを同時進行でおこなうスタッフは常に、慌ただしく動き回っている。
ERは、4つある少し広めの初療室のほか、リカバリー室、処置室などに分かれている。必要に応じて医療機器やストレッチャーが運び込まれるため、患者がいなければがらんとした空間に、物はほとんど置かれていない。しかし一度、救急搬送を受け入れれば、そこは文字どおり命運を握る医療の現場に変わる。
ほとんどの場所で、ほとんどの時間、なんらかの治療がおこなわれている。平日、日中のERには常時10人ほどの医師(半数は研修医)が勤務しており、看護師の数もほぼ同数だ。
「もうベッド(*ここでは治療スペースの意)ないよ!」「どうする?」看護師たちのやりとりを見やった都築さんが「ここ区切っちゃおうか」と指をさす。その先にあるのは、すでに別の患者の処置が始まっていた初療室の一つだった。スペースはパーテーションで区切られ、患者が運び込まれる。

患者をCT撮影に案内したスキマ時間を逃さず、空いたスペースに新しい患者を入れる。状態が安定した患者は帰宅させるか、入院用のベッドに移す。状況に応じてパズルのように患者を配置することで「救急搬送は断らない」をギリギリの一線で維持するのは、リーダー医師や看護師たちの手腕でもある。
救急搬送は17時ごろピークを迎えた。断続的に鳴り続ける、消防からのコール音。電話を取りに走る研修医が「やばい、止まらない」とつぶやいた。とうとう完全にスペースが埋まる。離れて作業していたスタッフ同士が大声でやりとりをする。「〇〇さんのオーダー、どうなった?」「ごめん、まだだ」――。
救急搬送された患者でも、緊急度が高くなければ、ストレッチャーのままERの隅でひっそり待機となっていた。
いつの間にか、外はすっかり暗くなっている。ERの中心にあるスタッフ用スペースには、電子カルテに接続されたパソコンが並ぶ。そのテーブルに座っていた医師たちの何気ない会話が聞こえてきた。
「先生、朝からでしょ? 帰らないの?」「うーん、今はちょっと、忙しそうだしねえ」
厚生労働省の医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査によれば、週に60時間以上の勤務をする医師は20代・30代男性で57%、20代女性で約半数。
月間80時間を超える残業は一般労働者の過労死ラインとされる。医師はその危険にさらされ続けているのだ。
都築さんもまた、当直の医師との引き継ぎの時間を超えても、治療に走り回っていた。
「日々、葛藤だ」
岩田さんは「疼痛による体動困難」で救急搬送されたAさんについて「日本の医療のさまざまな課題を、ある意味で象徴している」と表現する。
「とことん治療するなら、いくらでもできます。ICUに入院してもらって、がんがん管理して、それこそふんだんに医療費をかけて」
「一方、本人は医療を拒否した経緯があって、家族も延命を希望していない。本人の意識レベルが低い中、目の前の患者さんにどのような選択をするのが最適なのか。私たちは考えなければいけません」
「この患者さんにとっての最適なゴールは」
医師たちは常にこう問う。仮にAさんのゴールを「元の生活に戻ること」に設定したとしよう。幸い、今回は命が助かったとしても、もともと通院を嫌がるAさんは、また医療を拒否するかもしれない。DNARを望んだ家族は、介護の日々に戻れるだろうか。
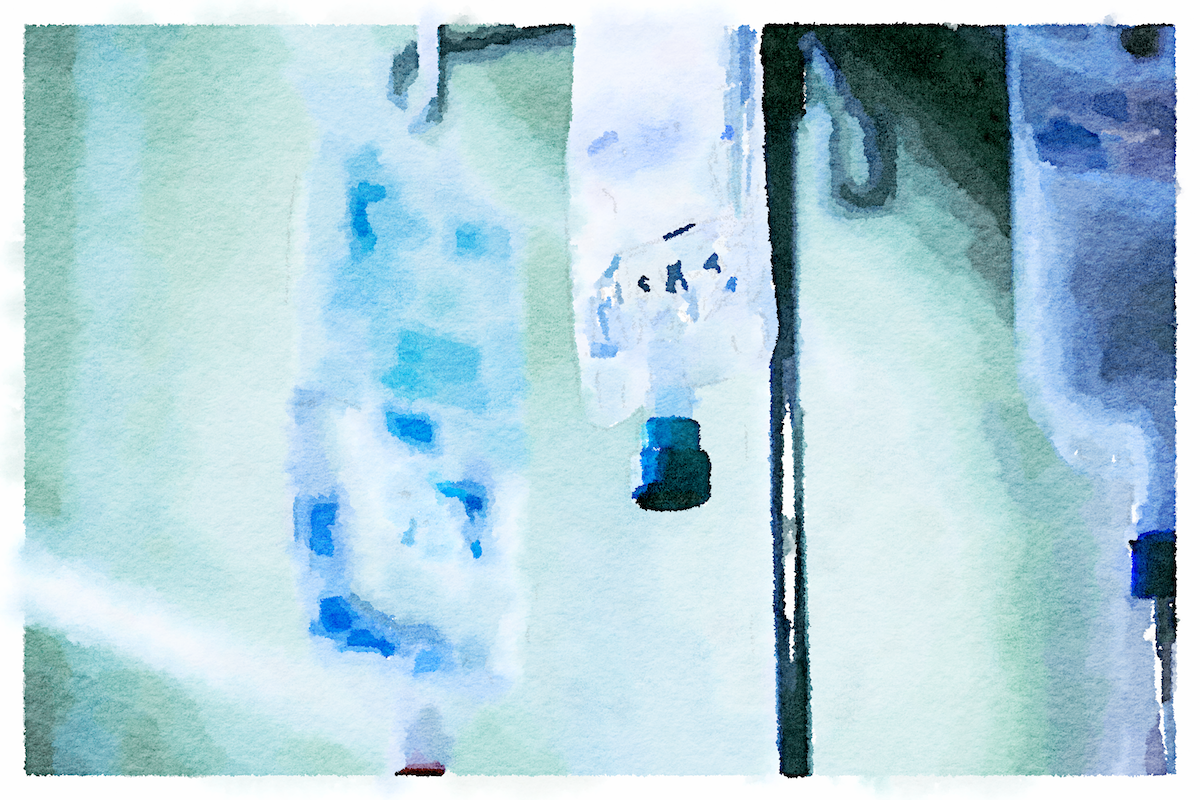
「目の前の命を救うのが医師の仕事だと言われれば、そのとおりです。だから私たちはこの患者さんを全力で治療します。一方で、見ていただいているように医療資源は有限です。私たちの科の病床もギリギリで回っています」
「この患者さんがベッドを使っている間、他の患者さんはベッドを使えません。日々、葛藤です」
医師はただ、長時間の労働をしているだけではない。その瞬間瞬間に、人の命を左右する判断をし続けている。その負担は単に、時間で測れるものではない。
Aさんのショックは、心不全か、感染か、搬送直後では明言できず、さまざまな原因が予想された。もしかしたら、そのすべてかもしれない。ERでの初期対応が無事に完了したとして、危機に瀕した命をどこの科が引き受けるのか。まさに「行き先が決まらない患者」だ。
「結局は、医療者はご家族、あるいは意識が戻った患者さんと話し合い、『こうするのがきっといいんじゃないでしょうか』というところまで治療をするしかないんです」
しばらく沈黙が流れたあと、岩田さんは自分に言い聞かせるように、こう話してくれた。Aさんはその日のうちに小康状態まで落ち着き、救急総合内科のベッドに入院することになった。
死が身近な場所
夜もふける頃、ピークを過ぎたER。スタッフ同士も余裕が生まれたのか、ガヤガヤと雑談をしている。そこに一転、消防からのコールにより、緊迫した空気が流れた。
搬送されてくるのは、救急車内で心肺停止(CPA)状態になった60代後半の男性患者、Bさん。この「CPA」という言葉を、記者はこの取材で、繰り返し何度も聞くことになる。ある人は救命でき、またある人は救命できなかった。
ERは常に死が身近な場所だ。
救急車入口が開いた瞬間、懸命に胸骨圧迫(心臓マッサージ)を続ける救急隊員の姿が目に飛び込んできた。
通路を曲がるストレッチャーの車輪がガラガラと荒い音をたてる。心停止状態を警告する心電図のアラームが鳴り続けている。看護師が胸骨圧迫を交代する。医師が消防隊員から状況の聞き取りをする。Bさんが初療室の一つに運び込まれる。

採血、心電図、点滴などのルートの確保。交代しながら続けられる胸骨圧迫。バイタルサインの機械音、走り回るスタッフの足音が再び、ERに戻る。
担当外のスタッフは、ER内でそれぞれの仕事をしている。必要な人数以上は邪魔になり、手を止めれば別の患者の命に関わるからだ。上級医の指導を受ける研修医、黙々とパソコンでカルテを記入する医師、点滴を準備する看護師たち。
唯一、Bさんのいる初療室の喧騒だけが、点けっぱなしのテレビのように聞こえている。
「シャッ」と初療室のカーテンが引かれた。
カーテンの向こうで、人の動きが急速に少なくなっていくのがわかる。
20分ほど経ったろうか、中の誰かが「奥様が入られます」と言った。看護師に連れられて、女性がその中に入っていく。憔悴した様子の女性の目は真っ赤に充血し、口元をハンカチで押さえていた。
そのほんの一瞬、ERから音が消えた。
Bさんは救命できなかった。Bさんのストレッチャーが運び出された初療室はがらんとしていて、いくつかの医療器械があるだけだ。
静かになったERに再度、鳴り響く消防からの電話。やがて新しい救急車が到着し、ERはまた、音で溢れかえる。
Bさんのいた初療室を覗いてみる。朝、記者が入室したときは、真新しいオフィスのようできれいだと感じたER。
その床には、無数の足跡と血痕が残っていた。
多くの勤務医が過労死ラインの前後で働く現状を背景に、医師の働き方改革の議論が盛り上がっています。一方で、医療の現場で実際に何が起きているのかは、世間にはあまり知られていません。
医療者たちはただ過重労働にあえいでいるのではなく、日々、プロフェッショナルとして患者の命を救いながら、生命倫理と社会的要請との間で葛藤し、自身も一人の人間として、理想の働き方を追い求めていました。
どんな議論も、その実際の様子を知ることから始まります。そこで、BuzzFeed Japan Medicalでは、記者の朽木誠一郎( @amanojerk )が藤田医科大学病院ERに1週間・60時間の密着取材を実施。医療現場の様子を紹介します。

