こんなこと、思い当たりますか?
同じミスを指摘され続ける、遅刻する、上司の指示を聞かない、モノを無くす。空気が読めず対人関係が悪い、じっと席に座っていられない——。
社会人生活で「ダメな人」に認定されがちなこんな行動、実は発達障害の症状とも重なっている。
これまで、スポットがあたりにくかった「大人の発達障害」が注目されている。どこに本当の問題があるのか。
昭和大付属烏山病院院長、ADHD専門外来を担当する岩波明さん(昭和大医学部教授)が語る。
ある営業職、男性の発達障害

ある建設会社の営業職、30代の男性の事例から始めたい。彼は小学校のころ、先生の話を聞いてもメモを取れない一方で、好きなことには熱中した。
友達ができないわけではない。本人は「他の人が話していることがわからない」と思っていたようだが、少し変わっている人だなと思われるくらいだった。
当時の通知表には「落ち着きがない、辛抱ができない」と書かれている。
だからといって、学校生活で大きな破綻をきたしたことはなかった。事実、専門学校を卒業し、経理事務所に就職することもできた。
ところが、である。
問題は就職後に顕在化した。
職場でケアレスミスが多く、同時並行で物事を処理できない。プレゼンで緊張してしまい、どう準備していいかわからない。スケジュール管理ができない。職場で、じっとしていられず動いてしまう。なによりもまず自分の話をしてしまう——。
これまでの生活に問題がなく過ごしていたのに、職場で「問題だらけのダメな人」扱いされることで、つらくなっていった。
「もしかして、自分はテレビで報道されているような発達障害なのではないか」と思い、精神科医のもとを訪れる。
社会生活を送るなかで、問題が顕在化する典型的な「大人の発達障害」の見つかり方だ。
東京都内で開かれた「大人の発達障害」をテーマにしたイベント(毎日新聞出版・リテラジャパン共催)で岩波さんが紹介した事例である。
発達障害ってそもそもなに?
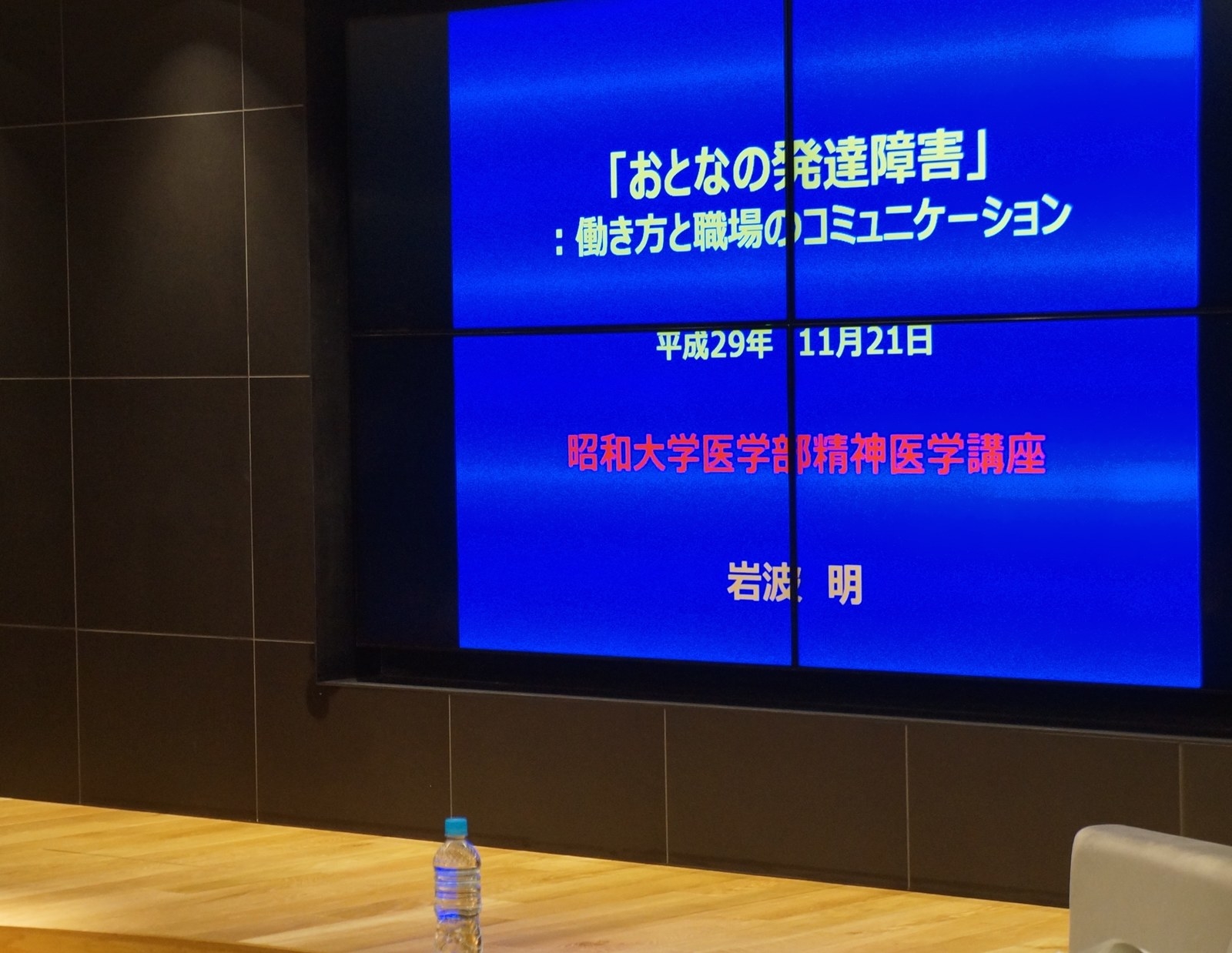
そもそも、発達障害とは何か。
《発達障害とは、特定の疾患をさす言葉ではありません。
対人関係に問題を抱えたり、度を越して特定のものへのこだわりを持つなどの症状があるASD(自閉症スペクトラム障害)。
多動、衝動的な行動、不注意などが特徴のADHDなどの総称です》
大人になるとどのような問題があるのか。臨床経験をもとに話す。
《まず発達障害は珍しいものではありません。特に多いのはADHDです。
彼らは大きなパターンとして、学歴は高いのに、信じられないミスを多発する。
書類作りがうまくいかない、集中ができず人の話がきけないため、上司(特に口頭の指示)が頭に入ってこない。だから、同じ注意を繰り返される。マルチタスクをこなせず、パニック状態になる。
自分の語りたいことを語る。本人に悪気がないのに、人間関係を損なうといったことが挙げられます。
発達障害は基本的に子供時代から同じ症状が大人になっても続いているともいえます。》
岩波さんは近著『大人のADHD』(ちくま新書)のなかでこんなことを書いている。
学生時代までの不適応はみられないものの、就労してから問題が顕在化する例が少なくないし、実際、成人になって精神科を受診する場合は、職場での不適応がきっかけであることが多い。
ADHDの人たちの実生活におけるパフォーマンスの悪さやケアレスミスの多さは、周囲からは本人の問題として否定的に評価され、「真面目に取り組んでいない」「仕事にやる気がない」、あるいは「能力不足」とみなされることが多かった。
その結果、どうなったか。周囲からのストレスによって、うつ病やパニック発作などの症状を併発する人もでてきた。
周囲ができることをできないダメな人認定されてしまい、自分を追い詰め、結果として生きづらくなっているのだ。
自分に当てはまったら?

自分が「発達障害かもしれない」と思ったらどうしたらいいのだろうか?
まず注意が必要なのは、ひとくちに「発達障害」といっても軽度なものから、実生活に重大な問題が生じるなど、個々人によって多様なケースがあることだ。
《発達障害には、いろんなレベルがあります。特に生活に大きな支障をきたしていない場合は診断を知りたいで済むこともあります。
しかし、仕事で明らかなトラブルやミスが続き、それを治したいという場合。それなら診断と治療が必要になります》
治療には薬物治療、認知行動療法などの方法がある。
職場側で気をつけることは何かあるのだろうか?
発達障害の特性を理解し、サポートする職場もあるという。
《本人に向いている職種もあるわけですから、そこに回してあげることができるならそれが一番いい。
前提は会社側にやる気があるかどうかです。ちゃんと取り組みたいという会社もあれば、(発達障害を)ネガティヴなものと捉えて切り捨てる会社もあるのです。
実際に「こういう社員は困る」という経営の論理があることも理解はできますが……。
だからこそ『仕事』のイメージを広げたほうがいいですね。
多くの人は定刻に出社し、決まった席に座り、さまざまな仕事をこなす事務職=仕事と考えがちです。
これは彼らには向いていない。でも、自分でオーガナイズできる仕事で力を発揮するケースもあります》
それは「障害」なのか?
多いとされるADHDもしくは、ADHD的な症状がでる人がうまく働けている仕事、向いている仕事はどのようなものか。
《個人に全部を任されている仕事は向いているといえるかもしれません。私の患者にも、例えばテレビの構成作家、小説関係の仕事をしている人がいます。
過剰なまでに集中する力があるので、任された物事を一気に仕上げたり、コツコツと積み上げていくことができる。
これは個性と捉えることもできますよね。突破力があるとも言える。
対人コミュニケーションに問題を抱えていても、職場で困った人扱いされていても、大事なのは使いようです。
会社の体制がコンプライアンス重視とかになると、もうここで彼らはダメになってしまう。》
苦手なものを無理強いさせるより、能力を最大限発揮できる職場環境を作ることが大事だということだ。
「変わったやつ」とレッテルを貼って遠ざけたり、コミュニケーションに難ありと本人に問題を押し付けたりして終わっても、その先はない。
異質さを大事することで生まれる力
結局、「個性」をうまく使うことができない周囲にも問題があるのかもしれない。岩波さんはこんなことも言っていた。
《こういうタイプが組織にいると、違う視点でものがみえるようになります。うまく個性がハマること、異質さを大事にすることで、組織の力になるんです。》
