1964年の東京五輪、開会式。聖火を灯した最終ランナーは「原爆の子」だった。
広島に原爆が投下された3時間後、同じ広島県内で生まれた、ひとりの青年。戦後日本の「象徴」となった彼が背負うことになった「物語」とはなんだったのだろうか。
あの戦争から76年。そしてあの五輪から、57年。当時の報道や証言などから振り返る。

「聖火リレー最終走者:十九歳の坂井君 原爆の日、広島県生れの早大生 陸連首脳内定」
東京五輪の閉会式の最終走者には、1945年8月6日に広島で生まれた19歳に決まったーー。そう朝日新聞がスクープしたのは、開会式まで2ヶ月に迫った、1964年8月10日のことだ。
青年は、早稲田大の学生だった坂井義則さん(2014年に死去)。競走部に所属する中距離走の選手だった。
朝日は坂井さんについて「広島を一瞬の間に灰とした原爆投下の日に同じ広島県下の三次市で生れた、いわば“原爆っ子”である」と書いた。
「陸連首脳としては、原爆は日本人の“平和祈願”への出発の日であり、(…)世界でただ一つの原爆被災国の日本で開かれるオリンピックに象徴的であり、ふさわしいと考えるに至ったもの」
組織委員会は「戦後生まれ」のランナーを探していたという。1964年の五輪は、戦争からの「復興五輪」だったのだ。
しかし、戦後生まれの高校生のなかに有力な候補は見つからず、白羽の矢が立ったのが、強化指定選手にも指定されながら、五輪の選考会で落選したばかりだった坂井さんだった。
その身長の高さや、フォームの美しさにも定評があり、「カモシカ」との異名もついた。戦後育ちであり、なにより象徴的な出自を持ち合わせていた。
なお当時、最終ランナーは世論の大きな注目の的となっており、「五輪前哨戦」とも呼ばれる壮絶な取材合戦が繰り広げられていた。
朝日は坂井さんを国立競技場に連れ出して写真を撮影。その影響で正式決定が遅れるなど、「マスコミの横暴」と批判の声もあがった。
とはいえ、朝日がスクープで用いた「原爆っ子」やそれを英語にした「アトミック・ボーイ」といった表現は、ほかのメディアにも広がっていった。
「アメリカ人として非常に不愉快です」

「原爆っ子」と呼ばれた坂井さんは、喜びと困惑が混ざったコメントを残している。
「決まった以上、りっぱにやっていこうと思います。ぼくは原爆の日に生まれたことなんか全然意識もしませんでした。でも新しい日本がスタートしてから二十年ですから、その一番目の世代ということは自覚しています」(読売新聞、64年月19日)
「生まれた日が原爆投下の日だから、原爆がどんなにむごいものかは知っています。しかしぼくもふくめてぼくらの世代は原爆ー終戦すなわち新しい時代と考え、平和な時代に生まれたという意識の方が強いじゃないかと思うんです」(毎日新聞、同日)
故郷である三次市は、広島市中心部から60キロ近く離れている。電力会社に勤務していた父親は投下翌日に市内に入った被爆者だったが、当時は報じられておらず、坂井さん自身も後になって知ったという。
また、組織委側には、坂井さんが最終走者を務めることが、「政治的」な受け止めをされるのではないかとという不安もあったようだ。
議論のさなかには「アメリカが悪い感情を持つのではないか」とする意見もあったという。これを制したのが、「ミスター・オリンピック」とも言われる田畑政治氏だ。以下のように述べた、と伝えられている。
「われわれが憎むのはアメリカではなく、原爆そのものです(…)アメリカにおもねるために原爆に対する憎しみを口に出せない者は、世界平和に背をむける卑怯者だ」
とはいえ予想通り、反発はあった。国内からは「原爆を強調したんでは、暗い感じを与えていい気持ちはしない」「あまりに生々しすぎる」「恥ずかしい」「国際感覚が足りない」などの批判があがった。
海外からも否定的な反応があった。知日派の日本学者、エドワード・G・サイデンステッカー氏は、雑誌の対談でこのように苦言を呈している。
「私はアメリカ人として非常に不愉快です(…)どうして原爆と関係づけるのですかね(…)何かアメリカに対してのコンプレックスがあると思うのです」(時事通信・時事解説版、64年7月18日)
さらに米紙・ニューヨークタイムズの投書欄にも「国際親善より敵意をあおるものだ。真珠湾攻撃の当日、そこで生まれた少年を選ぶのと同じだ」という声が寄せられたことがあった、と読売新聞(64年10月11日)は報じている。
「見出しに取りやすいから」
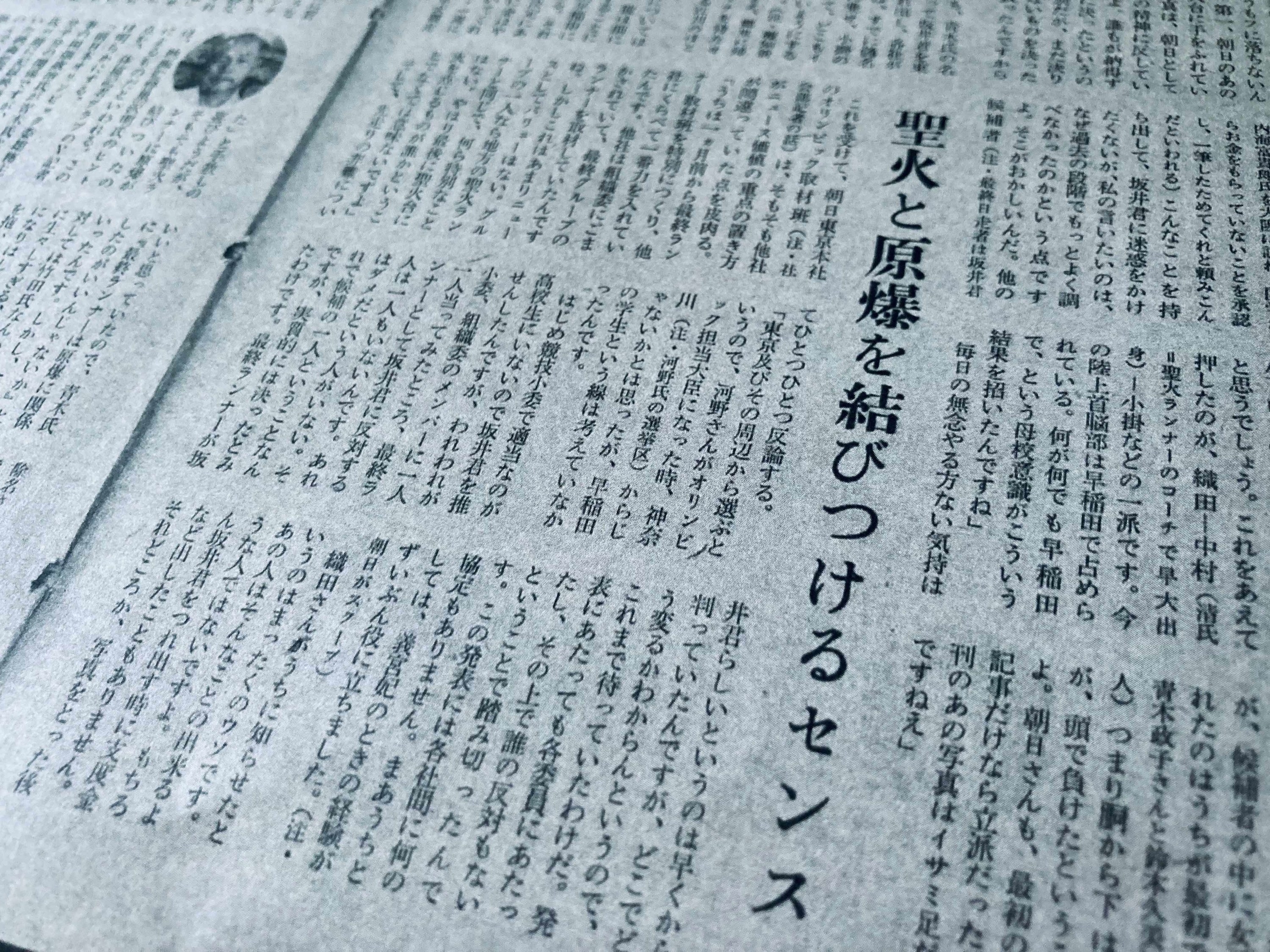
一方で、期待はそれ以上に大きなものだった。たとえば、組織委の関係者は、こんなコメントを寄せている。
「さいわいフォームが美しく、日本に平和をもたらすきっかけとなった広島原爆の日に生まれた(…)いい人が見つかった。われわれの平和の願いをこめ坂井君は最終走者としてうまくオリンピックの聖火を運んでくれると思う」(青木半治陸連理事長)
「東京オリンピックの最高の基調は、原爆のない世界平和の実現ということだ(…)広島県出身にそういう青年がいるのならば、たいへん結構なことだ」(田畑政治氏)
また、読売新聞の編集手帳(64年8月20日)には、このように感情のこもった文章もある。
「戦争をやめて『世界を一つに』という日本民族の祈りと願いを、この原爆の子に象徴するものである(…)原爆ー終戦、それは新しい日本の出発であった(…)坂井君、カモシカのように美しく、平和の階段を聖火を掲げて走れ」
一方の坂井さんはどうか。開会式前日には、同じく読売新聞に「未来の踏み台に」と寄稿を寄せ、緊張や不安をつづっている。
ただ、そこには「原爆」や「戦争」「平和」の言葉はひとつもない。どことなく、自らが「象徴」とされていることに困惑している様子もある。
「なぜぼくが選ばれたか。それは、新しい日本を代表するという意味の年齢とか、あまりにも偶然のことがあったからだと思います(…)手放しで喜んでよいのかどうか、自分でも反省しているのです」
のちにフジテレビに入社し、報道の現場に携わるようになった坂井さんは、自ら平和の象徴として選ばれたことを誇りとして振り返りつつも、少し冷めたコメントも残している。
「自分は原爆投下時に生まれてないし、被爆もしてない。新聞が勝手にタイトルをつけた」(日刊スポーツ、2014年9月11日)
「僕も後でテレビ局で働いてわかったけれど、見出しになりやすいということでしょ」(朝日新聞、2009年12月9日)
「原子力の平和利用」めぐるメッセージも

1964年10月10日、開会式当日。聖火を託された坂井さんは、国立競技場の163段の階段を駆け上り、聖火台のプロパンガスに火をうつした。
その間、180秒。坂井さんは後年、「人生で最高の3分間」だったと振り返っている。
その姿は、多くのメディアなどで賞賛された。たとえば、作家の大江健三郎は、こんな文章を残している。
「ヒロシマの悲惨を背後にひかえて、なお健康にみちあふれた広島生れの青年が、いっさんに聖火台を駆けのぼる光景に、ぼくは感動する。ぼくは愉快だ」
また、坂井さんの人選を「スクープ」した朝日は、こう書いた。
「聖火は平和のシンボルだった。その平和がよみがえる直前に、坂井君は生れた。ピカドンが光って数時間後、広島県三次市だった」
「平凡なサラリーマンの家庭。ロクに食べられない時代もあった。どこの家庭もがたどった道だ。坂井君のいままでの歩みは、日本の若者たちすべての歩みでもあった」
当時はまだ、原爆投下と敗戦から19年。彼の出自に自らの辛い記憶を重ね、「希望」を託す国民は少なくなかったのだろう。
もうひとつ、時代を感じさせるものがある。当時は「原子力の平和利用」が喧伝されていた、ということだ。朝日は、開会式報道をこう締めくくっている。
「外人記者席で、ある記者が『アトミック・ボーイ(原爆の子)がいま平和の火をともした』とタイプを叩いた」
「大観衆のまなざしも原爆の子ではなく、平和の、新しい時代のトビラをたたくく、原子の火であってくれ、との願いがこもる厳粛な瞬間だった」
引き継がれた物語

焼け野原からの復興、そして原子力の平和利用という、ひとつの物語。こうして1964年の聖火は、坂井さんは、新たな時代の「象徴」とされたのだ。
その物語は、いまにも引き継がれている。2020年1月の施政方針演説で、当時の安倍晋三首相は言った。
「8月6日広島生まれ。19歳となった若者の堂々たる走りは、我が国が、戦後の焼け野原から復興を成し遂げ、自信と誇りを持って、高度成長の新しい時代へと踏み出していく、そのことを、世界に力強く発信するものでありました」
「未来への躍動感あふれる日本の姿に、世界の目は釘付けとなった。半世紀ぶりに、あの感動が、再び、我が国にやってきます(…)国民一丸となって、新しい時代へと、皆さん、共に、踏み出していこうではありませんか」
そして、翌2021年。コロナ禍の東京で57年ぶりに聖火を灯したのは、テニスの大坂なおみ選手だった。
ひとつ前のランナーは、東日本大震災の被災地の子どもたち。かろうじて残された「復興五輪」の象徴だ。一方の大坂選手に託された象徴は、「多様性」であるとも伝えられている。そして、コロナ禍の「希望」とも。
生み出された物語は果たして本当に、「新しい時代」をつくり出すものになるのだろうか。戦後76年目の夏、2度目の東京五輪が終わろうとしている。
参考文献
- 〈東京オリンピック〉の誕生: 1940年から2020年へ(浜田幸絵、吉川弘文館、2018年)
- 人間 田畑政治―オリンピックと共に五十年(ベースボール・マガジン社 、1985年)
- 評伝田畑政治: オリンピックに生涯をささげた男(杢代哲雄、国書刊行会、1988年)
- ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑政治(大野益弘、講談社、2019年)
- 週刊サンケイ(扶桑社、1964年8月)
- 週刊現代(講談社、1964年9月)
- 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、時事通信



