<これは世界中の女の子たちに向けた、戦いへの呼びかけです。そう、世界を変える人間になるために、プログラミングを学ぶのです。>
世界12カ国で発売されている女子のためのプログラミング入門本の日本語訳が、「Girls Who Code 女の子の未来をひらくプログラミング」(日経BP)として発売されました。

原著者のレシュマ・サウジャニさんは、主に10代の女子にプログラミングを教えるNPO「Girls Who Code」の創設者。放課後や夏休みにプログラミングクラブを開き、女子中高生の興味を形にする支援をしています。
この本を訳した鳥井雪さんは、ひとりの現役プログラマーであり、2歳の娘を持つ母でもあります。
「日本でもプログラミングに興味を持つ女の子がもっと増えてほしい」――鳥井さんに、本に込めた思いを聞きました。

徹底的に「女の子を応援する」本

――自分が中高生の頃にこんな本が読みたかった! と思える素敵な1冊でした。鳥井さんがこの本に惹かれた理由を教えてください。
やっぱり、徹底的に「女の子を応援してくれていること」ですね。
プログラミングの知識を身につける本はたくさんありますが「これを身につけることで、こんな風に世界が広がるんだよ!」というメッセージに貫かれている本は、私は初めて見た気がします。
すぐに何かが作れるようになる本ではないけれど、「プログラミングでモノを作るとはどういうことか?」の入り口の考え方、そして必要な姿勢を知るにはとってもいい本だと思います。

――ソフトウェアエンジニアとして働く中で、鳥井さんご自身も「女の子を応援する」必要は感じますか?
そうですね、まだまだ男性主体の業界ではあると思います。
世の中はどんどん、プログラミングによって作られたツールで動くようになってきているのに、作る現場に女性がいないとそれだけ女性からの視点が抜け落ちてしまう、という要素はまずありますよね。私が働き始めた頃から比べたらだいぶ変わってきてはいますが!
「女性」という立場だけでなく、人には「その人だから持てる目線・発見できる問題」というのがあると思っています。例えば子育て世代にしか実感できない問題、介護が始まってからしかわからない問題など。
「その人だからわかる問題」の解決を、コンピューターで動くツールに反映させるために、さまざまな立場の人がプログラミングの力を持つことが大切だと考えています。
加えて、私が心配しているのは「そもそも今、女の子の進路の選択肢としてプログラマーが視界に入ってないんじゃないか?」という点です。
例えば、女の子たちが両親や、おじいちゃんおばあちゃんに「女の子だからパソコンなんて詳しくなくていい」「そんなに勉強しなくていい」と言われることって今も少なくないと思うんですよ。お母さんが「ちょっとパソコンわかんない人」として扱われて、自然と自分をそっち側に重ねちゃうとか。
――フィクションの世界でもよくある描写ですね。
「技術者=男性」というイメージのもと、そう言われ続けると少なからず苦手意識を持ってしまうし、「プログラマーなんて自分たちと無縁の仕事だ」と刷り込まれてしまいますよね。
そうじゃない、「向いてない」なんてことないんだよ、女の子たちが自分の手でテクノロジーを学ぶとこんなことができるよ、と何度も何度も伝えてくれているのが、この本はすごくいいなと思います。
だから、女の子自身はもちろん、娘を持つ保護者や、中高生に接する先生にぜひ読んでほしいです。彼女たちが「プログラマーになってみたい」と言い出した時に選択肢を狭めないでほしい、怖がらないでほしい。

応援しながら、応援されている
――本の中で、等身大の問題意識で作られたツールが具体的に紹介されているのが面白かったです。「髪の長さや天気予報を元に今日オススメの髪型を提案してくれるサービス」なんてかわいいものから、「危険なことがあった時用の防犯アプリ」など本格的なものまで。


素敵ですよね!女の子を応援する活動のはずなのに、彼女たちの姿を見ていると逆にこちらが応援された感覚になりませんでしたか? まっすぐで強くてかっこよくて!
――それはすごく思いました! みんなやりたいことがしっかりあって、しかも形にできていてかっこよくて元気が出た……!
ね、そうなんですよ! プログラマーにならなくても「世の中にはこういう手段があるんだ」と知っているだけで、未来の可能性が少し広がるんじゃないかな、と思っています。
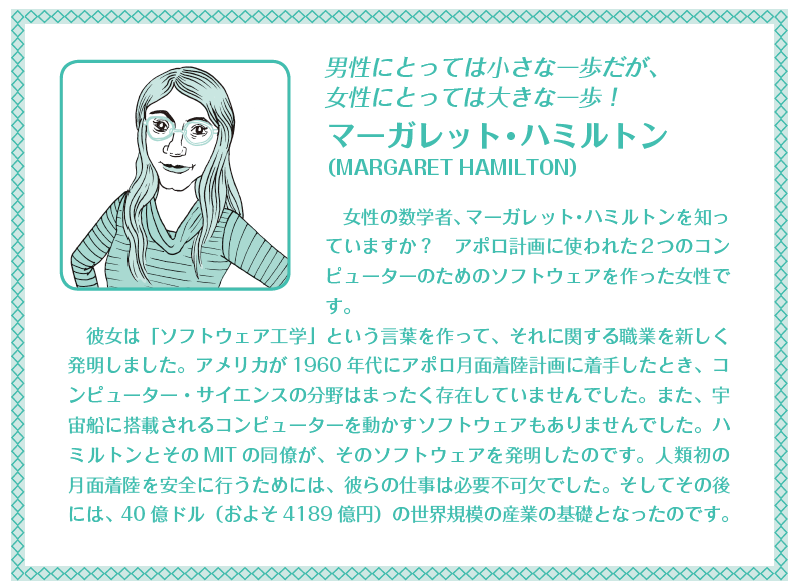
「みんなで幸せになろうよ!」
――鳥井さんご自身は働き始めてからプログラミングを学んだとお聞きしました。
そうです。学生時代は超文系で、初めて勤めた会社で「外国語ができるならプログラミングもできるんじゃない?」と配属されたんですよね。
――(笑)。強引な理論!
今思うとそうですよね(笑)。「できるかできないかわからないけど、とりあえずやってみるか」と始めてみたら、結構楽しくて。
「自分は文系だし」となんとなく敬遠していた世界に飛び込んでみたら、新しい発見があったんですよね。そういう人、きっとたくさんいると思うんです。きっかけさえあれば楽しく取り組める人。

――Webプログラマーは、柔軟な働き方がしやすそうなのもいいなと思います。
それはありますね。場所と時間に縛られにくい点は、女性にオススメできるポイントかも。実際、私も在宅で仕事をしている日もありますよ。子どもが小さいと本当に助かります。
女性が子育てのタスクを多めに持ちがちな社会だというのも一つの問題だと思いますが、そもそも世の中が言う「女性が働きやすい」って、女性だけじゃなくて男性も働きやすい、つまり、みんなが働きやすいってことじゃないですか。じゃあそこに合わせていこうよ、みんなで幸せになろうよ! と思いますね。
そういう意味でも、この業界にもっと女性が増えてほしいです。いろんな人がいろんな都合を持ち込みながら、解決していけるといいですね。
不完全さを受け入れる
――刊行にあたって書かれていたブログで、一番好きなのは「デバッグ」の章とおっしゃっているのがよかったです。確かにアツかった!
そう、アツいんですよ、デバッグの章! 訳していて一番楽しかったのはここでした。
――もはや、人生論のようなスケールでしたね。
女性っていうのは、いつもいろんな種類の矛盾したメッセージを受け続けてる。女性に何ができるか、できないとかいう話題でね。良い子でいなければならない、感じ良くなければいけない、規則は守らなきゃ、親しみやすく、優しく、親切で、すてきで……完璧でなきゃ!
わたしから言わせてもらえば、そう、大人の、仕事を持った女性で、母親でもあるわたしの言うことを信じてほしいんだけど、完璧な人間なんていない。
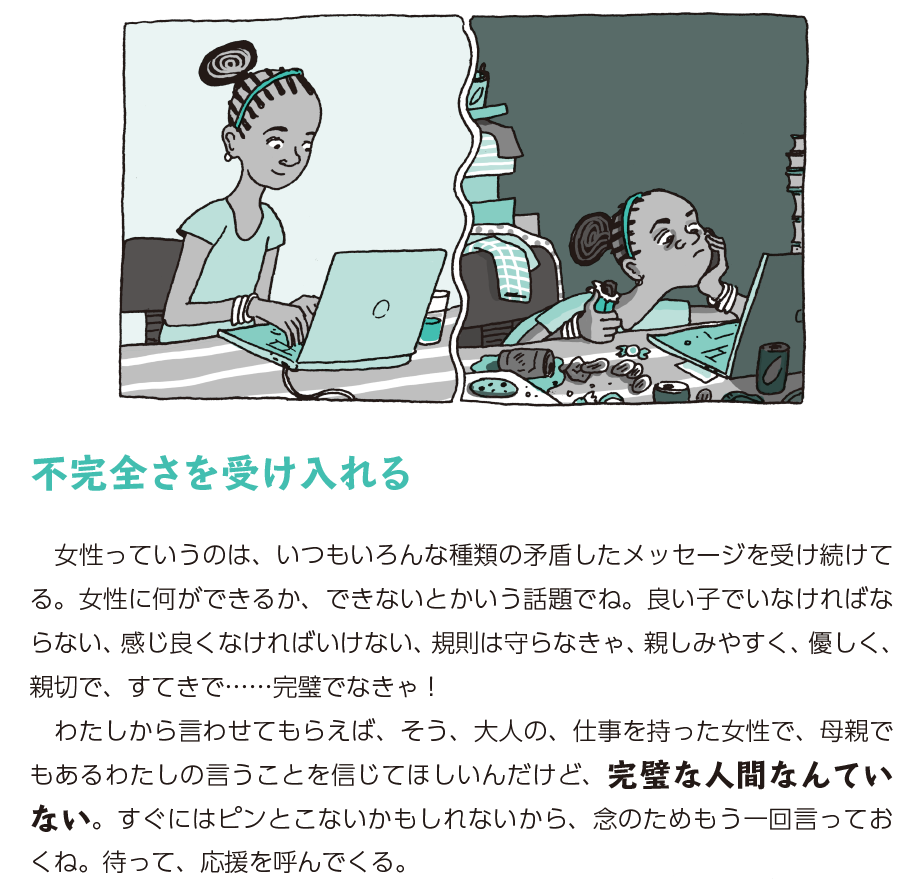
一番大事なのは、自分に優しくすること。ミスはするものだと思っておく。きっとやり遂げられる、理解できる、それから、完璧じゃなくても大丈夫だって自分に言ってあげよう。
プログラミングって、最初からいきなり上手くいくことってまずないんですよ。トライ&エラーを繰り返せることが何よりも大事で、失敗していいんです。いきなり正解しなくていい。
まずは、小さくてもいいから何か作ってみる。失敗することに慣れる。わからないことは誰かに助けてもらって、自分がわかることは惜しまず教える。
これって、プログラミングに限らず、生きていく上で大事な姿勢だと思うんです。バグとの向き合い方は、実生活にも絶対に役に立つんですよ。
単なる技術だけでなく、考え方や「人といっしょに何かをやりとげる」というのがどういうことかを学べるのがプログラミングの素敵だなと思うところのひとつです。
――最初から「失敗して当たり前」という心持ちでいれば挑戦しやすいですね。
コンピュータのいいところは、いくら間違えても怒らないところ(笑)。どんなひどいコードを書いても、無茶を言っても、同じことを言えば同じことを返してくれる。嫌われないし、怒られない。一番失敗しやすいパートナーですよ!
YouTubeでこの動画を見る
「女の子は完璧さよりも勇気を」。原著者のレシュマ・サウジャニさんはTEDでもこれに近い内容をスピーチしている
いつか「時代遅れだよ」になればいい
――この本も含め、今、特別に「女の子」だけにメッセージを送ることには意味があると思いますか?
思います。なぜなら、現状にどうしようもなく差がありすぎるから。
「プログラマーになりたい」と思った時に、「ええ、女なのに?」という言葉をはねのけるエネルギーが必要な立場と、積極的に「頑張れ!」と応援してもらえる立場だと、その道を選ぶハードルの高さがまったく違いますよね。
医学部の不正入試問題なんかもありましたが、この社会に男女差別は当たり前のように横たわっていて、「女の子なんだから」という意識の人もまだまだ根強くいる。男女で違いすぎるスタートラインを合わせていく努力は、たゆまず必要だと思います。
もちろんその先に「そんなの時代遅れだよ」という時代が来たらいいなとも思います。10年後、うちの娘が中学生になる頃には……少しでもそうなっていたらいいですね!
願わくば、この本がたくさんの女の子や、その進む道を応援したくてやり方がわからなかったり、プログラミングってものに戸惑ってる大人たちを励ます力になりますように。
それから10年後や、もっと先でも、あなたが「女の子だけへの応援なんてもういらないよ、時代遅れだよ」っていつか笑ってくれますように。(鳥井さんのブログより)

